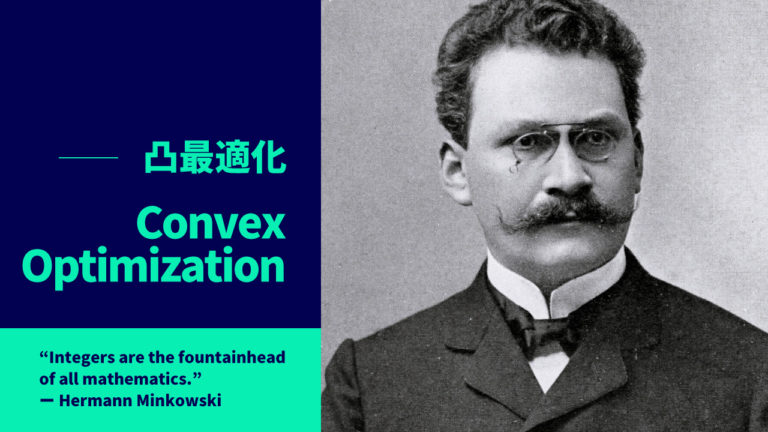
1変数関数の凹最適化問題の解
1変数関数の凹最適化問題の内点解が満たす条件を劣勾配(劣微分)を用いて特徴づけます。微分可能な凹関数に関して、これは最大化のための1階の条件と必要十分です。
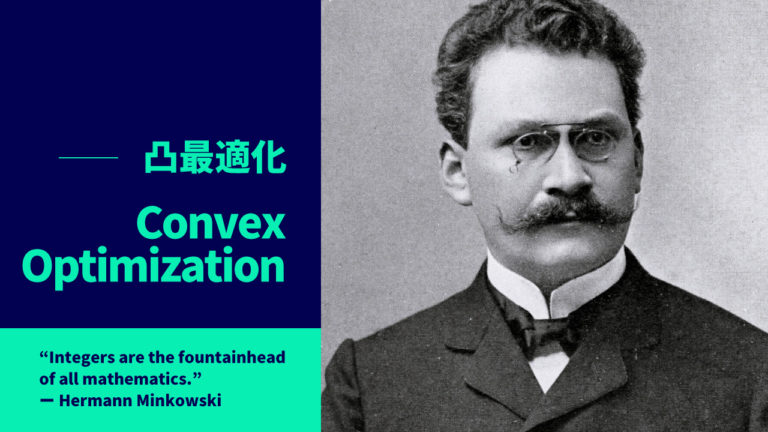
1変数関数の凹最適化問題の内点解が満たす条件を劣勾配(劣微分)を用いて特徴づけます。微分可能な凹関数に関して、これは最大化のための1階の条件と必要十分です。
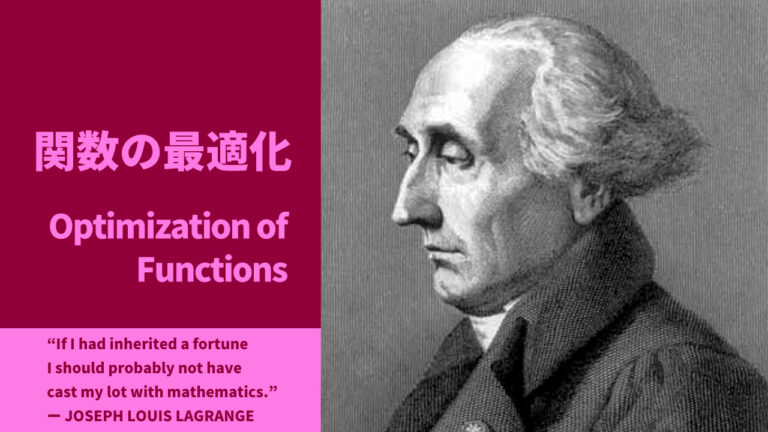
多変数関数の変数がとり得る値の範囲が複数の線型不等式によって制限されている場合に、関数の最小点が満たす条件(クーン・タッカー条件)を特定するとともに、最小点を具体的に導出する方法(ラグランジュの未定乗数法)について解説します。
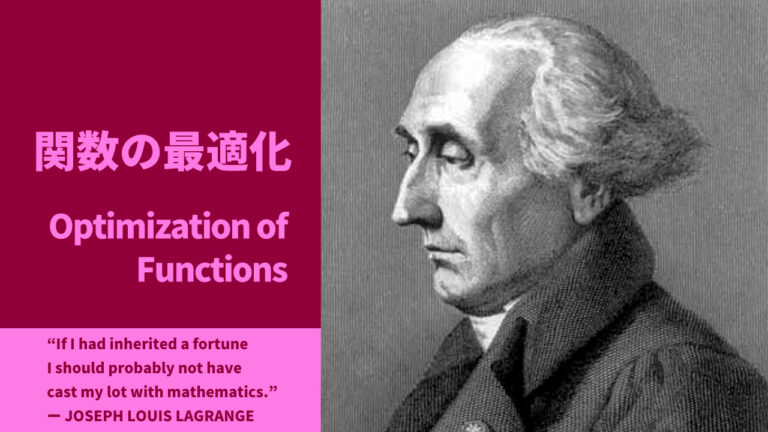
多変数関数の変数がとり得る値の範囲が1本の線型不等式によって制限されている場合に、関数の最大点が満たす条件(クーン・タッカー条件)を特定するとともに、最大点を具体的に導出する方法(ラグランジュの未定乗数法)について解説します。
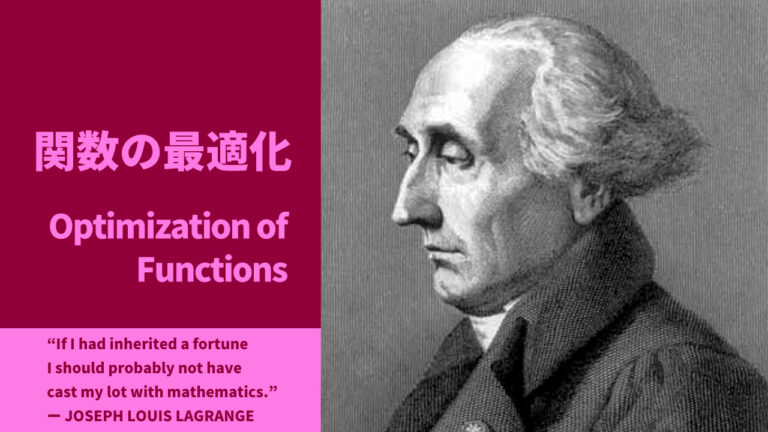
多変数関数の変数がとり得る値の範囲が1本の線型不等式によって制限されている場合に、関数の最小点が満たす条件(クーン・タッカー条件)を特定するとともに、最小点を具体的に導出する方法(ラグランジュの未定乗数法)について解説します。
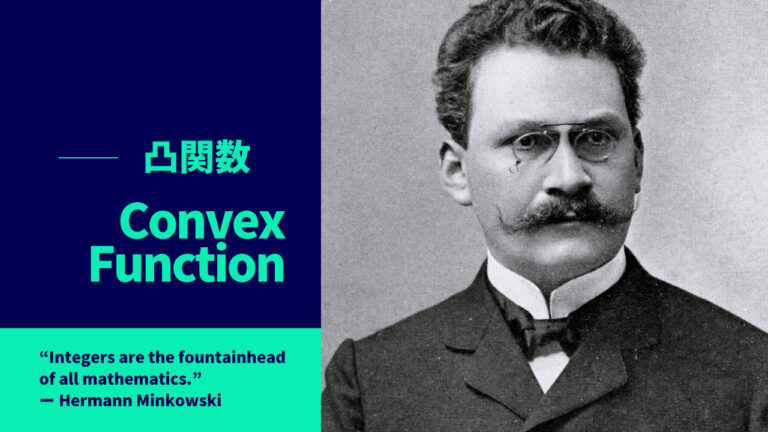
多変数の凸関数や凹関数の内点における劣勾配と呼ばれる概念を定義するとともに、その関数が内点において全微分可能である場合、そこでの劣勾配と勾配ベクトルは概念として一致することを示します。
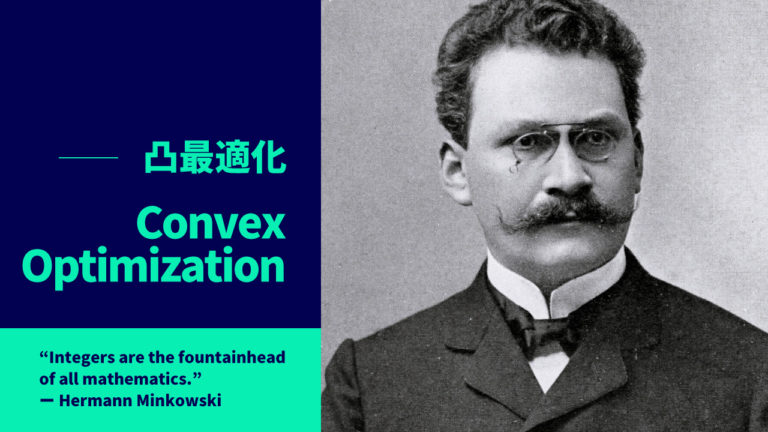
1変数関数の凸最適化問題の内点解が満たす条件を劣勾配(劣微分)を用いて特徴づけます。微分可能な凸関数に関して、これは最小化のための1階の条件と必要十分です。
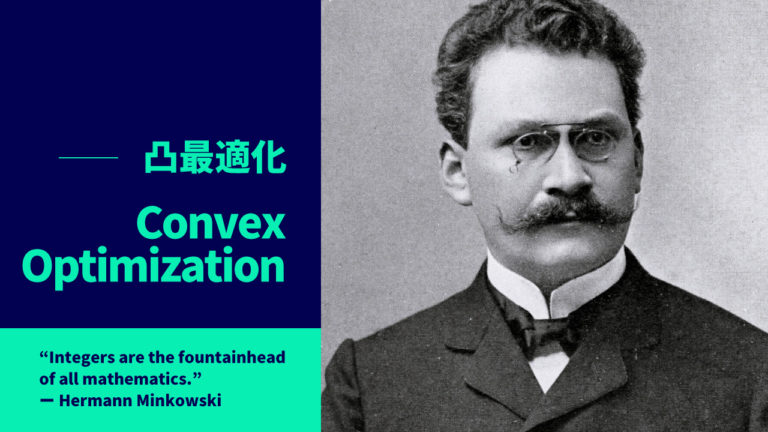
制約集合が凸集合であり目的関数が凸関数であるような制約条件付き最小化問題を凸最適化(凸計画問題)と呼び、制約集合が凸集合であり目的関数が凹関数であるような制約条件付き最大化問題を凹最適化(凹計画問題)と呼びます。
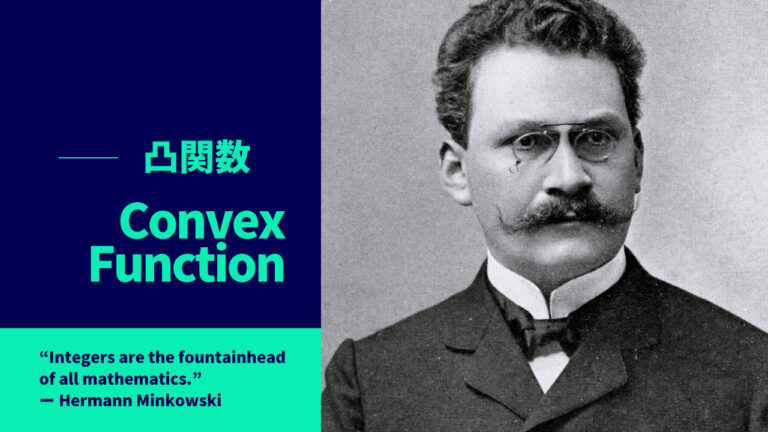
1変数の凸関数や凹関数の内点における劣勾配と呼ばれる概念を定義するとともに、その関数が内点において微分可能である場合、そこでの劣勾配と微分係数は概念として一致することを示します。
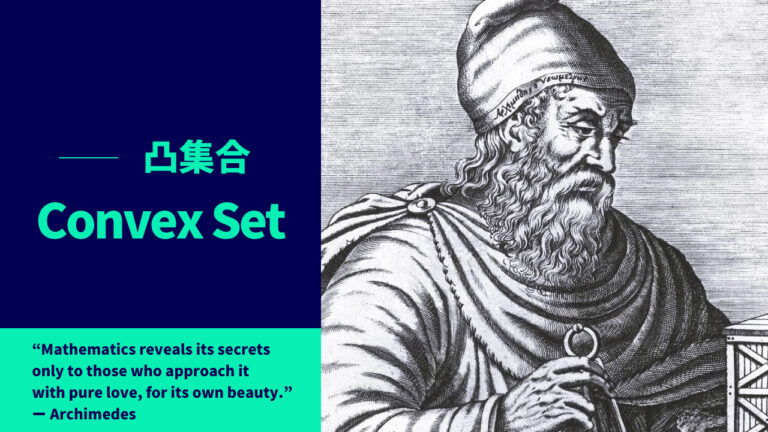
ユークリッド空間上の2つの集合が超平面によって分離されることの意味を定義するとともに、非空かつ互いに素な2つの凸集合は何らかの超平面のもとで必ず分離可能であることを示します。
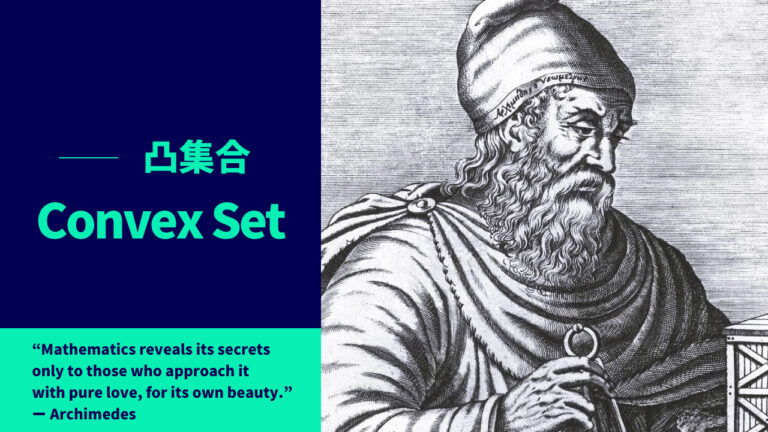
ユークリッド空間上の点と集合が超平面によって分離されることの意味を定義するとともに、非空な凸集合とその集合に属さない点は何らかの超平面のもとで必ず分離可能であることを示します。
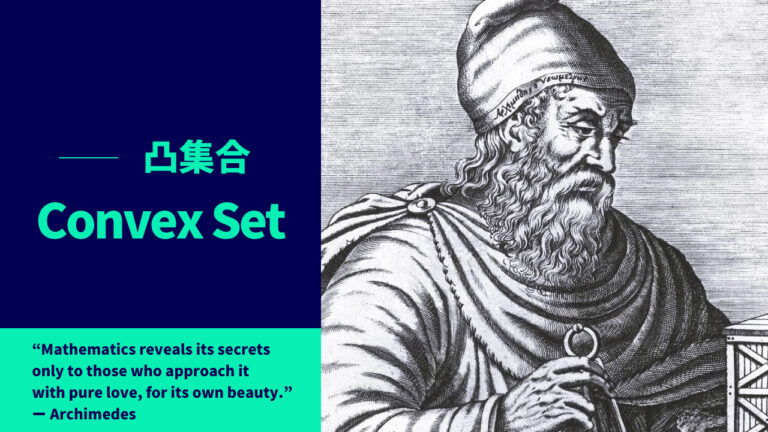
ユークリッド空間上の集合が超平面によって支持されることの意味を定義するとともに、非空な凸集合はその任意の境界点において何らかの超平面のもとで必ず支持されることを示します。
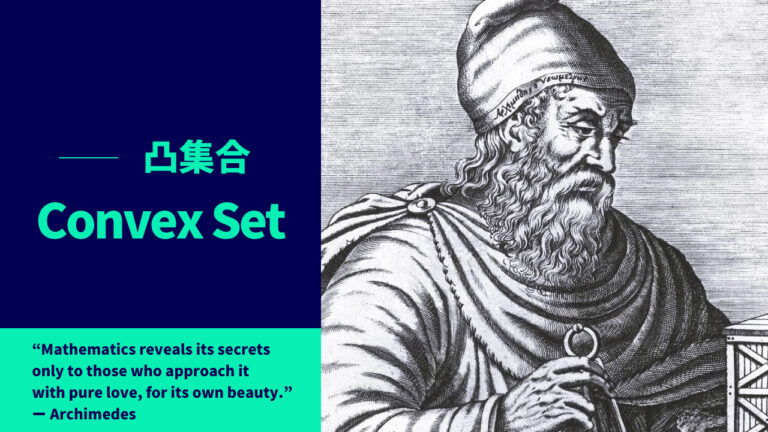
ユークリッド空間上の点と集合が超平面によって狭義分離されることの意味を定義するとともに、非空な凸集合とその外点は何らかの超平面のもとで必ず狭義分離されることを示します。
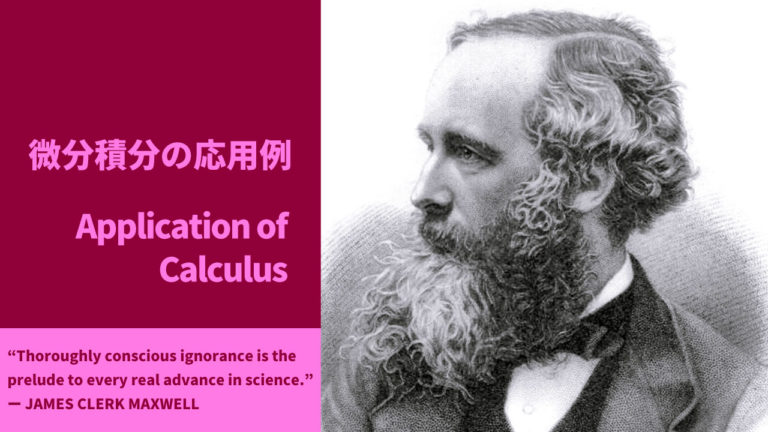
自然対数関数や自然対数などの概念は積分を用いて定義することもできます。その場合にも、自然対数関数の微分に関する既知の性質や対数法則などがそのまま成立します。
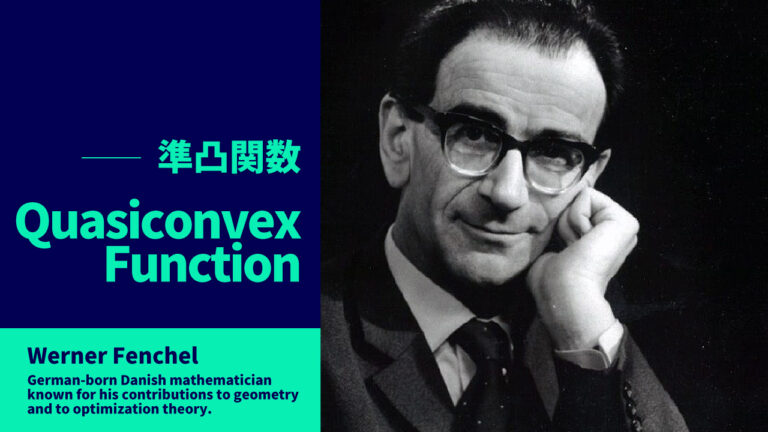
1変数関数が連続な狭義準凸関数である場合、任意の下位集合は狭義凸集合または空集合になります。また、1変数関数が連続な狭義準凹関数である場合、任意の上位集合は狭義凸集合または空集合になります。
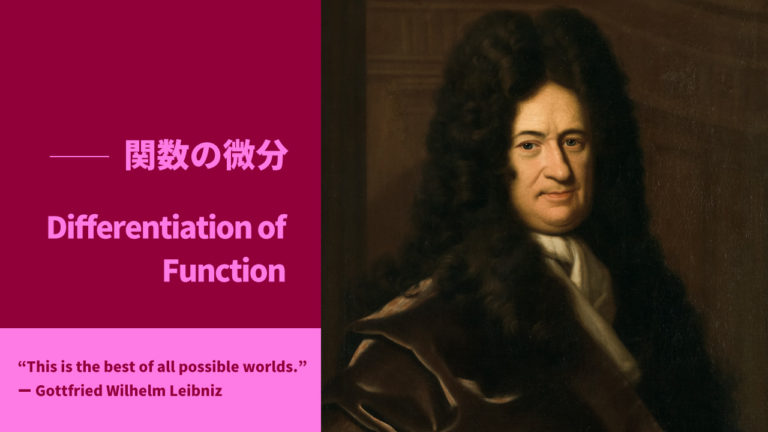
自然指数関数とは限らない指数関数がテイラー(マクローリン)展開可能であるための条件と特定するとともに、そのテイラー(マクローリン)級数を特定します。
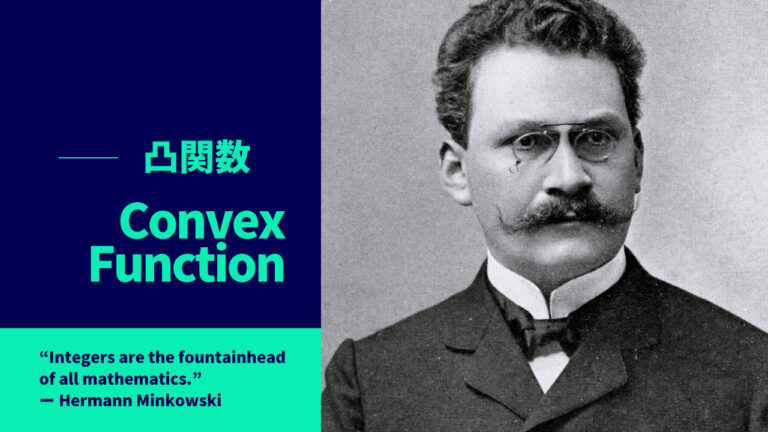
多変数関数が凸関数であることとその関数のエピグラフが凸集合であることは必要十分であり、多変数関数が凹関数であることとその関数のハイポグラフが凸集合であることは必要十分です。
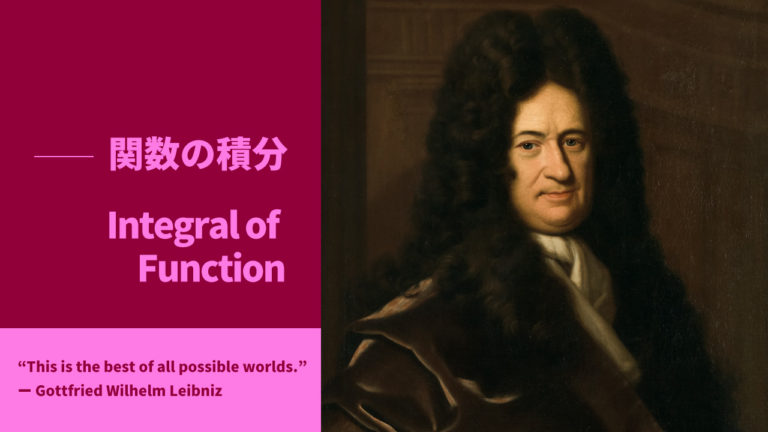
区間上に定義された関数の不定積分ないし定積分を具体的に特定することが困難である場合でも、被積分関数が複数の関数をあるパターンのもとで組み合わせる形で表現されていることに気づいた場合には、それを容易に積分できます。
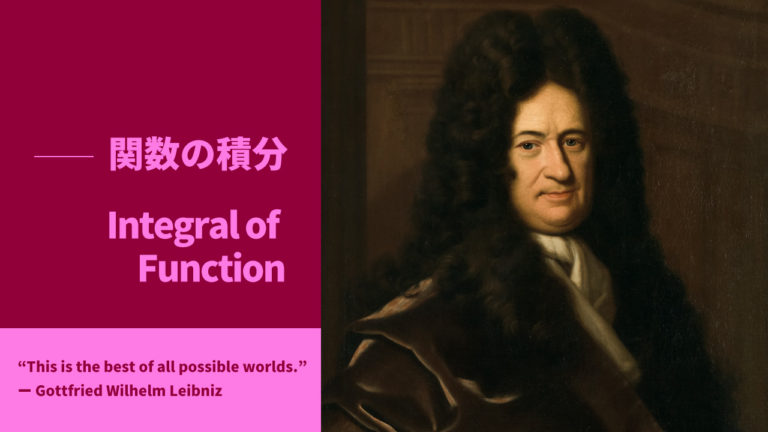
区間上に定義された関数の不定積分ないし定積分を具体的に特定することが困難である場合には、被積分関数の変数を適切な形で変換することにより容易に積分できるようになる場合があります。
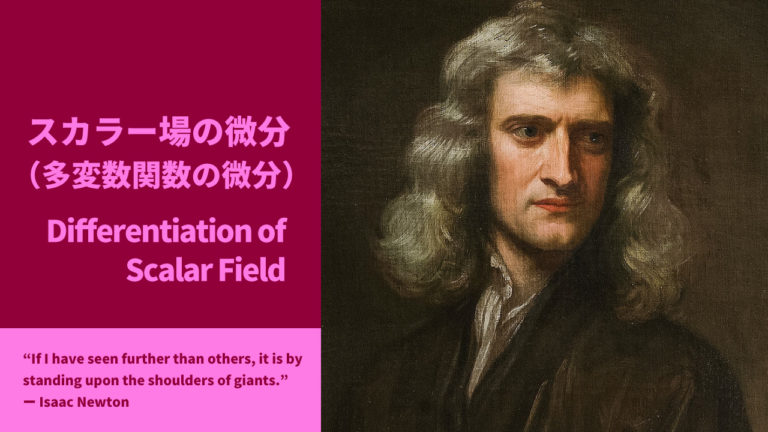
多変数関数が高階連続微分可能である場合に、その関数をテイラーの近似多項式によって近似できることの根拠を与えるのがテイラーの定理です。

逆正接関数(arctan関数・アークタンジェント関数)や逆正接関数との合成関数について、その極限、片側極限、および無限大における極限を求める方法を解説します。

逆余弦関数(arccos関数・アークコサイン関数)や逆余弦関数との合成関数について、その極限、片側極限、および無限大における極限を求める方法を解説します。

逆正弦関数(arcsin関数・アークサイン関数)や逆正弦関数との合成関数について、その極限、片側極限、および無限大における極限を求める方法を解説します。
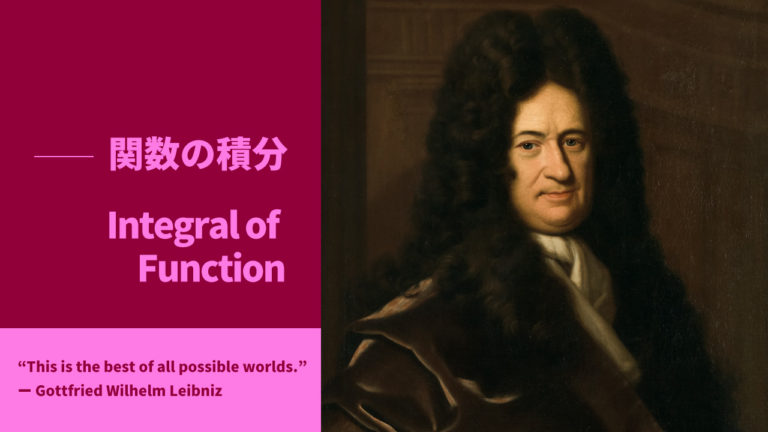
有界な閉区間上に定義された関数がリーマン積分可能であり、その関数の原始関数であるような連続関数が存在する場合、原始関数が区間の端点に対して定める値の差は、もとの関数の定積分と一致します。
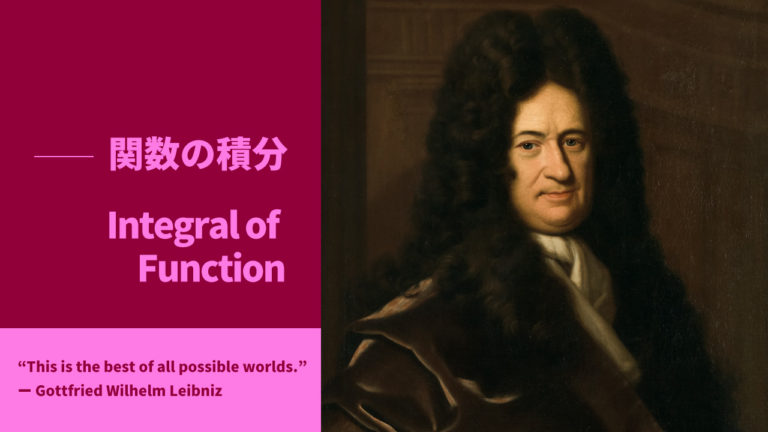
有界な閉区間上に定義された連続関数に対してその平均値を定義するとともに、連続関数が定義域上の少なくとも1つの点に対して定める値が平均値と一致することを示します。
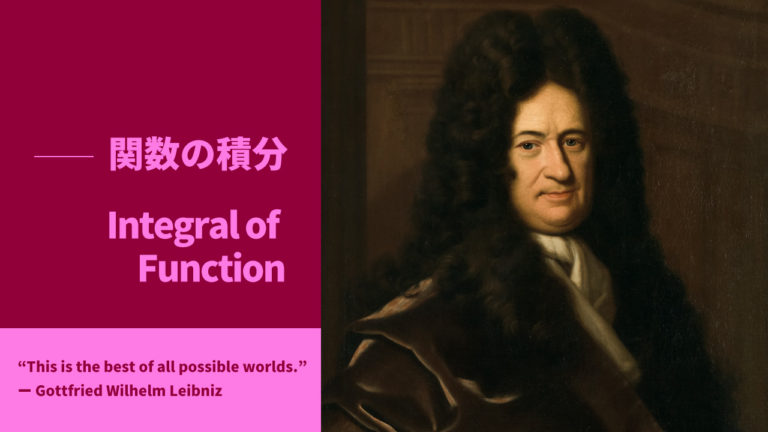
有界閉区間上でリーマン積分可能な2つの関数について、一方の関数が定める値が他方の関数が定める値以上であるとき、両者の定積分の間にも同様の大小関係が成り立ちます。
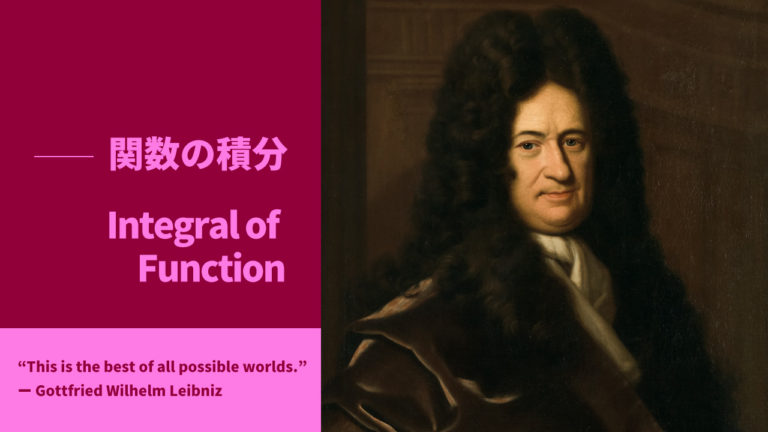
有界な閉区間上に定義された有界な1変数関数がリーマン積分可能であることを判定するために関数の振幅と呼ばれる概念を用いる手法を解説します。
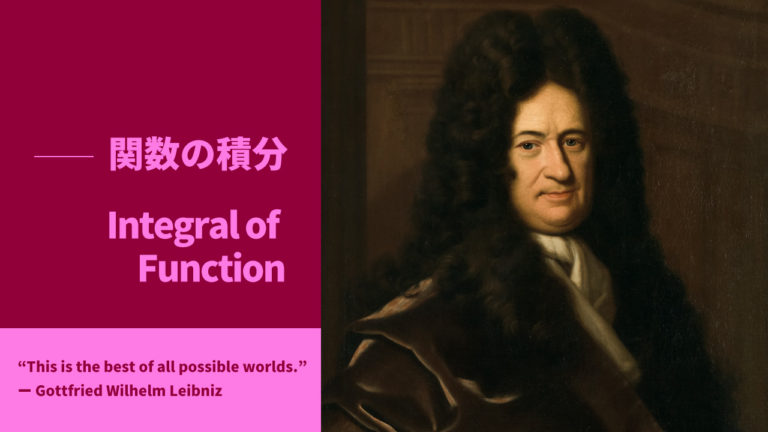
リーマン積分可能な関数の和として定義される関数もまたリーマン積分可能であり、もとの関数の定積分の和をとれば新たな関数の定積分が得られます。