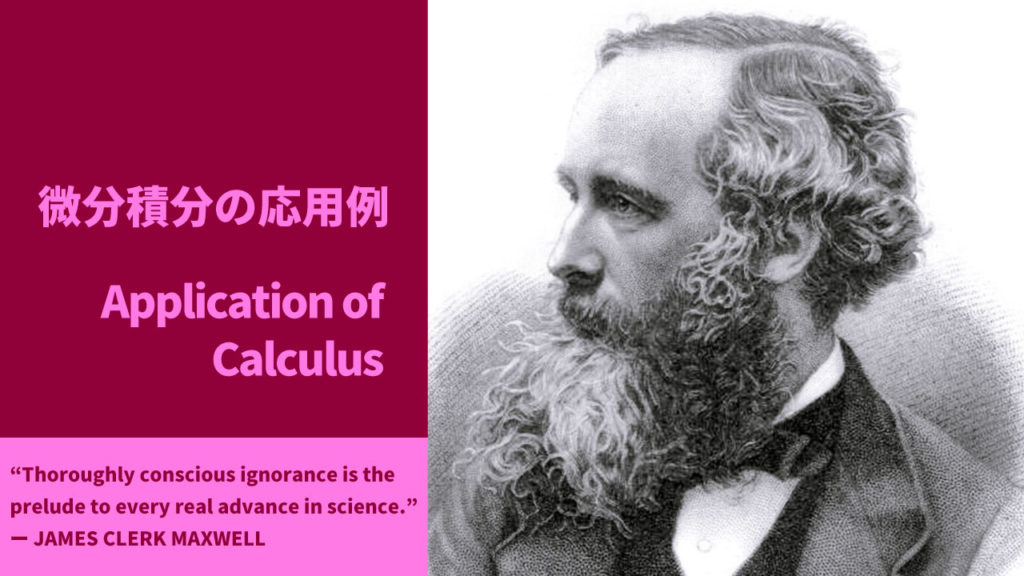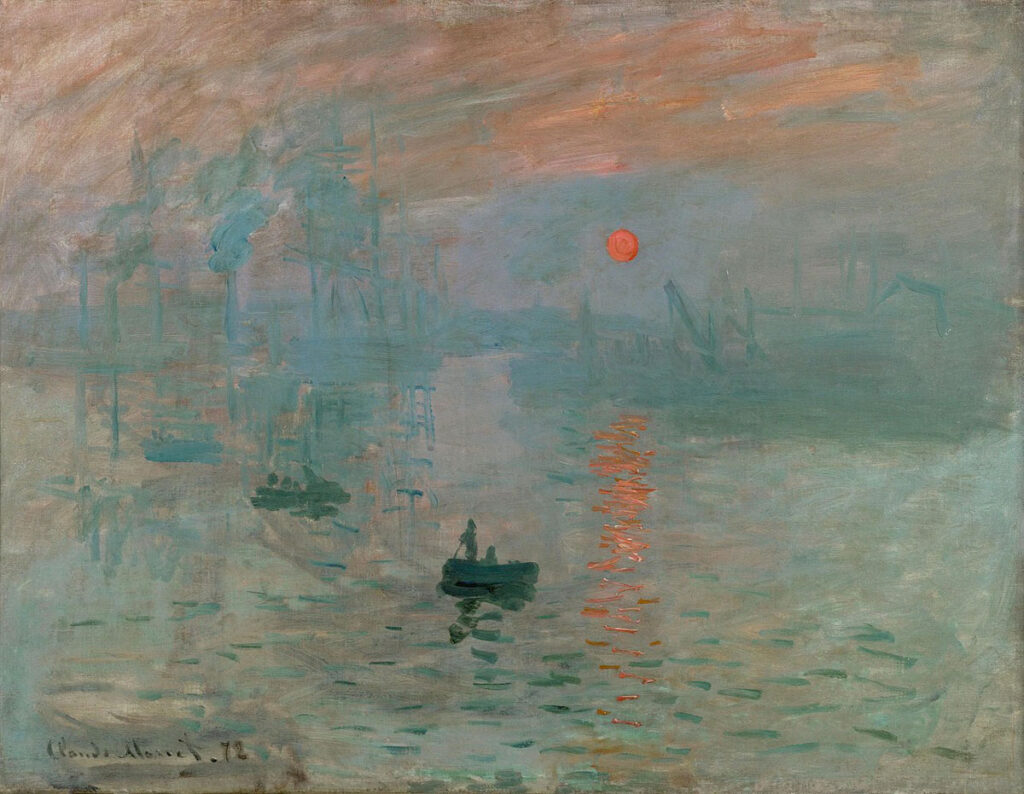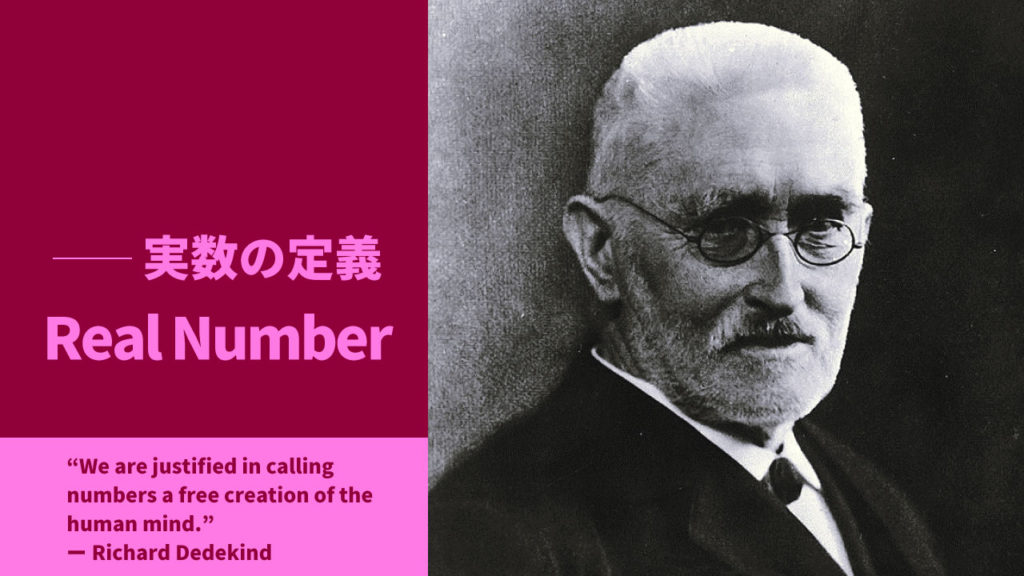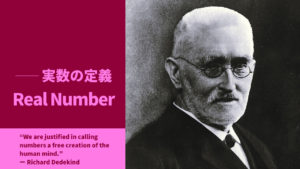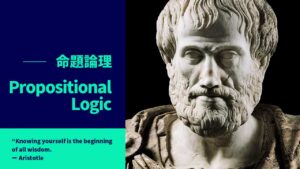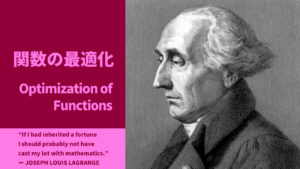算術演算と公理
算術演算とは何か?
小学校で掛け算や割り算を学ぶ際に、以下のことを守るべき「お約束」として教わりますが、その理屈までは習いません。\begin{eqnarray*}
&&\left( a\right) \ 0\text{では割ってはいけない} \\
&&\left( b\right) \ \text{マイナスの数を掛けると正負の符号が逆になる} \\
&&\left( c\right) \ \text{マイナスの数どうしを掛けるとプラスの数になる}
\end{eqnarray*}そこで今回はその理由を体(field)と呼ばれる概念を用いて解説します。ただし、本題に入る前の準備として、そもそも「掛け算」や「割り算」とは何であるか、少し一般的な視点から解説します。
掛け算や割り算は、足し算や引き算などとともに算術演算(arithmetic operation)と呼ばれます。これら 4 種類の算術演算を合わせて四則演算(four arithmetic operations)と呼びます。算術演算とは一般に、「2 つの数に対して 1 つの数を定める規則」のことです。このことを確認するために、以下に四則演算の例を挙げます。\begin{eqnarray*}
\text{足し算(加法):}1+2
&=&3 \\
\text{引き算(減法):}1-2
&=&-1 \\
\text{かけ算(乗法):}1\times 2 &=&2 \\
\text{割り算(除法):}1\div
2 &=&\frac{1}{2}
\end{eqnarray*}上の例において、\(1+2=3\)は\(1,2\)という 2 つの数に対して\(3\)という 1 つの数を定めています。また、\(1-2=-1\)は\(1,2\)という 2 つの数に対して\(-1\)という 1 つの数を定めています。残りの 2 つの例についても同様です。4 種類の算術演算それぞれが 2 つの数に対して定める数は異なりますが、2 つの数に対して 1 つの数を定めるという点では共通しています。
有理数における算術演算
「2 つの数に対して 1 つの数を定める規則」を算術演算と呼びますが、ここでの「数」はどのような種類の数でもよいというわけではありません。例えば、私たちがモノを数えるときに使う数\(1,2,3,\cdots \)を自然数(natural number)と呼びますが、試しに、自然数を用いて算術演算を以下のように定義してみましょう。
算術演算をこのように定義したとき、先ほど例として挙げた\(1+2=3\)という足し算は算術演算としての要件を満たしています。なぜならこれは、\(1,2\)という 2 つの自然数に対して\(3\)という自然数を定めているからです。
しかし、引き算に関する例\(1-2=-1\)は算術演算としての要件を満たしません。なぜなら、\(1,2\)は自然数ですが、それらに対して減法\(-\)が定める数\(-1\)は自然数ではないからです。マイナスの数は自然数ではありません。この例が示唆するように、自然数どうしの四則演算の結果は自然数であるとは限らないため、算術演算の定義を修正する必要があります。
そこで、算術演算の定義を以下のように修正します。
ただし、整数(integer)とは\(\cdots ,-3,-2,-1,0,1,2,3,\cdots \)などの数を指します。任意の自然数は整数でもありますが、整数の中には自然数以外の数(負の整数とゼロ)が存在します。いずれにせよ、上の定義を採用するならば、引き算に関する例\(1-2=-1\)もまた算術演算としての要件を満たします。なぜならこれは、\(1,2\)という 2 つの整数に対して\(-1\)という整数を定めているからです。
しかし、割り算に関する例\(1\div 2=\frac{1}{2}\)は算術演算としての要件を満たしていません。なぜなら、\(1,2\)は整数ですが、それらに対して除法\(\div \)が定める数\(\frac{1}{2}\)は整数ではないからです。分数の形で表される数は整数ではありません。この例が示唆するように、整数どうしの四則演算の結果は整数であるとは限らないため、再び算術演算の定義を修正する必要があります。
そこで、算術演算の定義を以下のように再修正します。
なお、有理数とは整数\(a,b\)を用いて\(\frac{a}{b}\)という分数の形で表される数です。ただし、\(b\)は\(0\)以外の整数である必要があります。ちなみに、任意の整数は有理数でもあります。なぜなら、任意の整数\(a\)は\(\frac{a}{1}\)という有理数として表すことができるからです。
さて、この新たな定義のもとでは、割り算に関する例\(1\div 2=\frac{1}{2}\)もまた算術演算としての要件を満たしています。なぜならこれは、\(1,2\)という 2 つの有理数に対して\(\frac{1}{2}\)という有理数を定めているからです。一般に、任意の有理数どうしの四則演算の結果は必ず有理数になります。したがって、足し算・引き算・掛け算・割り算という四則演算について考える際には、有理数という数の範囲で考えておけば支障はありません。
公理主義の考え方
繰り返しになりますが、「2 つの有理数に対して 1 つの有理数を定める規則」を算術演算と呼びます。足し算・引き算・掛け算・割り算はいずれも算術演算ですが、これらはどのようなルールを持つ算術演算でしょうか。ただし、「\(0\)では割ってはいけない」、「マイナスの数を掛けると正負の符号が逆になる」、「マイナスの数どうしを掛けるとプラスの数になる」などのお約束もまた掛け算や割り算に関するルールであることに違いはありません。しかし、これから行おうとしていることは、四則演算を特徴づける「最小のルール」を定めた上で、それらのルールだけを使って先の「お約束」の根拠を論理的に説明するということです。
数学では、より少ないルールからより多くのことを説明できることを良しとします。足し算・引き算・掛け算・割り算という算術演算には、それらを特徴づけるルールがそれぞれ存在します。しかし、そのようなルールは少なければ少ないほど良いというのが数学の考え方です。「\(0\)では割ってはいけない」、「マイナスの数を掛けると正負の符号が逆になる」、「マイナスの数どうしを掛けるとプラスの数になる」などを守るべき「お約束」とみなすことは、これらを算術演算のルールとして定めることを意味します。しかし、これらをあらかじめ算術演算のルールに含めるのではなく、よりシンプルで常識に適ったルールを出発点としてこれらを説明できるのであれば、それはより望ましいのです。四則演算を特徴づける最小限のシンプルなルールを算術演算の公理(axioms of arithmetic operation)と呼びます。
以降では算術演算の公理を 1 つずつ順番に解説した上で、最後にそれらの公理を用いて「\(0\)では割ってはいけない」ことをはじめとする諸々の「お約束」を証明します。
加法に関する公理
加法に関する交換律
加法\(+\)という算術演算に関する 1 つ目の公理は、任意の 2 つの有理数\(a,b\)に対して、「\(a\)足す\(b\)」と「\(b\)足す\(a\)」は同じ結果になるというものです。この公理を加法に関する交換律(commutative law)と呼びます。
a+b=b+a
\end{equation*}が成り立つ。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(1,2\)に対して、\begin{equation*}
1+2=2+1
\end{equation*}が成り立ちます。これは当たり前のことのようですが、当たり前であることが重要なのです。当たり前でシンプルなルールだけを前提として、多くの複雑なことを導くことが数学の醍醐味だからです。
加法に関する結合律
加法\(+\)に関する 2 つ目の公理は、3 つの有理数\(a,b,c\)を足すときに、隣り合うどの 2 つを先に足しても同じ結果になるというものです。この公理を加法に関する結合律(associative law)と呼びます。
\left( a+b\right) +c=a+\left( b+c\right)
\end{equation*}が成り立つ。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(1,2,3\)に対して、\begin{equation*}
(1+2)+3=1+(2+3)
\end{equation*}が成り立ちます。左辺の\(\left( 1+2\right) +3\)は、先に\(1+2\)を計算して、その計算結果に\(3\)を加えることを意味します。一方、右辺の\(1+\left( 2+3\right) \)は、先に\(2+3\)を計算して、その計算結果に\(1\)を加えることを意味します。これらの間に等号が成り立つということは、\(1,2,3\)という 3 つの数を足すときに、\(1\)と\(2\)を先に足しても、\(2\)と\(3\)を先に足しても結果は同じであるということです。これも当たり前のことのようですが、やはり当たり前であることが重要です。
加法単位元の存在
加法\(+\)に関する 3 つ目の公理は、どのような有理数\(a\)に足しても結果が\(a\)のままであるような有理数が存在するというものです。具体的には、それは有理数\(0\)に他なりません。言い換えると、どのような有理数に足しても結果が変わらないような有理数として\(0\)を定義するということです。このような文脈のもとでは、有理数\(0\)のことを加法単位元(additive identity element)と呼びます。
a+0=a
\end{equation*}という関係が成り立つ。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(1\)に対して、\begin{equation*}
1+0=1
\end{equation*}が成り立ちます。これも当たり前です。
加法逆元の存在
加法\(+\)に関する 4 つ目の公理は、それぞれの有理数\(a\)に対して、それに足すと結果が\(0\)になるような有理数が存在するというものです。具体的には、それは負の数\(-a\)に他なりません。言い換えると、それぞれの有理数\(a\)に対して、それに足すと結果が\(0\)になるような有理数として\(a\)の負数\(-a\)を定義するということです。このような文脈のもとでは、負数\(-a\)のことを\(a\)の加法逆元(additive inverse element)と呼びます。
a+\left( -a\right) =0
\end{equation*}を満たす有理数\(-a\)が存在する。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(1\)に対して、\begin{equation*}
1+\left( -1\right) =0
\end{equation*}を満たす負の有理数\(-1\)が存在します。これも当たり前です。
加法\(+\)に関する公理は以上ですべてです。有理数どうしの加法\(+\)は、以上の 4 つの公理にしたがうものとして定義されます。
減法の定義
加法\(+\)に関しては\(\left( A1\right)\)から\(\left( A4\right) \)までの 4 つの公理を定めましたが、減法\(-\)に関して同様のことを繰り返す必要はありません。減法は加法から間接的に定義されます。加法に関するルールを定めてしまえば、そのルールを使って減法を定めることができるというわけです。これは、より少ないルールからより多くのことを導くことを良しとする数学の考え方と合致しています。
では、減法\(-\)は加法\(+\)からどのように定めればよいのでしょうか。このことを順を追って説明します。まずは以下の命題について考えます。
この命題が真であることを、先に定めた\(\left( A1\right) \)から\(\left( A4\right) \)までの公理を用いて証明します。
\(a+b=a+c\)を満たす有理数\(a,b,c\)を任意に選びます。公理\(\left( A3\right) \)より、\(b\)に対しては、\begin{equation}
b=b+0 \quad\cdots (1)
\end{equation}が成り立ちます。また、公理\(\left( A4\right) \)より、\(a\)について\(0=a+\left( -a\right) \)となりますが、これを\(\left( 1\right) \)に代入すると、\begin{equation*}
b=b+\left( a+\left( -a\right) \right)
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A2\right) \)を用いてこれを変形すると、\begin{equation}
b=\left( b+a\right) +\left( -a\right) \quad\cdots (1)
\end{equation}を得ます。さて、\(a+b=a+c\)と公理\(\left( A1\right) \)より\(b+a=c+a\)が成り立ちますが、これを\(\left( 2\right) \)に代入すると、\begin{equation*}
b=(c+a)+(-a)
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A2\right) \)を再び用いてこれを変形すると、\begin{equation}
b=c+\left( a+\left( -a\right) \right) \quad\cdots (3)
\end{equation}を得ますが、公理\(\left( A4\right) \)より\(a+(-a)=0\)であるため、これを\(\left( 3\right) \)に代入して、\begin{equation*}
b=c+0
\end{equation*}を得ます。ただし、公理\(\left( A3\right) \)より\(c+0=c\)であるため、これを用いると上の式は、\begin{equation*}
b=c
\end{equation*}と言い換えられます。これで証明完了です。
続いて、上の補題から以下の命題を証明します。ただし、証明で使うことができるのは\(\left( A1\right) \)から\(\left( A4\right)\)までの公理と、それらを用いて証明した上の補題だけです。
有理数\(a,b\)を任意に選びます。まず、\(x=a+\left( -b\right) \)が方程式\(b+x=a\)の解であることを示します。そこで、\(b+x\)の\(x\)に\(x=a+\left( -b\right) \)を代入すると、\begin{equation*}
b+(a+(-b))
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A1\right) \)より\(a+\left( -b\right) =\left( -b\right) +a\)が成り立つため、これを用いて上の式を変形すると、\begin{equation*}
b+\left( \left( -b\right) +a\right)
\end{equation*}を得ます。さらに公理\(\left( A2\right) \)を用いてこれを変形すると、\begin{equation*}
(b+(-b))+a
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A4\right) \)より\(b+\left( -b\right) =0\)が成り立つため、これを上の式に代入すると、\begin{equation*}
0+a
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A1\right) ,\left( A3\right) \)を用いてこれをさらに変形すると、\begin{equation*}
a
\end{equation*}となります。つまり、\(b+x\)は\(a\)と一致するため、目標が達成されました。
続いて、方程式\(b+x=a\)の解が一意的であることを示します。そこで、2 つの異なる有理数\(y,y^{\prime }\)がともに\(b+x=a\)の解であるものと仮定して矛盾を導きます。仮定より、\begin{eqnarray*}
b+y &=&a \\
b+y^{\prime } &=&a
\end{eqnarray*}がともに成り立つため、\begin{equation*}
b+y=b+y^{\prime }
\end{equation*}を得ます。すると、先に示した補題より\(y=y^{\prime }\)となりますが、これは\(y\not=y^{\prime }\)であることと矛盾します。したがって\(b+x=a\)の解が一意的であることが示されました。
長々とこの命題を証明してきた理由は、この命題を用いて加法\(+\)から減法\(-\)を間接的に定義するからです。この命題を導くために利用したのは、\(\left( A1\right) \)から\(\left( A4\right) \)までの 4 つの公理と、それらの公理から示された先の補題だけです。したがって、上の命題は実質的には\(\left( A1\right) \)から\(\left( A4\right) \)までの公理から導かれたものです。\(\left( A1\right) \)から\(\left( A4\right) \)は加法\(+\)に関する公理です。加法に関する公理より導かれた補題から減法を定義するということは、加法から減法を定義するということです。
では、上の補題を用いて加法\(+\)から減法\(-\)を定義しましょう。具体的には、有理数\(a,b\)に対して、方程式\(b+x=a\)を満たすような有理数\(x=a+\left( -b\right) \)を定める演算を減法と定義します。ただし、\(a+\left( -b\right) \)をシンプルに\(a-b\)で表記し、これを\(a\)と\(b\)の差と呼びます。
例えば、2 つの有理数\(1,2\)の減法とは、\(2+x=1\)を満たすような有理数\(x=1+\left( -2\right) \)を求めることであり、それを簡略化して\(1-2\)で表すということです。
乗法に関する公理
乗法に関する交換律
乗法\(\times \)という算術演算に関する 1 つ目の公理は、任意の 2 つの有理数\(a,b\)に対して、「\(a\)掛ける\(b\)」と「\(b\)掛ける\(a\)」は同じ結果になるというものです。この公理を乗法に関する交換律(commutative law)と呼びます。
a\times b=b\times a
\end{equation*}が成り立つ。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(1,2\)に対して、\begin{equation*}
1\times 2=2\times 1
\end{equation*}が成り立ちます。
乗法に関する結合律
乗法\(\times \)に関する 2 つ目の公理は、3 つの有理数\(a,b,c\)を掛けるときに、隣り合うどの 2 つを先に掛けても同じ結果になるというものです。この公理を乗法に関する結合律(associative law)と呼びます。
\left( a\times b\right) \times c=a\times \left( b\times c\right)
\end{equation*}が成り立つ。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(1,2,3\)に対して、\begin{equation*}
(1\times 2)\times 3=1\times (2\times 3)
\end{equation*}が成り立ちます。左辺の\(\left( 1\times 2\right) \times 3\)は、先に\(1\times 2\)を計算して、その計算結果に\(3\)を掛けることを意味します。一方、右辺の\(1\times \left( 2\times 3\right) \)は、先に\(2\times 3\)を計算して、その計算結果に\(1\)を掛けることを意味します。これらの間に等号が成り立つということは、\(1,2,3\)という 3 つの数を掛けるときに、\(1\)と\(2\)を先に掛けても、\(2\)と\(3\)を先に掛けても結果は同じであるということです。
乗法単位元の存在
乗法\(\times \)に関する 3 つ目の公理は、どのような有理数\(a\)に掛けても結果が\(a\)のままであるような有理数が存在するというものです。具体的には、それは有理数\(1\)に他なりません。言い換えると、どのような有理数に掛けても結果が変わらないような有理数として\(1\)を定義するということです。このような文脈のもとでは、有理数\(1\)のことを乗法単位元(multiple identity element)と呼びます。
a\times 1=a
\end{equation*}という関係が成り立つ。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(2\)に対して、\begin{equation*}
2\times 1=2
\end{equation*}が成り立ちます。
乗法逆元の存在
乗法\(\times \)に関する 4 つ目の公理は、\(0\)とは異なるそれぞれ有理数\(a\)に対して、それに掛けると結果が\(1\)になるような有理数が存在するというものです。具体的には、それは逆数\(a^{-1}=\frac{1}{a}\)に他なりません。言い換えると、\(0\)とは異なるそれぞれの有理数\(a\)に対して、それに掛けると結果が\(1\)になるような有理数として\(a\)の逆数\(a^{-1}=\frac{1}{a}\)を定義するということです。このような文脈のもとでは、\(0\)とは異なる有理数\(a\)の逆数\(a^{-1}=\frac{1}{a}\)のことを\(a\)の乗法逆元(multiple inverse element)と呼びます。
a\times a^{-1}=1
\end{equation*}を満たす有理数\(a^{-1}=\frac{1}{a}\)が存在する。
この公理のもとでは、例えば、有理数\(2\)に対して、\begin{equation*}
2\times 2^{-1}=1
\end{equation*}を満たす逆数\(2^{-1}=\frac{1}{2}\)が存在します。
乗法\(\times \)に関する公理は以上ですべてです。有理数どうしの乗法\(\cdot \)は、以上の 4 つの公理にしたがうものとして定義されます。
除法の定義
加法\(+\)から減法\(-\)を間接的に定義したのと同様に、乗法\(\times \)から除法\(\div \)を間接的に定義します。乗法に関する\(\left( A5\right) \)から\(\left( A8\right) \)までの公理をルールとして定めてしまえば、そのルールから除法を間接的に定義できるというわけです。これは、加法に関する\(\left( A1\right) \)から\(\left( A4\right)\)までの公理から減法を間接的に定義したのと同様のアプローチです。
では、除法\(\div \)は乗法\(\times \)からどのように定めればよいでしょうか。まずは以下の命題について考えます。
この命題が真であることを、先に定めた公理\(\left( A5\right) \)から\(\left( A8\right) \)を用いて証明します。
\(a\times b=a\times c\)を満たす有理数\(a,b,c\)を任意に選びます。ただし\(a\not=0\)です。公理\(\left( A7\right) \)より、\(b\)に対しては、\begin{equation}
b=b\times 1 \quad\cdots (1)
\end{equation}が成り立ちます。また、公理\(\left( A5\right) \)より、\(a\)について\(1=a\times a^{-1}\)となりますが、これを\(\left( 1\right) \)に代入すると、\begin{equation*}
b=b\times \left( a\times a^{-1}\right)
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A6\right) \)を用いてこれを変形すると、\begin{equation}
b=\left( b\times a\right) \times a^{-1} \quad\cdots (1)
\end{equation}を得ます。さて、\(a\times b=a\times c\)と公理\(\left( A5\right) \)より\(b\times a=c\times a\)が成り立ちますが、これを\(\left( 2\right) \)に代入すると、\begin{equation*}
b=(c\times a)\times a^{-1}
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A6\right) \)を再び用いてこれを変形すると、\begin{equation}
b=c\times \left( a\times a^{-1}\right) \quad\cdots (3)
\end{equation}を得ますが、公理\(\left( A8\right) \)より\(a\times a^{-1}=1\)であるため、これを\(\left( 3\right) \)に代入して、\begin{equation*}
b=c\times 1
\end{equation*}を得ます。ただし、公理\(\left( A7\right) \)より\(c\times 1=c\)であるため、これを用いると上の式は、\begin{equation*}
b=c
\end{equation*}と言い換えられます。これで証明完了です。
続いて、上の補題から以下の命題を証明します。ただし、証明で使うことができるのは\(\left( A5\right) \)から\(\left( A8\right)\)までの公理と、それらを用いて真であることが示された上の補題のみです。
有理数\(a,b\)を任意に選びます。ただし\(b\not=0\)です。まず、\(x=a\times b^{-1}\)が方程式\(b\times x=a\)の解であることを示します。そこで、\(b\times x\)の\(x\)に\(x=a\times b^{-1}\)を代入すると、\begin{equation*}
b\times (a\times b^{-1})
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A5\right) \)より\(a\times b^{-1}=b^{-1}\times a\)が成り立つため、これを用いて上の式を変形すると、\begin{equation*}
b\times \left( b^{-1}\times a\right)
\end{equation*}を得ます。さらに公理\(\left( A6\right) \)を用いてこれを変形すると、\begin{equation*}
(b\times b^{-1})\times a
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A8\right) \)より\(b\times b^{-1}=1\)が成り立つため、これを上の式に代入すると、\begin{equation*}
1\times a
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A5\right) ,\left( A7\right) \)を用いてこれをさらに変形すると、\begin{equation*}
a
\end{equation*}となります。つまり、\(b\times x\)は\(a\)と一致するため、目標が達成されました。
続いて、方程式\(b\times x=a\)の解が一意的であることを示します。そこで、2 つの異なる有理数\(y,y^{\prime }\)がともに\(b\times x=a\)の解であるものと仮定して矛盾を導きます。仮定より、\begin{eqnarray*}
b\times y &=&a \\
b\times y^{\prime } &=&a
\end{eqnarray*}がともに成り立つため、\begin{equation*}
b\times y=b\times y^{\prime }
\end{equation*}を得ます。すると、先に示した補題より\(y=y^{\prime }\)となりますが、これは\(y\not=y^{\prime }\)であることと矛盾します。したがって\(b\times x=a\)の解が一意的であることが示されました。
長々とこの命題を証明してきた理由は、この命題を用いて乗法\(\times \)から減法\(\div \)を間接的に定義するからです。この命題を導くために利用したのは\(\left( A5\right) \)から\(\left( A8\right) \)までの 4 つの公理と、それらの公理から示された先の補題だけです。したがって、上の命題は実質的には\(\left( A5\right) \)から\(\left( A8\right) \)までの公理だけから導かれたものです。\(\left( A5\right) \)から\(\left( A8\right) \)は乗法\(\times \)に関する公理です。乗法に関する公理より導かれた補題から除法を定義するということは、乗法から除法が定義されるということです。
では、上の補題を用いて乗法\(\times \)から減法\(\div \)を定義しましょう。具体的には、有理数\(a,b\)(ただし\(b\not=0\))に対して、方程式\(b\times x=a\)を満たすような有理数\(x=a\times b^{-1}\)を定める演算を減法と呼びます。ただし、\(a\times b^{-1}\)を\(a\div b\)で表記し、これを\(a\)と\(b\)の商と呼びます。
例えば、2 つの有理数\(1,2\)の除法とは、\(2\times x=1\)を満たすような有理数\(x=1\times 2^{-1}=1\times \frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)を求めることであり、それを\(1\div 2\)で表すということです。
加法と乗法の関係を規定する公理
分配律
加法\(+\)と乗法\(\times \)を特徴づける公理を定めた上で、そこから減法\(-\)と除法\(\div \)を間接的に定義しました。最後に、加法と乗法の関係を特徴づける公理を定めます。1 つ目は、任意の 3 つの有理数\(a,b,c\)に対して、\begin{equation}
a\times \left( b+c\right) =\left( a\times b\right) +\left( a\times c\right) \quad\cdots (1)
\end{equation}という関係が成り立つというものです。これを分配律(distributive law)と呼びます。
例えば、3 つの有理数\(1,2,3\)が与えられたとき、\(\left( 1\right) \)の左辺は、\begin{equation*}
1\times \left( 2+3\right) =1\times 5=5
\end{equation*}となり、\(\left( 1\right) \)の右辺は、\begin{equation*}
\left( 1\times 2\right) +\left( 1\times 3\right) =2+3=5
\end{equation*}となるため、確かに\(\left( 1\right) \)の等号は成立します。
a\times \left( b+c\right) =a\times b+a\times c
\end{equation*}という関係が成立する。
加法単位元と乗法単位元の関係
加法と乗法の関係を特徴づける 2 つ目の公理は、加法単位元\(0\)と乗法単位元\(1\)が異なるというものです。
加法と乗法の関係を規定する公理は以上で全てです。
また、以上で算術演算を特徴づける公理がすべて揃いました。すべての公理をまとめておきます。
\(\left( A1\right) \ \)任意の有理数\(a,b\)に対して、\(a+b=b+a\)が成り立つ。
\(\left( A2\right) \ \)任意の有理数\(a,b,c\)に対して、\(\left( a+b\right) +c=a+\left( b+c\right) \)が成り立つ。
\(\left( A3\right) \ \)有理数\(0\)が存在して、これと任意の有理数\(a\)の間には、\(a+0=a\)という関係が成り立つ。
\(\left( A4\right) \ \)それぞれの有理数\(a\)に対して、\(a+\left( -a\right) =0\)を満たす有理数\(-a\)が存在する。
\(\left( A5\right) \ \)任意の有理数\(a,b\)に対して、\(a\times b=b\times a\)が成り立つ。
\(\left( A6\right) \ \)任意の有理数\(a,b,c\)に対して、\(\left( a\times b\right) \times c=a\times \left( b\times c\right) \)が成り立つ。
\(\left( A7\right) \ \)有理数\(0\)が存在して、これと任意の有理数\(a\)の間には、\(a\times 1=a\)という関係が成り立つ。
\(\left( A8\right) \ 0\)とは異なるそれぞれの有理数\(a\)に対して、\(a\times a^{-1}=1\)を満たす有理数\(a^{-1}=\frac{1}{a}\)が存在する。
\(\left( A9\right) \ \)任意の有理数\(a,b,c\)に対して、\(a\times \left( b+c\right) =a\times b+a\times c\)という関係が成立する。
\(\left( A10\right) \ 0\not=1\)が成り立つ。
ある集合において加法\(+\)と乗法\(\times \)という 2 つの演算を定義したときに、この 2 つの演算が上のルールをすべて満たす場合には、その集合を体(field)と呼びます。したがって、すべての有理数からなる集合を体として定義するということです。
「0を掛けると0になる」ことの証明
準備ができました。以降では「\(0\)では割ってはいけない」ことを証明しますが、その前に「\(0\)を掛けると\(0\)になる」ことを証明します。なぜならば、「\(0\)では割ってはいけない」ことを証明する際には「\(0\)を掛けると\(0\)になる」という事実を利用するからです。ただし、「\(0\)を掛けると\(0\)になる」こととは、任意の有理数\(a\)に対して\(a\times 0=0\)が成り立つこととして定式化されます。
a\times 0=0
\end{equation*}が成り立つ。
まず、\begin{equation*}
a\times 0=a\times 0
\end{equation*}が明らかに成り立ちます。公理\(\left( A3\right) \)より\(0+0=0\)が成り立つため、これを上の式の右辺に代入すると、\begin{equation*}
a\times 0=a\times \left( 0+0\right)
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A9\right) \)を利用して上の式の右辺を変形すると、\begin{equation*}
a\times 0=\left( a\times 0\right) +\left( a\times 0\right)
\end{equation*}を得ます。両辺に有理数\(-\left( a\times 0\right) \)を足すと、\begin{equation*}
\left( a\times 0\right) +\left( -\left( a\times 0\right) \right) =\left( a\times 0\right) +\left( a\times 0\right) +\left( -\left( a\times 0\right) \right)
\end{equation*}を得ますが、公理\(\left( A4\right) \)を利用して両辺をそれぞれ変形すると、\begin{equation*}
0=a\times 0+0
\end{equation*}となります。さらに公理\(\left( A3\right) \)を利用して上の式の右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=a\times 0
\end{equation*}を得るため証明が完了しました。
「0では割ってはいけない」ことの証明
続いて、「\(0\)では割ってはいけない」ことを証明します。
有理数を\(0\)で割ることができるものと仮定して矛盾を導きます。除法\(\div \)の定義より、有理数\(a,b\)(ただし\(b\not=0\))に関する商\(a\div b\)とは、方程式\(b\times x=a\)の一意的な解\(x=a\times b^{-1}\)に相当します。有理数を\(0\)で割ってもよい場合には、これが\(b=0\)の場合にも成立します。つまり、任意の有理数\(a\)に対して、一意的な有理数\begin{equation*}
a\times 0^{-1}
\end{equation*}が存在するということです。\(a\)は任意の有理数であるため、上の式において\(a=0\)としても構いません。つまり、一意的な有理数\begin{equation}
0\times 0^{-1} \quad\cdots (1)
\end{equation}が存在するということです。先に示した「有理数に\(0\)を掛けると\(0\)になる」を利用すると、\(\left( 1\right) \)は\(0\)と一致します。一方、公理\(\left( A8\right) \)を利用すると、\(\left( 1\right) \)は\(1\)と一致します。つまり、\(\left( 1\right) \)は\(0\)であると同時に\(1\)です。\(\left( 1\right) \)が一意的な有理数であることを考えると、\(\left( 1\right) \)が異なる 2 つの値を同時にとることはありません。しかし、公理\(\left( A10\right) \)より\(0\not=1\)であるため、これでは\(\left( 1\right) \)が異なる 2 つの値を同時にとることとなり矛盾です。したがって、当初の仮定である「有理数を\(0\)で割ることができる」という仮定が誤りであることを意味します。したがって、有理数を\(0\)で割ることはできません。
マイナスの数を掛けると符号が逆になることの証明
続いて、「マイナスの数を掛けると正負の符号が逆になる」ことを証明します。
\left( -a\right) \times b=-\left( a\times b\right)
\end{equation*}が成り立つ。
まず、\begin{equation*}
0=0
\end{equation*}が明らかに成り立ちます。先に示したように、任意の有理数\(b\)に\(0\)を掛けると\(0\)になるため、\(0\times b=0\)が成り立ちます。これを用いて上の式の右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=0\times b
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A4\right) \)より、任意の有理数\(a\)に対して\(0=a+\left( -a\right) \)を満たす有理数\(-a\)が存在するため、これを用いて上の式の右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=\left( a+\left( -a\right) \right) \times b
\end{equation*}を得ます。さらに公理\(\left( A9\right) \)を用いて右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=\left( a\times b\right) +\left( \left( -a\right) \times b\right)
\end{equation*}を得ます。両辺に\(-\left( a\times b\right) \)を加えると、\begin{equation*}
0+\left( -\left( a\times b\right) \right) =\left( a\times b\right) +\left( \left( -a\right) \times b\right) +\left( -\left( a\times b\right) \right)
\end{equation*}を得ます。左辺に関しては公理\(\left( A3\right) \)を、右辺に関しては公理\(\left( A4\right) \)と\(\left( A5\right) \)をそれぞれ用いて変形すると、\begin{equation*}
-\left( a\times b\right) =\left( -a\right) \times b
\end{equation*}を得るため証明が完了しました。
マイナスどうしをかけるとプラスになることの証明
最後に、「マイナスどうしをかけるとプラスになる」ことを証明します。
\left( -a\right) \times \left( -b\right) =a\times b
\end{equation*}が成り立つ。
まず、\begin{equation}
0=0 \quad\cdots (1)
\end{equation}が明らかに成り立ちます。先に示したように任意の有理数\(b\)に\(0\)を掛けると\(0\)になります。つまり、\(0\times b=0\)が成り立ちますが、\(b\)は任意の有理数であるため、\(b\)を\(-b\)に置き換えた\(0\times \left( -b\right) =0\)もまた成り立ちます。これを用いて\(\left( 1\right) \)の右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=0\times \left( -b\right)
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A4\right) \)より、任意の有理数\(a\)について\(0=a+\left( -a\right) \)が成り立つため、これを用いて上の式の右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=\left( a+\left( -a\right) \right) \times \left( -b\right)
\end{equation*}を得ます。公理\(\left( A6\right) \)を用いて右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=\left( -b\right) \times \left( a+\left( -a\right) \right)
\end{equation*}が成り立ち、さらに公理\(\left( A9\right) \)を用いて右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=\left( \left( -b\right) \times a\right) +\left( \left( -b\right) \times \left( -a\right) \right)
\end{equation*}を得ます。先に示した「マイナスの数を掛けると符号が逆になる」より\(\left( -b\right) \times a=-\left( b\times a\right) \)となるため、これを用いて上の式の右辺を変形すると、\begin{equation*}
0=-\left( b\times a\right) +\left( \left( -b\right) \times \left( -a\right) \right)
\end{equation*}を得ます。両辺に\(b\times a\)を加えると、\begin{equation*}
0+\left( b\times a\right) =-\left( b\times a\right) +\left( \left( -b\right) \times \left( -a\right) \right) +\left( b\times a\right)
\end{equation*}となります。左辺については公理\(\left( A1\right) \)と\(\left( A3\right) \)を、右辺については公理\(\left( A1\right) \)と\(\left( A3\right)\)、さらに\(\left( A4\right) \)を用いて変形すると、\begin{equation*}
b\times a=\left( -b\right) \times \left( -a\right)
\end{equation*}を得ます。最後に公理\(\left( A5\right) \)を用いて両辺を変形すると、\begin{equation*}
a\times b=\left( -a\right) \times \left( -b\right)
\end{equation*}となり、証明が完了しました。