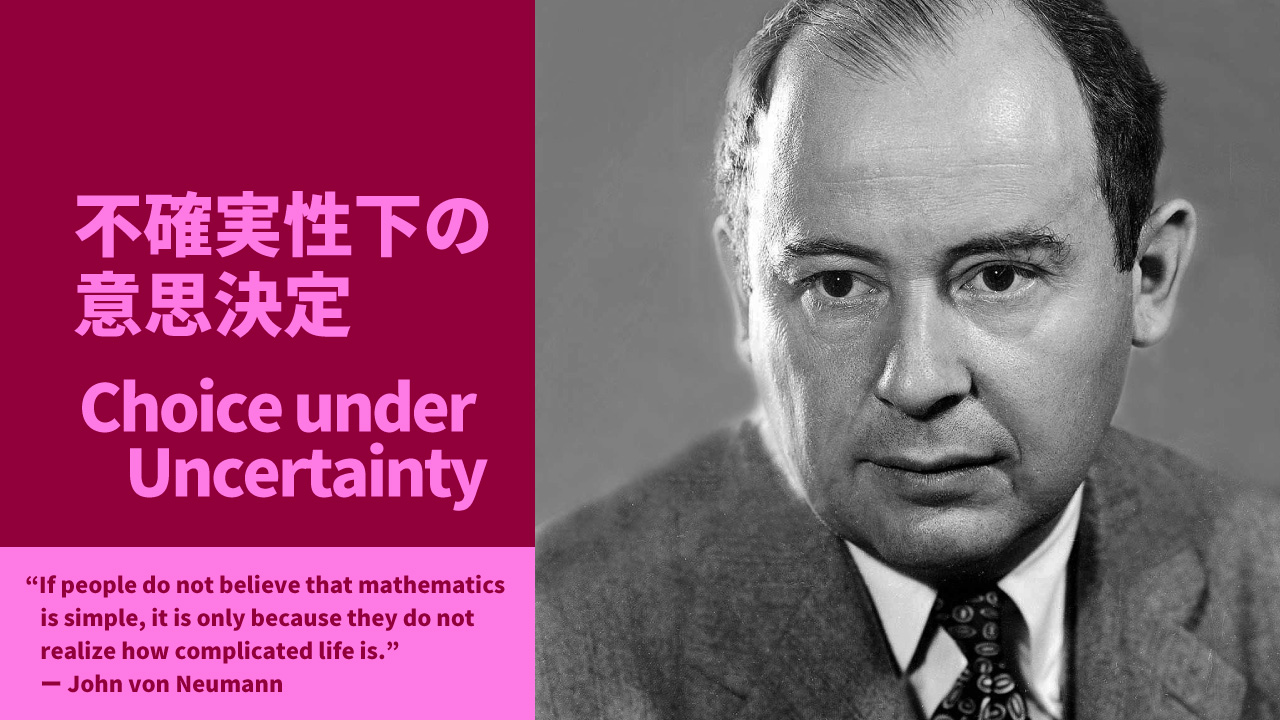目次
不確実性の定式化
リスクが存在する状況における選択肢をクジと呼ばれる概念として定式化します。
複合クジと結果主義の仮定
リスクが存在する状況における選択肢をクジと呼ばれる概念として表現しましたが、何らかの確率分布にもとづいてクジをランダムに選ぶことも考えられるため、そのような意思決定を複合クジと呼ばれる概念として表現します。
期待値最大化原理の妥当性(サンクトペテルブルクのパラドクス)
行動を選択した場合に起こり得る結果が数値として表現できる場合には、クジを選択すれば結果の期待値を計算できます。ただ、人は期待値を最大化するような選択を行うとは限りません。
不確実性の評価
意思決定主体が持つ不確実性に対する好みの体系を選好関係や効用関数、期待利得関数などとして定式化します。
不確実性を評価する選好関係
リスクが存在する状況における意思決定は、その人が持つ不確実性に対する好みの体系によって左右されます。そこで、そのような好みをクジどうしを比較する選好関係として定式化します。
不確実性を評価する効用関数
リスクが存在する状況において、意思決定主体がクジどうしを比較する選好を表現する効用関数が存在する場合には、クジの間の相対的な望ましさを、実数の大小関係として表現することができます。
期待効用関数の定義とその性質
リスクが存在する状況において、意思決定主体がクジどうしを比較する選好を表現する効用関数が線型性と呼ばれる性質を満たす場合、そのような効用関数を期待効用関数と呼びます。通常の効用関数とは異なり、期待効用関数は一定の基数性を満たします。
期待効用定理
意思決定主体の選好関係を表す効用関数や期待効用関数が存在するための条件を明らかにします。
不確実性を評価する選好関係の完備性
2つのクジを任意に選んだとき、意思決定主体が一方を他方以上に好むか、もしくは両者を同じ程度望ましいものと考えている場合には、主体の選好関係は完備性を満たすと言います。
不確実性を評価する選好関係の推移性
不確実性に直面する意思決定主体がクジどうしを比較する選好が循環しないことを保証するために、選好関係に対して推移性と呼ばれる性質を要求します。選好関係を表す効用関数が存在する場合、その選好は推移性を満たします。
不確実性を評価する選好関係の連続性
不確実性に直面する意思決定主体がクジどうしを比較する選好が連続的に変化することを保証するために、選好関係に対して連続性と呼ばれる性質を要求します。選好関係を表す連続な効用関数や期待効用関数が存在する場合、その選好は連続性を満たします。
リスク選好
意思決定主体の選好関係を表す効用関数や期待効用関数が存在するための条件を明らかにします。
クジの確実同値額(確実性等価)
主体にとってクジLを選択することと結果xを確実に得ることが無差別である場合、xをLの確実性等価と呼びます。クジの確実性等価とクジのもとでの結果の期待値を比較することにより、主体のリスク選好を特定できます。
BDMメカニズム(クジの確実同値額の測定実験)
主体にとってのクジの確実性等価を測定するためにはBDMメカニズム(Becker-DeGroot-Marschakメカニズム)と呼ばれる実験手法が有効です。BDMメカニズムは耐戦略性を満たすため、主体にとってクジの確実性等価を正直に表明することが支配戦略になります。
クジのリスクプレミアム(保険プレミアム)
クジのもとでの結果の期待値と確実同値額の差を、そのクジのリスクプレミアムと呼びます。クジのリスクプレミアムの符号を観察することにより、主体のリスク選好を特定できます。
クジの確率プレミアム
ある結果を確実に得ることと、その結果より望ましい結果と望ましくない結果が等確率で起こるクジを無差別にするための確率の調整幅を確率プレミアムと呼びます。確率プレミアムの符号を観察することにより、主体のリスク選好を特定できます。
アロー・プラットの絶対的リスク回避度
アロー・プラットの絶対的リスク回避度の符号を通じて主体のリスク選好(リスク回避的・中立的・愛好的)を判定できます。また、絶対的リスク回避度の値を通じてリスク回避の度合いを比較できます。
分析例
準備中
関連知識
必須知識
消費者理論
世の中に存在する資源は有限であり、加えて消費者は所得をはじめとする様々な制約に直面しているため、好きなものを好きなだけ消費できるわけではありません。だからこそ消費者が何をどのように選ぶのかという問題について考える意味があります。消費者理論は、様々な制約に直面する消費者がどのような意思決定を行うかを明らかにしようとします。
発展知識
本節で得た知識は以下の分野を学ぶ上での土台になります。