リーマン積分に関する微分積分学の第2基本定理
\(a<b\)を満たす実数\(a,b\in \mathbb{R} \)を端点とする有界な閉区間上に定義された関数\begin{equation*}f:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分可能でることは判明している一方で、その定積分は明らかではない状況を想定します。つまり、定積分\begin{equation*}\int_{a}^{b}f\left( x\right) dx
\end{equation*}が有限な実数として定まることは判明しているものの、その具体的な値は不明であるということです。
関数\(f\)と定義域を共有する関数\begin{equation*}F:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}の中に、以下の2つの条件を満たすものが存在する状況を想定します。
1つ目の条件は、この関数\(F\)が区間\(\left[ a,b\right] \)上で連続であるということです。つまり、関数\(F\)は定義域の内部\(\left( a,b\right) \)上の任意の点において連続であるとともに、定義域の左側の端点\(a\)において右側連続であり、定義域の右側の端点\(b\)において左側連続です。
2つ目の条件は、関数\(F\)は区間\(\left[ a,b\right] \)の内部\(\left(a,b\right) \)上で微分可能であるとともに、その導関数\(\frac{dF}{dx}:\mathbb{R} \supset \left( a,b\right) \rightarrow \mathbb{R} \)が\(\left( a,b\right) \)上において関数\(f\)と一致すること、すなわち、\begin{equation*}\forall x\in \left( a,b\right) :\frac{dF\left( x\right) }{dx}=f\left(
x\right)
\end{equation*}が成り立つということです。このとき、\(\left( a,b\right) \)上において関数\(F\)は関数\(f\)の原始関数であると言います。
以上の条件が満たされる場合、関数\(f\)の\(\left[a,b\right] \)上の定積分が、\begin{equation*}\int_{a}^{b}f\left( x\right) dx=F\left( b\right) -F\left( a\right)
\end{equation*}として定まることが保証されます。つまり、関数\(f\)が区間\(\left[ a,b\right]\)上でリーマン積分可能である場合、リーマン積分の定義にもとづいて関数\(f\)の定積分を導出する作業は煩雑になりがちですが、\(\left[ a,b\right] \)上で連続な原始関数\(F\)が存在する場合には、関数\(f\)の定積分を以下の関係\begin{equation*}\int_{a}^{b}f\left( x\right) dx=F\left( b\right) -F\left( a\right)
\end{equation*}から容易に導出できます。関数\(F\)の定義より、上の関係を、\begin{equation*}\int_{a}^{b}\frac{dF\left( x\right) }{dx}dx=F\left( b\right) -F\left(
a\right)
\end{equation*}と表現することもできます。つまり、\(\left[ a,b\right] \)上で連続かつ\(\left( a,b\right) \)上で微分可能な関数\(F\)の導関数を\(\left[ a,b\right] \)上で積分すると、関数\(F\)の値の変化量が得られます。いずれにせよ、これを微分積分学の第2基本定理(second fundamental theorem of calculus)や求積分定理(evaluatioin theorem)などと呼びます。
ルベーグ積分に関して微分積分学の第2基本定理は成り立つとは限らない
以下の例から明らかであるように、ルベーグ積分に関しては微分積分学の第2基本定理は成り立つとは限りません。
x\right) }{dx}=0
\end{equation*}であり、したがって、\begin{equation*}
\int_{\left[ 0,1\right] \backslash \mathcal{C}}\frac{dF}{dx}=0
\end{equation*}を得ます。カントール集合\(\mathcal{C}\)は零集合であるため、カントール関数\(F\)は\(\left[ 0,1\right] \)上のほとんどいたるところで微分可能であることが明らかになりました。そこで、カントール関数の導関数の定義域を\(\left[ 0,1\right] \)へ拡張して、\begin{equation*}\frac{dF}{dx}:\mathbb{R} \supset \left[ 0,1\right] \rightarrow \left[ 0,1\right] \end{equation*}とした場合にも、カントール集合\(\mathcal{C}\)は零集合であることから、\begin{equation*}\int_{\left[ 0,1\right] }\frac{dF}{dx}=0
\end{equation*}が成り立ちます。その一方、カントール関数の定義より、\begin{eqnarray*}
F\left( 1\right) -F\left( 0\right) &=&1-0 \\
&=&1
\end{eqnarray*}であるため、\begin{equation*}
\int_{\left[ 0,1\right] }\frac{dF}{dx}<F\left( 1\right) -F\left( 0\right)
\end{equation*}を得ます。以上より、ルベーグ積分に関しては微分積分学の第2基本定理の主張は成り立つとは限らないことが明らかになりました。
カントール関数は連続かつ有界変動ですが、絶対連続関数ではありません。ルベーグ積分に関して微分積分学の第2基本定理の主張が成り立つことを保証するためには、関数が絶対連続である必要があります。以下で順番に解説します。
絶対連続関数が定数関数であるための十分条件
実数空間\(\mathbb{R} \)とルベーグ可測集合族\(\mathfrak{M}_{\mu }\)およびルベーグ測度\(\mu \)からなるルベーグ測度空間\(\left( \mathbb{R} ,\mathfrak{M}_{\mu },\mu \right) \)が与えられているものとします。
\(a<b\)を満たす実数\(a,b\in \mathbb{R} \)を端点とする有界閉区間上に定義された関数\begin{equation*}F:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が\(\left[ a,b\right] \)上において絶対連続であるものとします。つまり、以下の条件\begin{equation*}\forall \varepsilon >0,\ \exists \delta >0,\ \forall \left( a\right) ,\left(
b\right) ,\left( c\right) \text{を満たす}\left\{ \left[ a_{i},b_{i}\right] \right\} _{i=1}^{n}:\left[ \sum_{i=1}^{n}\left\vert b_{i}-a_{i}\right\vert <\delta \Rightarrow \sum_{i=1}^{n}\left\vert
F\left( b_{i}\right) -F\left( a_{i}\right) \right\vert <\varepsilon \right]
\end{equation*}が成り立つということです。ただし、\begin{eqnarray*}
&&\left( a\right) \ n\in \mathbb{N} \\
&&\left( b\right) \ \forall i\in \left\{ 1,\cdots ,n\right\} :a\leq
a_{i}<b_{i}\leq b \\
&&\left( c\right) \ \forall i,j\in \left\{ 1,\cdots ,n\right\} :\left(
i\not=j\Rightarrow \left[ a_{i},b_{i}\right] \cap \left[ a_{j},b_{j}\right]
=\phi \right)
\end{eqnarray*}です。つまり、どれほど小さい\(\varepsilon >0\)を任意に選んだ場合でも、それに対して何らかの\(\delta >0\)を選ぶことにより、以下の4つの条件\begin{eqnarray*}&&\left( a\right) \ n\in \mathbb{N} \\
&&\left( b\right) \ \forall i\in \left\{ 1,\cdots ,n\right\} :a\leq
a_{i}<b_{i}\leq b \\
&&\left( c\right) \ \forall i,j\in \left\{ 1,\cdots ,n\right\} :\left(
i\not=j\Rightarrow \left[ a_{i},b_{i}\right] \cap \left[ a_{j},b_{j}\right]
=\phi \right) \\
&&\left( d\right) \ \sum_{i=1}^{n}\left\vert b_{i}-a_{i}\right\vert <\delta
\end{eqnarray*}を満たす任意の閉区間族\(\left\{ \left[ a_{i},b_{i}\right] \right\} _{i=1}^{n}\)について、\begin{equation*}\sum_{i=1}^{n}\left\vert F\left( b_{i}\right) -F\left( a_{i}\right)
\right\vert <\varepsilon
\end{equation*}が成り立ちます。
絶対連続関数はほとんどいたるところで微分可能であるため、\(F\)は\(\left( a,b\right) \)上のほとんどいたるところで微分可能です。したがって、導関数\begin{equation*}\frac{dF}{dx}:\left( a,b\right) \backslash A\rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}の存在を保証する零集合\(A\subset \left( a,b\right) \)が存在します。この導関数\(\frac{dF}{dx}\)の定義域を\(\left[ a,b\right] \)に拡張することにより得られる関数\begin{equation*}\frac{dF}{dx}:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}を任意に選んだとき、この関数\(\frac{dF}{dx}\)が\(\left[ a,b\right] \)上のほとんどいたるところでゼロを値としてとる場合には、つまり、\begin{equation*}\forall x\in \left[ a,b\right] \backslash A:\frac{dF\left( x\right) }{dx}=0
\end{equation*}を満たす零集合\(A\subset \left[ a,b\right] \)が存在する場合には、もとの関数\(F\)は\(\left[a,b\right] \)上において定数関数になることが保証されます。
\end{equation*}を満たす零集合\(A\subset \left[ a,b\right] \)が存在する場合には、関数\(F\)は\(\left[ a,b\right] \)上において定数関数になる。
ルベーグ積分に関する微分積分学の第2基本定理
\(a<b\)を満たす実数\(a,b\in \mathbb{R} \)を端点とする有界閉区間上に定義された関数\begin{equation*}F:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が\(\left[ a,b\right] \)上において絶対連続であるものとします。
絶対連続関数はほとんどいたるところで微分可能であるため、関数\(F\)は\(\left( a,b\right) \)上のほとんどいたるところで微分可能です。したがって、導関数\begin{equation*}\frac{dF}{dx}:\left( a,b\right) \backslash A\rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}の存在を保証する零集合\(A\subset \left( a,b\right) \)が存在します。この導関数\(\frac{dF}{dx}\)の定義域を\(\left[ a,b\right] \)に拡張することにより得られる関数\begin{equation*}\frac{dF}{dx}:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}を任意に選んだとき、この関数は\(\left[ a,b\right] \)上においてルベーグ積分可能であるとともに、以下の関係\begin{equation*}\int_{\left[ a,b\right] }\frac{dF}{dx}=F\left( b\right) -F\left( a\right)
\end{equation*}が成り立つことが保証されます。
\end{equation*}が成り立つ。
関数\(f\)が区間\(\left[ a,b\right] \)上において絶対連続である場合には、\begin{equation*}\int_{\left[ a,b\right] }\frac{dF}{dx}=F\left( b\right) -F\left( a\right)
\end{equation*}が成り立つことが明らかになりました。つまり、\(\left[ a,b\right] \)上において絶対連続な関数\(F\)の導関数を\(\left[ a,b\right] \)上でルベーグ積分すると、関数\(F\)の値の変化量が得られます。以上より、絶対連続関数を対象とした場合には、ルベーグ積分についても微分積分学の第2基本定理が成立することが明らかになりました。

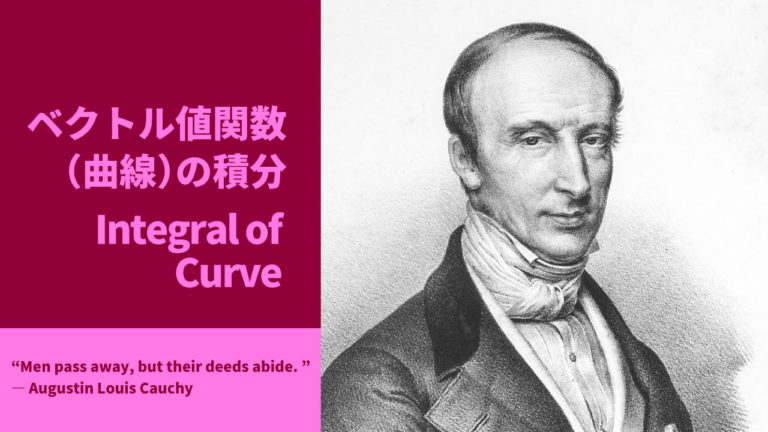
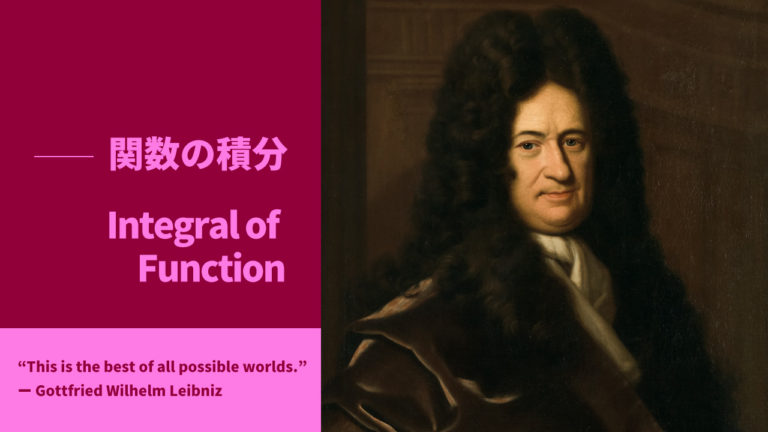
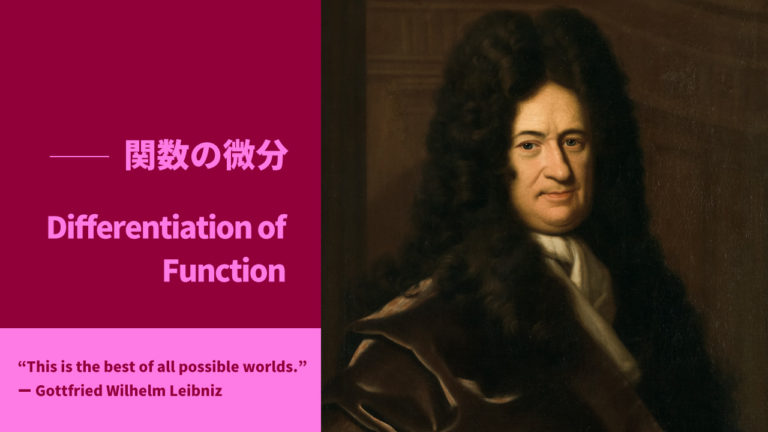
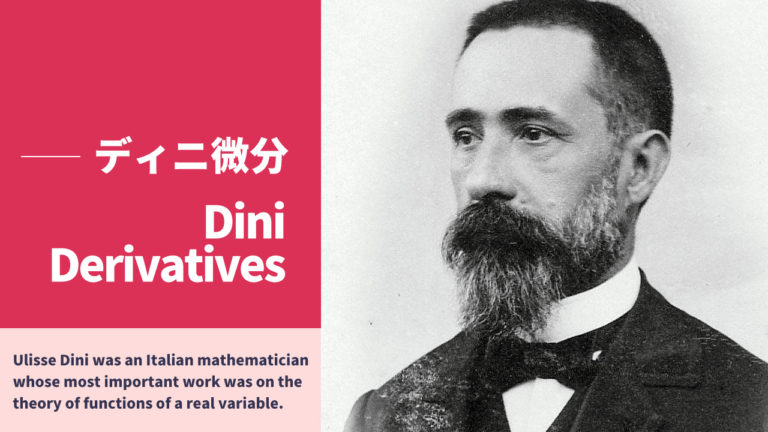

プレミアム会員専用コンテンツです
【ログイン】【会員登録】