リーマン積分に関する純変化量定理
\(a<b\)を満たす実数\(a,b\in \mathbb{R} \)を端点とする有界閉区間上に定義された関数\begin{equation*}f:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が\(\left[ a,b\right] \)上で連続かつ\(\left( a,b\right) \)上で微分可能であるものとします。つまり、導関数\begin{equation*}\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left( a,b\right) \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が存在するということです。関数\(f\)は区間の端点\(a,b\)において微分可能であるとは限らないため、導関数\(\frac{df}{dx}\)は点\(a,b\)において定義されているとは限らず、したがって\(\frac{df}{dx}\)が\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分可能であるか検討できない可能性があります。ただ、区間\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分可能な関数に関しては、区間\(\left[ a,b\right] \)上の有限個の点\(x\)に対して関数が定める値を自由に入れ替えても、その関数は\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分可能であることが保証されます。したがって、導関数\(\frac{df}{dx}\)が\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分可能であるか検討する際には、区間の端点\(a,b\)に対して\(\frac{df}{dx}\)が定める値\(\frac{df\left( a\right) }{dx},\frac{df\left( b\right) }{dx}\)を任意に選んでも一般性は失われません。いずれにせよ、そのようにして得られた関数\begin{equation*}\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分可能であるならば、\(f\)および\(\frac{df}{dx}\)は微分積分学の第2基本定理が要求する条件を満たすため、導関数\(\frac{df}{dx}\)の\(\left[ a,b\right] \)上の定積分について、\begin{equation*}\int_{a}^{b}\frac{df\left( x\right) }{dx}dx=f\left( b\right) -f\left(
a\right)
\end{equation*}という関係が成り立つことが保証されます。つまり、関数\(f\)の導関数\(\frac{df}{dx}\)の区間\(\left[ a,b\right] \)上での定積分をとれば、もとの関数\(f\)の区間\(\left[ a,b\right] \)上での変化が得られることを微分積分学の第2基本定理は保証します。これを純変化量定理(net change theorem)と呼びます。
導関数\(\frac{df}{dx}\)がそれぞれの点\(x\in \left( a,b\right) \)に対して定める値、すなわち点\(x\)における\(f\)の微分係数\begin{equation*}\frac{df\left( x\right) }{dx}=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f\left( x+h\right)
-f\left( x\right) }{h}
\end{equation*}とは、点\(x\)における\(f\left(x\right) \)の瞬間変化率に相当する概念です。純変化量定理によると、この瞬間変化率\(\frac{df\left( x\right) }{dx}\)を区間\(\left[ a,b\right] \)上でリーマン積分することにより、変数\(x\)が点\(a\)から点\(b\)へ変化する場合の前後における\(f\left( x\right) \)の変化量\begin{equation*}f\left( b\right) -f\left( a\right)
\end{equation*}が得られます。
単調増加関数とルベーグ積分に関する純変化量定理
ルベーグ積分に関しても純変化量定理は成立するのでしょうか。まずは単調関数を対象に議論を行います。
実数空間\(\mathbb{R} \)とルベーグ可測集合族\(\mathfrak{M}_{\mu }\)およびルベーグ測度\(\mu \)からなるルベーグ測度空間\(\left( \mathbb{R} ,\mathfrak{M}_{\mu },\mu \right) \)が与えられているものとします。
\(a<b\)を満たす実数\(a,b\in \mathbb{R} \)を端点とする有界閉区間上に定義された関数\begin{equation*}f:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が\(\left[ a,b\right] \)上で単調増加関数であるものとします。つまり、\begin{equation*}\forall x,x^{\prime }\in \left( a,b\right) :\left[ x<x^{\prime }\Rightarrow
f\left( x\right) \leq f\left( x^{\prime }\right) \right]
\end{equation*}が成り立つということです。
\(\left[ a,b\right] \)上で単調増加な関数は\(\left( a,b\right) \)上においても単調増加であるため、\(f\)は\(\left( a,b\right) \)上で単調増加関数です。するとルベーグの定理より、\(f\)は\(\left( a,b\right) \)上のほとんどいたるところで微分可能であることが保証されます。つまり、単調増加関数\(f\)が微分可能ではない\(\left( a,b\right) \)上の点からなる集合\begin{equation*}A=\left\{ x\in \left( a,b\right) \ |\ \overline{D}f\left( x\right) =+\infty
\right\} \cup \left\{ x\in \left( a,b\right) \ |\ 0\leq \underline{D}f\left(
x\right) <\overline{D}f\left( x\right) <+\infty \right\}
\end{equation*}について、\begin{equation*}
\mu ^{\ast }\left( A\right) =0
\end{equation*}が成り立つということです。したがって、導関数\(\frac{df}{dx}\)が\(\left( a,b\right) \)上のほとんどいたるところで定義されます。つまり、\begin{equation*}\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left( a,b\right) \backslash A\rightarrow \mathbb{R} \end{equation*}が定義可能です。
単調増加関数の導関数は非負値をとるため、\(\frac{df}{dx}\)は\(\left( a,b\right) \backslash A\)上で非負値をとります。つまり、\begin{equation*}\forall x\in \left( a,b\right) \backslash A:\frac{df\left( x\right) }{dx}\geq 0
\end{equation*}です。加えて、\(f\)が単調増加である場合に\(\frac{df}{dx}\)はルベーグ可測関数になることが証明されます。以上より、\(\frac{df}{dx}\)は\(\left( a,b\right) \backslash A\)上に定義された非負値をとるルベーグ可測関数であることが明らかになりました。したがって、そのルベーグ積分\begin{equation*}\int_{\left( a,b\right) \backslash A}\frac{df}{dx}
\end{equation*}をとることができます。加えて、以下の関係\begin{equation*}
\int_{\left( a,b\right) \backslash A}\frac{df}{dx}\leq f\left( b\right)
-f\left( a\right)
\end{equation*}が成り立つことが証明されます。右辺\(f\left(b\right) -f\left( a\right) \)は有限な実数であるため左辺もまた有限な実数であり、したがってこの不等式は\(\frac{df}{dx}\)が\(\left( a,b\right) \backslash A\)上でルベーグ積分可能であることも同時に意味します。証明ではファトゥの補題を利用します。
-f\left( a\right)
\end{equation*}が成り立つ。
上の命題中の導関数\begin{equation}
\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left( a,b\right) \backslash A\rightarrow \mathbb{R} \quad \cdots (1)
\end{equation}が与えられた状況において、\(A\cup \left\{ a,b\right\} \)上の点\(x\)に対して実数\(\frac{df\left(x\right) }{dx}\)を割り当てれば\(\frac{df}{dx}\)の定義域を\(\left[ a,b\right] \)に拡大した関数\begin{equation}\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left[ a,b\right] \rightarrow \mathbb{R} \quad \cdots (2)
\end{equation}が得られます。\(A\cup \left\{a,b\right\} \)は零集合であるため、\(A\cup \left\{ a,b\right\} \)上の点\(x\)に対する\(\frac{df\left( x\right) }{dx}\)としてどのような値を選んだ場合でも、\(\left[ a,b\right] \)上に定義された関数\(\frac{df}{dx}\)はいずれも\(\left[ a,b\right] \)上でルベーグ可測になることが保証されます。\(\left( 1\right) \)と\(\left( 2\right) \)は\(\left[ a,b\right] \)上のほとんどいたるところで等しいため\(\left( 2\right) \)は\(\left[ a,b\right] \)上でルベーグ積分可能であるとともに、\begin{equation*}\int_{\left[ a,b\right] }\frac{df}{dx}=\int_{\left( a,b\right) \backslash A}\frac{df}{dx}
\end{equation*}を得ます。以上の事実と先の命題を踏まえると、\begin{equation*}
\int_{\left[ a,b\right] }\frac{df}{dx}\leq f\left( b\right) -f\left(
a\right)
\end{equation*}を得ます。
a\right)
\end{equation*}が成り立つ。
\end{equation*}を定めるものとします。\(f\)は単調増加関数であるため、\(\left[ 0,1\right] \)上のほとんどいたるところで微分可能です。実際、\(f\)は\(\left( 0,1\right] \)上で微分可能であり、導関数\(\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left( 0,1\right] \rightarrow \mathbb{R} \)はそれぞれの\(x\in \left( 0,1\right] \)に対して、\begin{equation*}\frac{df\left( x\right) }{dx}=\frac{1}{2\sqrt{x}}
\end{equation*}を定めます。\(\frac{df}{dx}\)は非負値をとるとともに、\begin{eqnarray*}\lim_{x\rightarrow 0+}\frac{df\left( x\right) }{dx} &=&\lim_{x\rightarrow 0+}\frac{1}{2\sqrt{x}} \\
&=&+\infty
\end{eqnarray*}が成り立ちます。\(\frac{df}{dx}\)は\(\left( 0,1\right] \)上で広義リーマン積分可能であるため、\begin{eqnarray*}\int_{\left[ 0,1\right] }\frac{df}{dx} &=&\int_{0}^{1}\frac{df\left(
x\right) }{dx}dx\quad \because \text{ルベーグ積分と広義リーマン積分の関係} \\
&=&\int_{0}^{1}\frac{1}{2\sqrt{x}}dx \\
&=&1
\end{eqnarray*}を得ます。その一方で、\begin{eqnarray*}
f\left( 1\right) -f\left( 0\right) &=&\sqrt{1}-\sqrt{0} \\
&=&1
\end{eqnarray*}となるため、\begin{equation*}
\int_{\left[ 0,1\right] }\frac{df}{dx}=f\left( 1\right) -f\left( 0\right)
\end{equation*}が成立しますが、この結果は先の命題の主張と整合的です。
純変化量定理は等号で成立するとは限らない
先の命題中の主張は等号で成立するとは限りません。以下の例より明らかです。
\end{equation*}です。カントール関数\(f\)はカントール集合の補集合\(\left[ 0,1\right] \backslash \mathcal{C}\)上において定数関数です。定数関数は微分可能であるとともに導関数は\(0\)であるため、\begin{equation*}\forall x\in \left[ 0,1\right] \backslash \mathcal{C}:\frac{df\left(
x\right) }{dx}=0
\end{equation*}であり、したがって、\begin{equation*}
\int_{\left[ 0,1\right] \backslash \mathcal{C}}\frac{df}{dx}=0
\end{equation*}を得ます。そこで、カントール関数の導関数の定義域を\(\left[ 0,1\right] \)へ拡張して、\begin{equation*}\frac{df}{dx}:\mathbb{R} \supset \left[ 0,1\right] \rightarrow \left[ 0,1\right] \end{equation*}とした場合にも、\begin{equation*}
\int_{\left[ 0,1\right] }\frac{df}{dx}=0
\end{equation*}が成り立ちます。その一方、カントール関数の定義より、\begin{eqnarray*}
f\left( 1\right) -f\left( 0\right) &=&1-0 \\
&=&1
\end{eqnarray*}であるため、\begin{equation*}
\int_{\left[ 0,1\right] }\frac{df}{dx}<f\left( 1\right) -f\left( 0\right)
\end{equation*}を得ます。以上より、先の命題の主張は等号で成立するとは限らないことが明らかになりました。


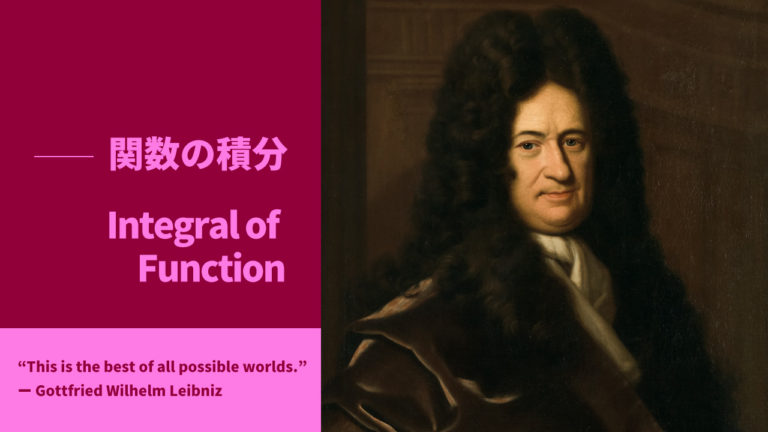
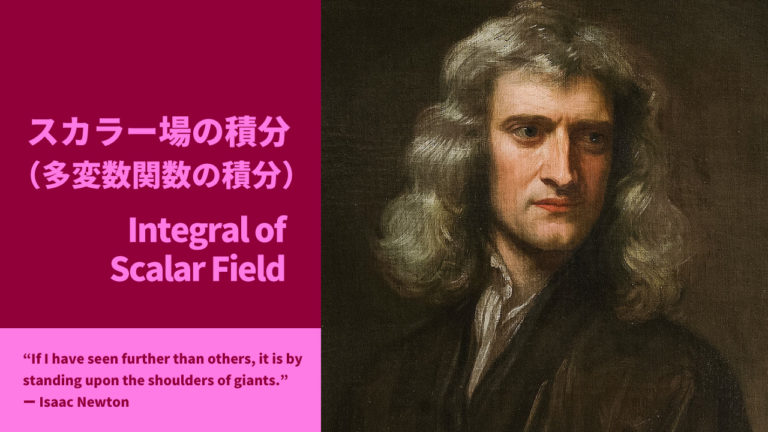
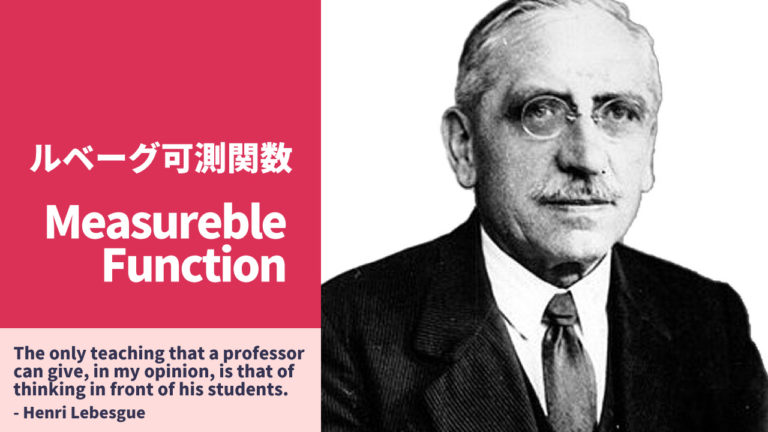
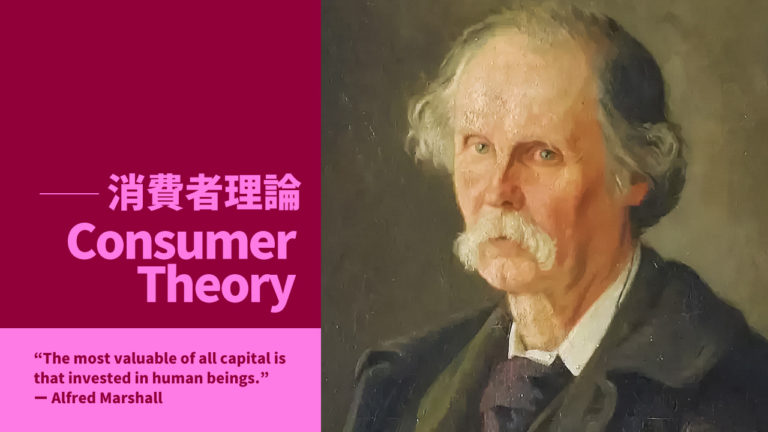
プレミアム会員専用コンテンツです
【ログイン】【会員登録】