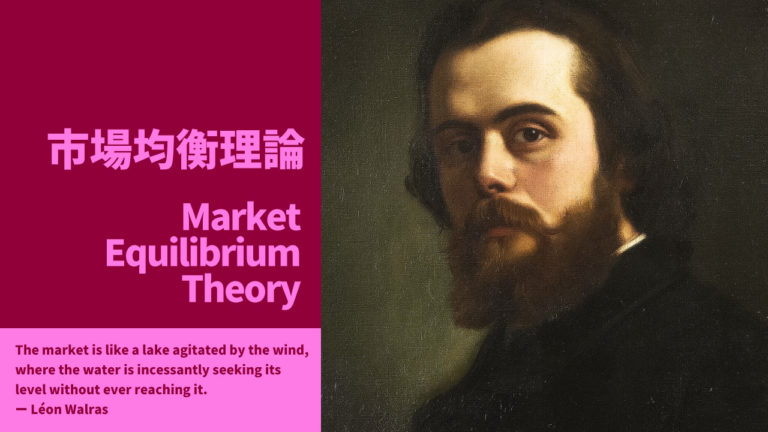
私有経済におけるパレート効率的な配分
私有経済において消費者は効用最大化原理にもとづいて行動し、生産者は利潤最大化原理にもとづいて行動する一方で、それとは別に、社会的に望ましい配分を考えることもできます。パレート効率性という基準のもとで社会的に望ましい配分を定義します。
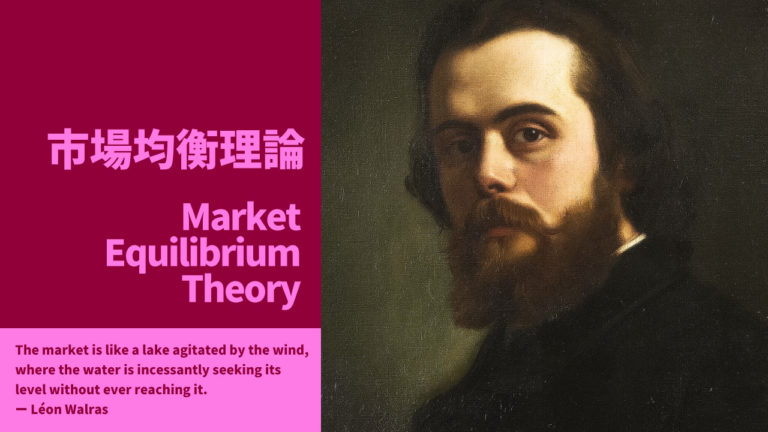
純粋交換経済における厚生経済学の基本定理
純粋交換経済においてワルラス均衡のもとで実現する配分はパレート効率的です(厚生経済学の第1基本定理)。また、パレート効率的な配分が与えられたとき、適切な再配分と価格体系のもとでは、その配分をワルラス均衡として実現できます(厚生経済学の第2基本定理)。
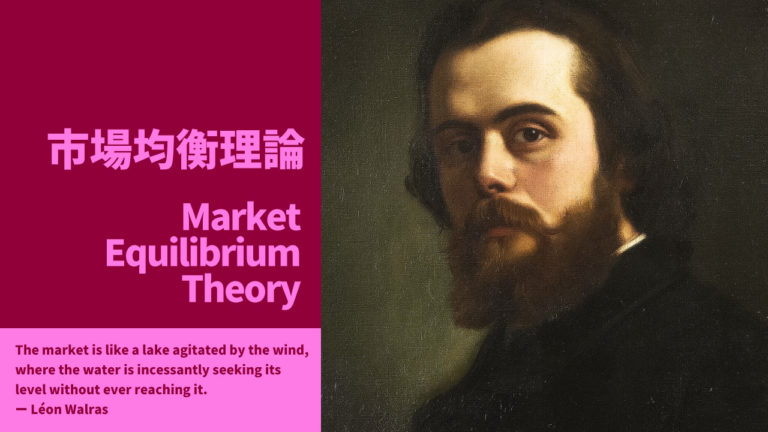
純粋交換経済におけるワルラス均衡
純粋交換経済においてそれぞれの消費者は効用最大化原理にもとづいて行動します。純粋交換経済に価格メカニズムを導入した場合に実現する結果をワルラス均衡(競争均衡)として定義します。
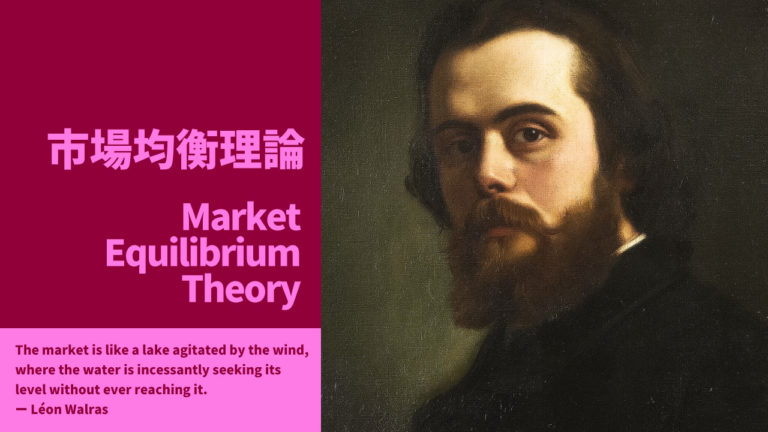
純粋交換経済におけるパレート効率的な配分
純粋交換経済においてそれぞれの消費者は効用最大化原理にもとづいて行動する一方で、それとは別に、社会的に望ましい配分を考えることもできます。パレート効率性という基準のもとで社会的に望ましい配分を定義します。
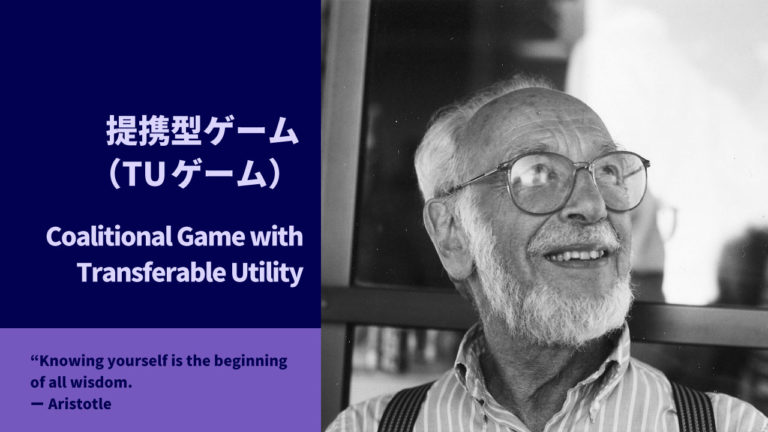
凸ゲーム・優モジュラゲーム(TUゲームの分類)
協力ゲームが譲渡可能効用を前提とする提携型ゲーム(TUゲーム)として記述されているとともに特性関数が凸性(優モジュラ性)を満たす場合、そのようなゲームを凸ゲーム(優モジュラゲーム)と呼びます。
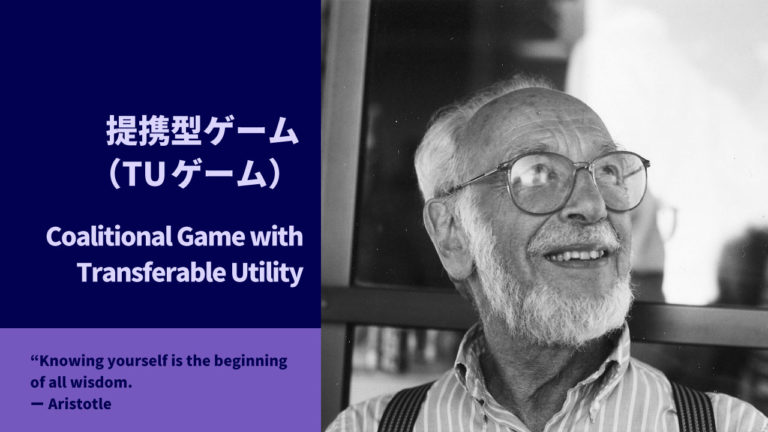
優加法ゲーム(TUゲームの分類)
協力ゲームが譲渡可能効用を前提とする提携型ゲーム(TUゲーム)として記述されているとともに特性関数が優加法性を満たす場合、そのようなゲームを優加法ゲームと呼びます。
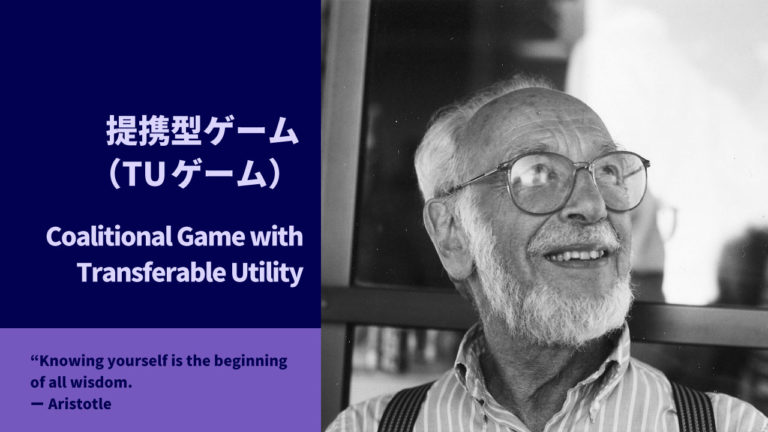
単調ゲーム(TUゲームの分類)
協力ゲームが譲渡可能効用を前提とする提携型ゲーム(TUゲーム)として記述されているとともに特性関数が単調性を満たす場合、そのようなゲームを単調ゲームと呼びます。
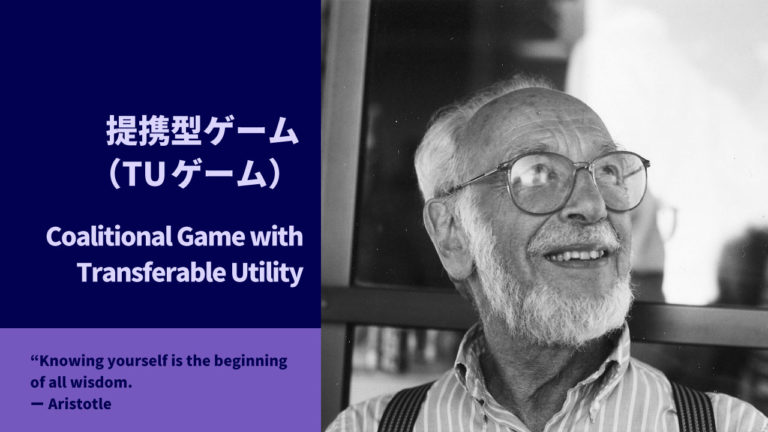
譲渡可能効用を前提とした提携型ゲーム(TUゲーム)
協力ゲームにおいて提携の内部においてプレイヤーどうしが金銭を媒介する形で利得を自由に譲渡できる場合、そのような戦略的状況は譲渡可能効用を前提とする提携型ゲーム(TUゲーム)と呼ばれるモデルとして定式化されます。
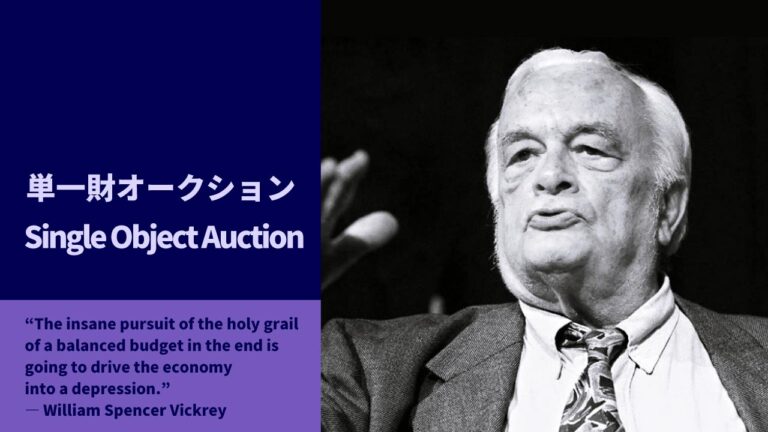
タイ・ブレークを考慮した第一価格封印オークション(ファーストプライス・オークション)
単一財オークションでは複数の入札者が最高額を入札する状況が起こり得ます。そのような状況に対応できる形で第一価格封印オークション(ファーストプライスオークション)を修正します。
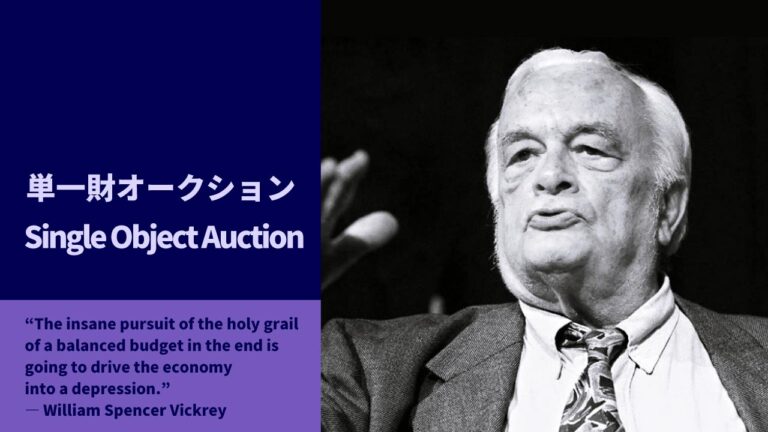
SIPVモデルにおける第一価格封印オークションの均衡分析
単一財オークション環境がSIPVモデルである場合に、第一価格封印オークションのベイジアンナッシュ均衡において、入札者が直面する期待支払いや期待利得、オークションの主催者が直面する期待収入などを明らかにします。
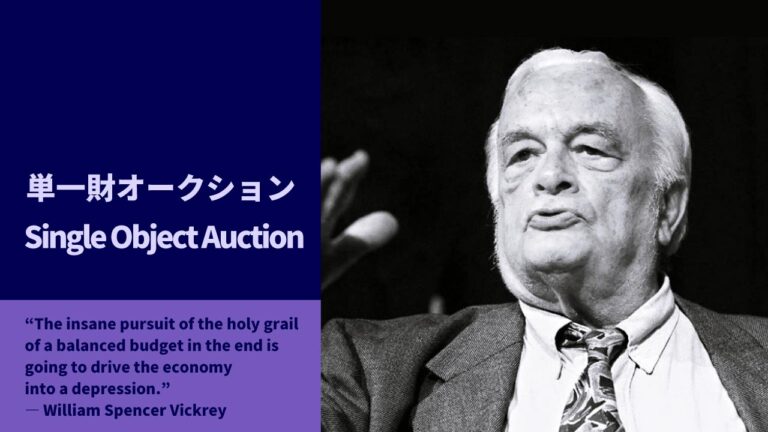
参加料を導入した第二価格封印オークション(セカンドプライス・オークション)
単一財オークションでは主催者が入札者たちから参加料を徴収することを望む状況は起こり得ます。そのような状況に対応できる形で第二価格封印オークション(セカンドプライスオークション)を修正します。
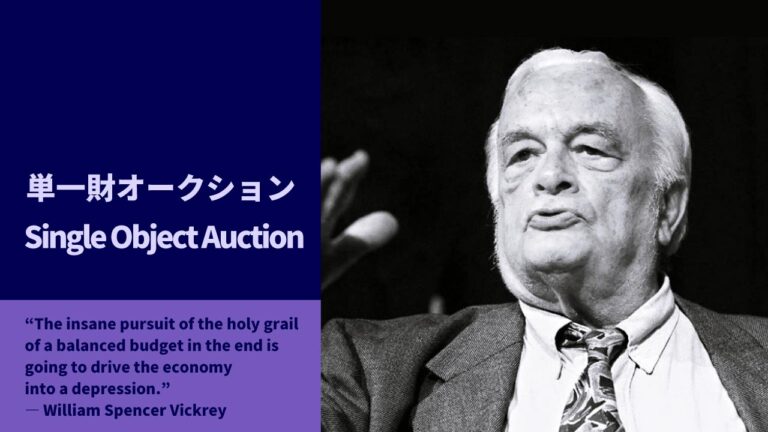
最低落札価格を導入した第二価格封印オークション(セカンドプライス・オークション)
単一財オークションでは商品の売り手が最低落札価格の導入を望む状況は起こり得ます。そのような状況に対応できる形で第二価格封印オークション(セカンドプライスオークション)を修正します。
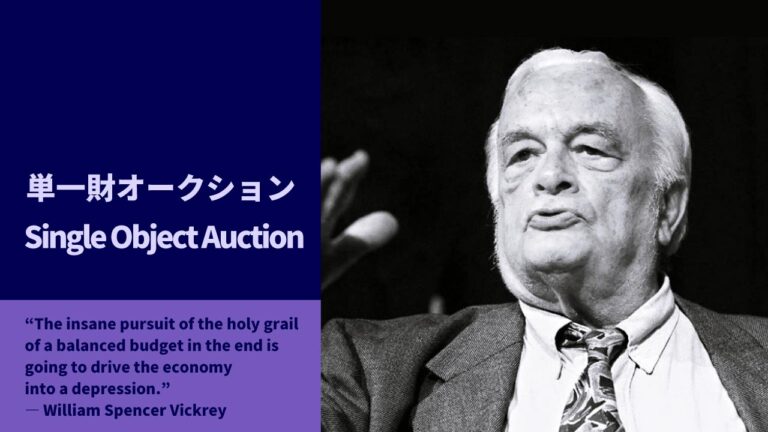
SIPVモデルのもとでの順序統計量と期待収入
単一オークションのSIPVモデルではすべての入札者たちのタイプが独立同一分布にしたがう確率変数とみなすことができるため、その順序統計量を定義することができます。
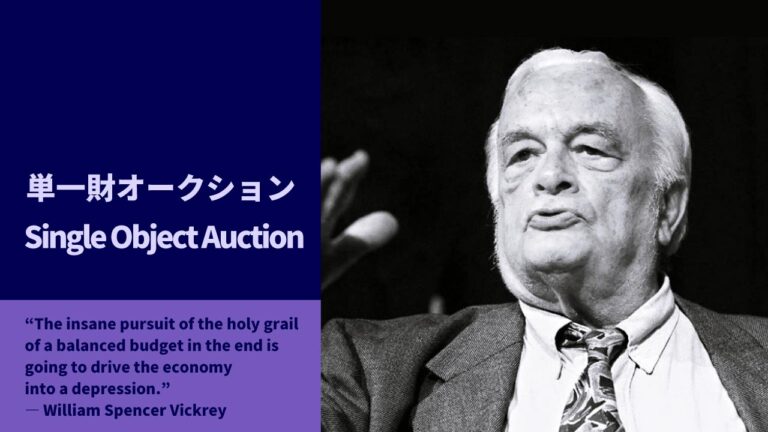
タイ・ブレークを考慮した第二価格封印オークション(セカンドプライス・オークション)
単一財オークションでは複数の入札者が最高額を入札する状況が起こり得ます。そのような状況に対応できる形で第二価格封印オークション(セカンドプライスオークション)を修正します。
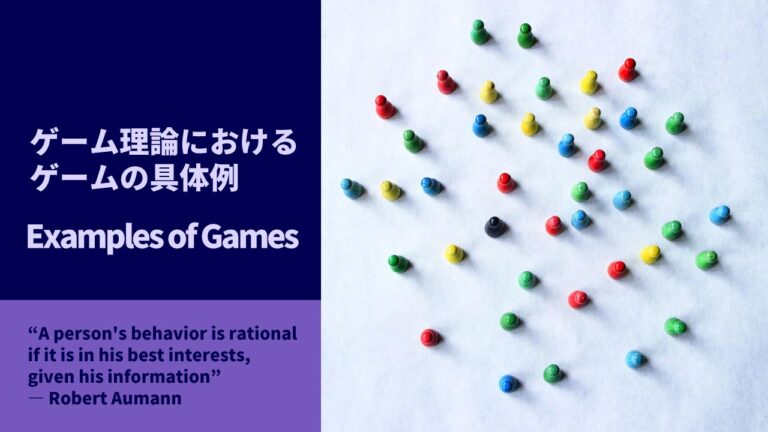
ギフト交換ゲーム(公平性と互恵性)
雇用者と社員の関係をモデル化したギフト交換ゲームと呼ばれる動学ゲームの理論的な結果と実験結果を比較することにより、人間の意思決定では公平性や互恵性が重要なファクターであることを浮き彫りにできます。
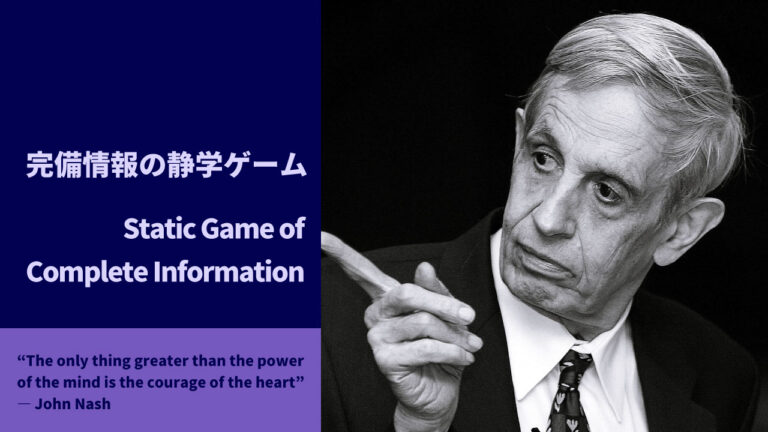
混合戦略によって広義支配される戦略の逐次消去
純粋戦略によって広義支配されない戦略が混合戦略によって広義支配される事態が起こり得ることを踏まえた上で、混合戦略によって広義支配される戦略の逐次消去と呼ばれる均衡概念を定義します。
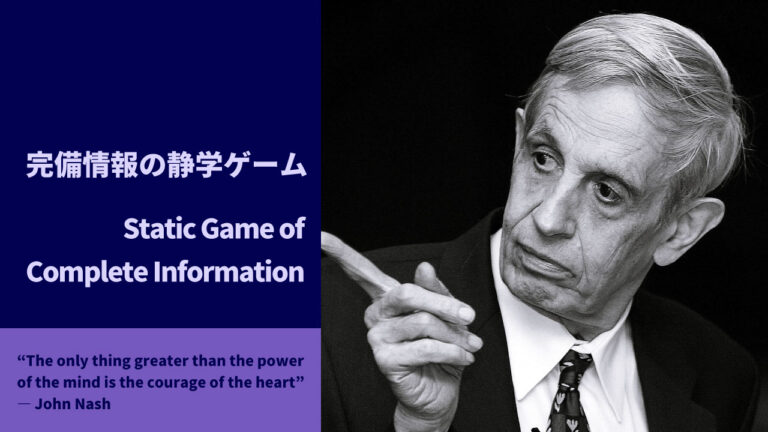
混合戦略によって狭義支配される戦略の逐次消去
純粋戦略によって狭義支配されない戦略が混合戦略によって狭義支配される事態が起こり得ることを踏まえた上で、混合戦略によって狭義支配される戦略の逐次消去と呼ばれる均衡概念を定義します。
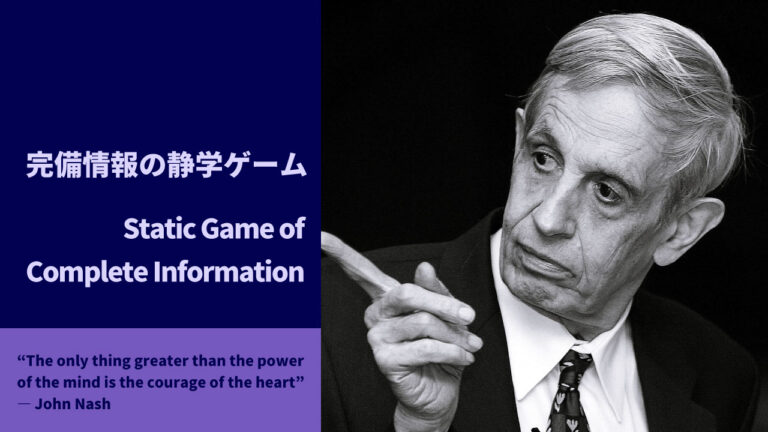
対称ゲームに対称ナッシュ均衡が存在するための条件
対称的な戦略型ゲームに対称的な純粋戦略ナッシュ均衡が存在するための条件を明らかにします。以上の事実を用いることにより、有限かつ対称的な戦略型ゲームの混合拡張には対称的な混合戦略ナッシュ均衡が存在することを示します。
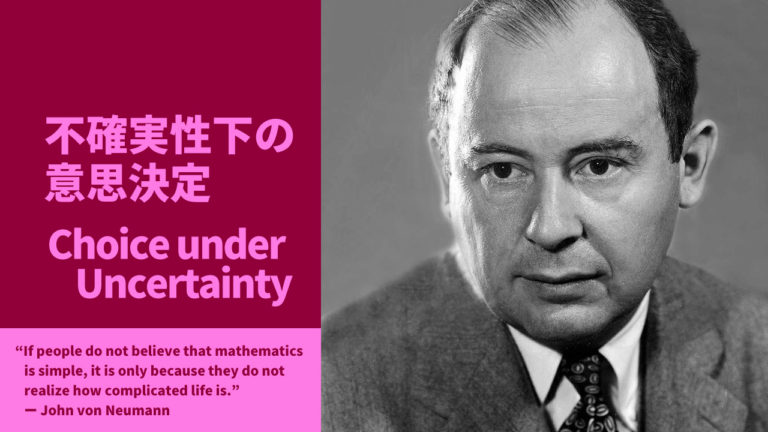
アロー・プラットの絶対的リスク回避度
アロー・プラットの絶対的リスク回避度の符号を通じて主体のリスク選好(リスク回避的・中立的・愛好的)を判定できます。また、絶対的リスク回避度の値を通じてリスク回避の度合いを比較できます。
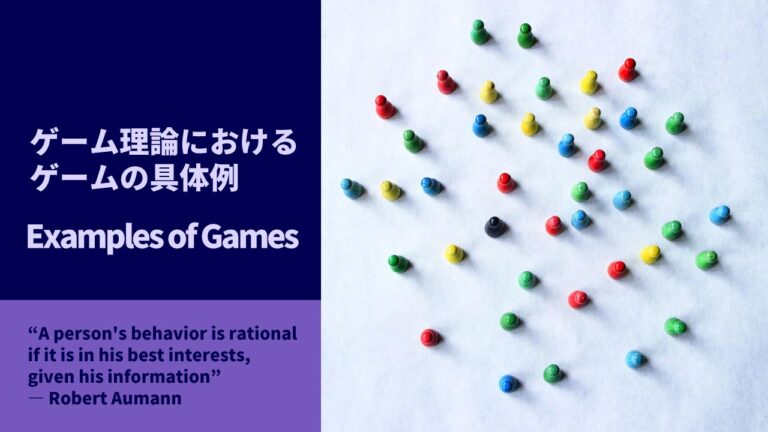
チキンゲームとコミットメント
2人のドライバーがお互いに相手の車に向かって一直線に走行し、衝突寸前まで車を走らせる度胸試しをチキンゲームと呼びます。チキンゲームを完備情報の静学ゲームとして定式化した上でナッシュ均衡を求めます。
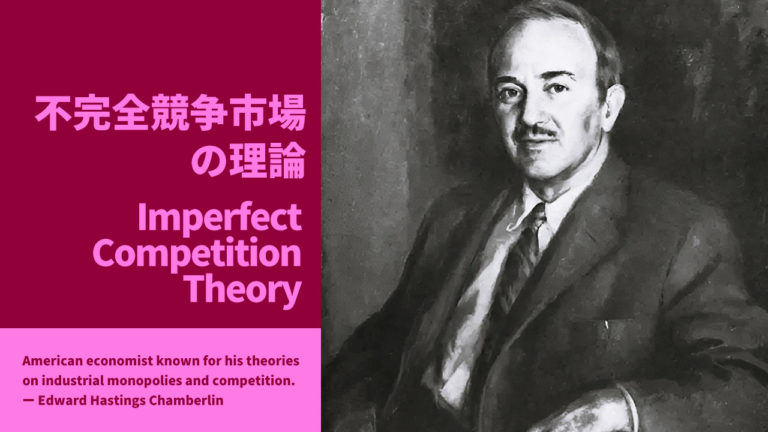
シュタッケルベルグの数量競争(複占市場における動学的数量競争)
複占市場においてカルテルを形成せずに競争する企業が商品の供給量を同時に決定する状況をクールノー競争と呼ばれるモデルを用いて記述しましたが、同様の市場において2つの企業が商品の供給量を順番に決定する場合には何が起こるでしょうか。
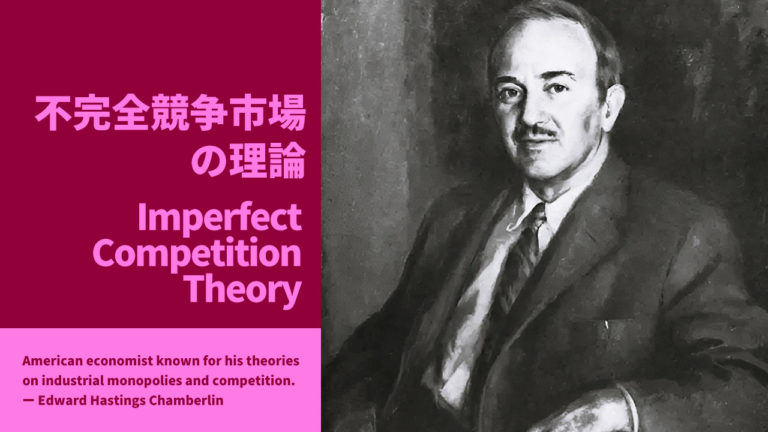
製品差別化が行われている場合のベルトラン競争
2つの企業が生産する商品が代替財ないし補完財である状況において行われるベルトラン競争を定式化するとともに、そこでのベルトラン均衡を特定します。
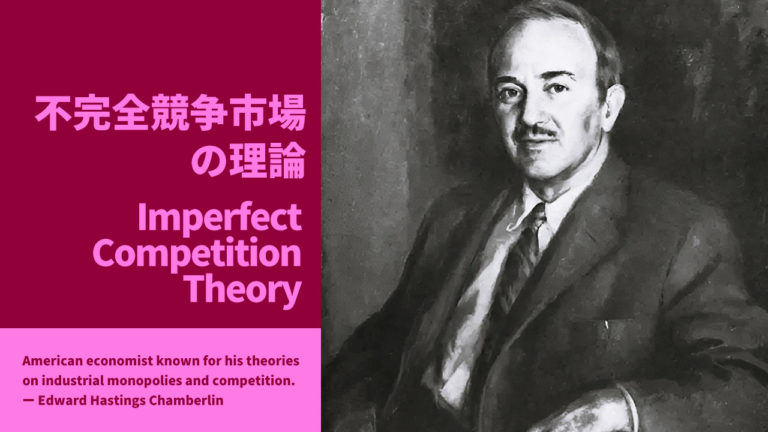
製品差別化が行われている場合のクールノー競争
2つの企業が生産する商品が代替財ないし補完財である状況において行われるクールノー競争を定式化するとともに、そこでのクールノー均衡を特定します。
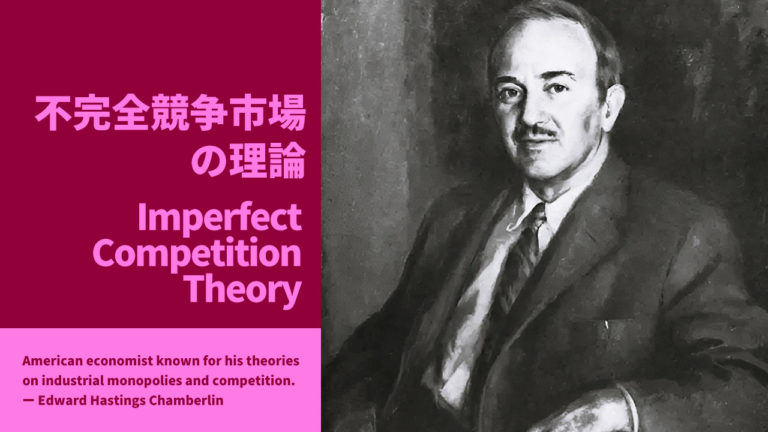
複数業種にまたがる独占(範囲の経済や範囲の不経済が成立する場合)
同一企業が複数の商品市場を独占しており、なおかつ商品の生産に範囲の経済や範囲の不経済が成立する場合の利潤最大化問題について解説します。
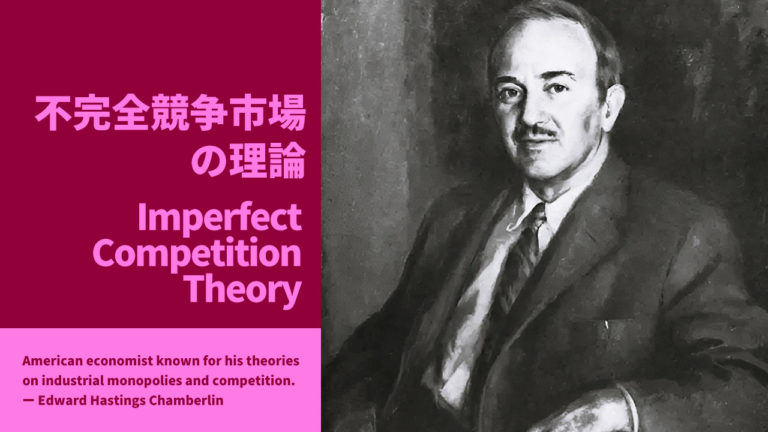
複数業種にまたがる独占(代替財や補完財を供給する場合)
同一企業が複数の商品市場を独占しており、なおかつ商品どうしが代替財ないし補完財である場合の利潤最大化問題について解説します。
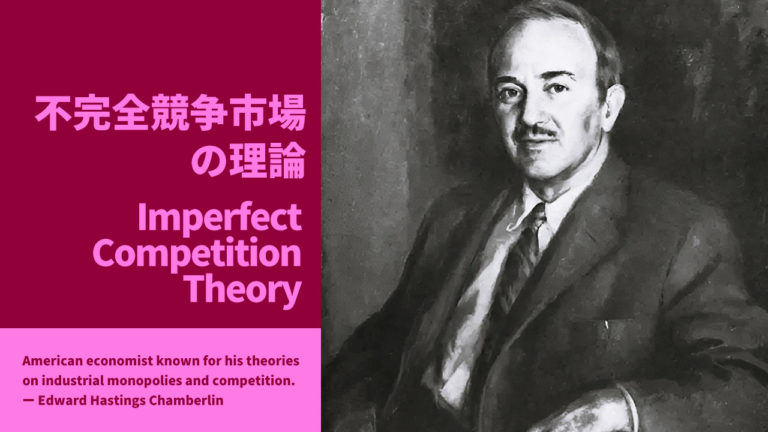
価格に関するカルテルの不安定性(カルテル破り)
複占市場の線型モデルにおいて2つの企業が結合利潤を最大化するような価格を選択するよう約束した場合においても、その約束に拘束力がない場合には、実際に実現するのは、両社とも価格競争を行うという結果(ベルトラン競争)であり、これは両社にとって効率的ではありません。
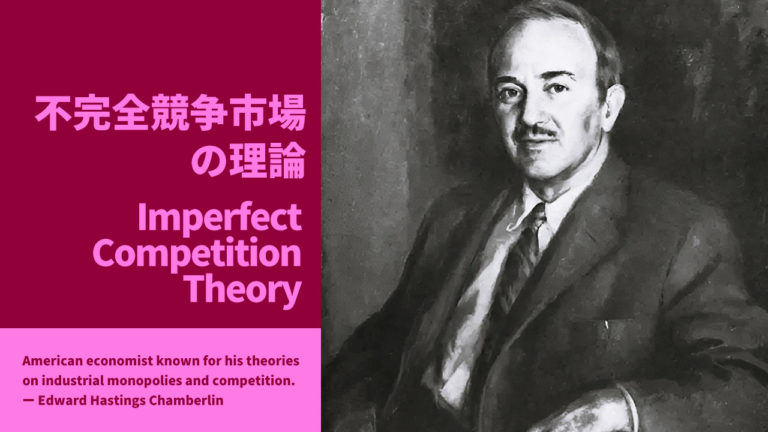
生産量に関するカルテルの不安定性(カルテル破り)
複占市場の線型モデルにおいて2つの企業が結合利潤を最大化するような生産計画を実行するよう約束した場合においても、その約束に拘束力がない場合には、実際に実現するのは、両社とも数量競争を行うという結果(クールノー競争)であり、これは両社にとって効率的ではありません。
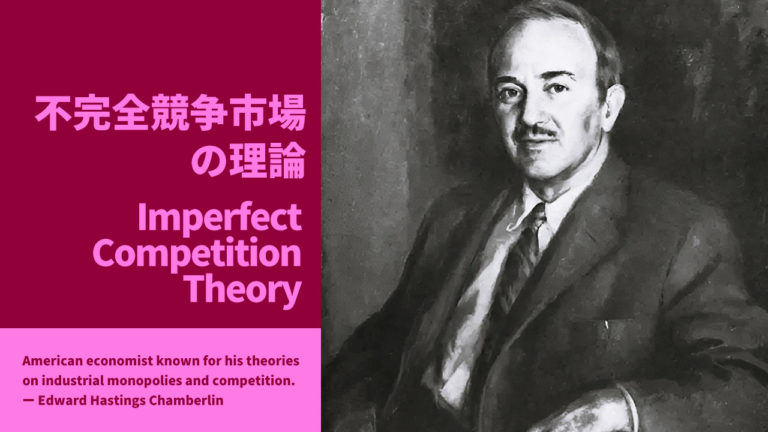
技術水準が異なる企業間のベルトラン競争
等しい限界費用を持つ2つの企業がベルトラン競争を行う場合、均衡において両企業の利潤はゼロになります。一方、限界費用に差がある2つの企業がベルトラン競争を行う場合には、均衡において、相対的に効率的な企業は正の利潤を得られます。
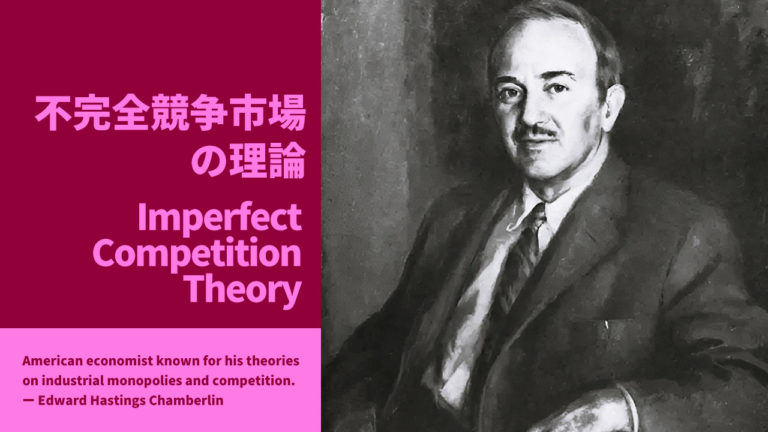
技術水準が異なる企業間のクールノー競争
クールノー競争が行われる複占市場において企業間の技術水準に差がある場合、すなわち企業間で限界費用に差がある場合にも、両企業の間の技術水準の差が十分小さい場合にはクールノー均衡が存在します
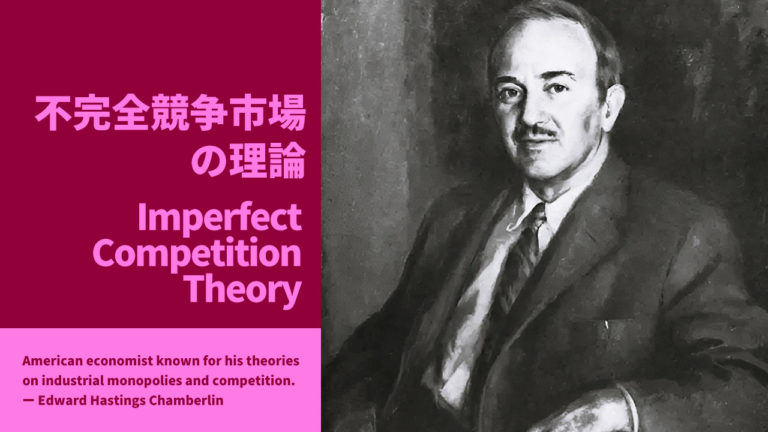
生産力に制約がある企業間のベルトラン競争(ベルトラン・エッジワースモデル)
複占市場においてベルトラン競争が行われる場合には完全競争市場と同様に均衡価格が限界費用と一致しますが(ベルトランのパラドクス)、企業の生産力に制約がある場合には、均衡価格が限界費用を上回る事態が起こり得ます。
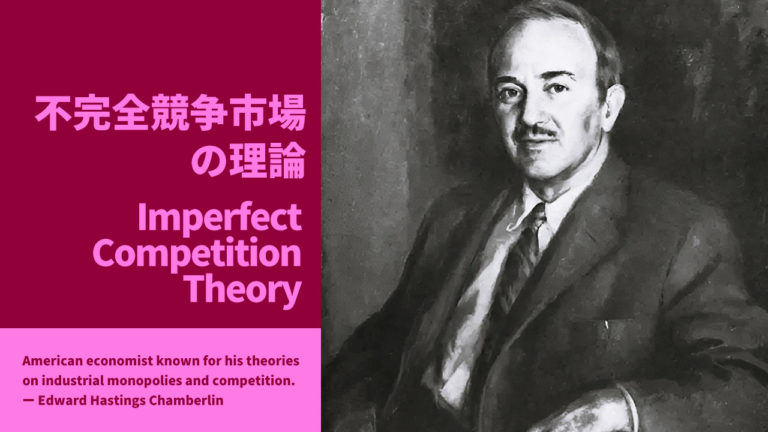
企業数の変化がベルトラン競争に与える影響(n企業ベルトラン競争)
ベルトラン競争が行われる市場において企業数が1から2へ変化すると均衡価格が限界費用まで急激に下落して死荷重が消失しますが、企業数をそれ以上増やした場合、均衡における各企業の供給量は企業数に逆比例する形で減少していく一方で、均衡価格や死荷重は変化しません。
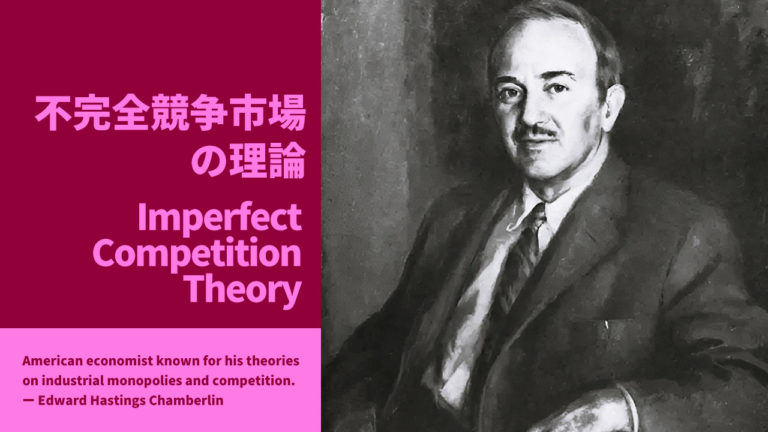
企業数の変化がクールノー競争に与える影響(n企業クールノー競争)
クールノー競争において企業数が増加するにつれて企業間の競争が激化し、クールノー均衡は完全競争均衡へ限りなく近づいていきます。
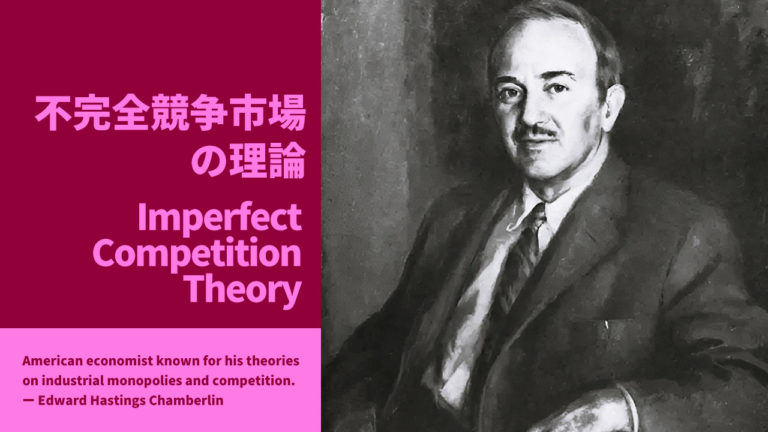
ベルトラン均衡の社会的効率性
通常、独占市場や複占市場、寡占市場などの不完全競争市場において社会的余剰は最大化されません。一方、複占市場においてベルトラン競争が行われる場合には完全競争市場と同様に社会的余剰が最大化されます。こうした現象をベルトランのパラドクスと呼びます。
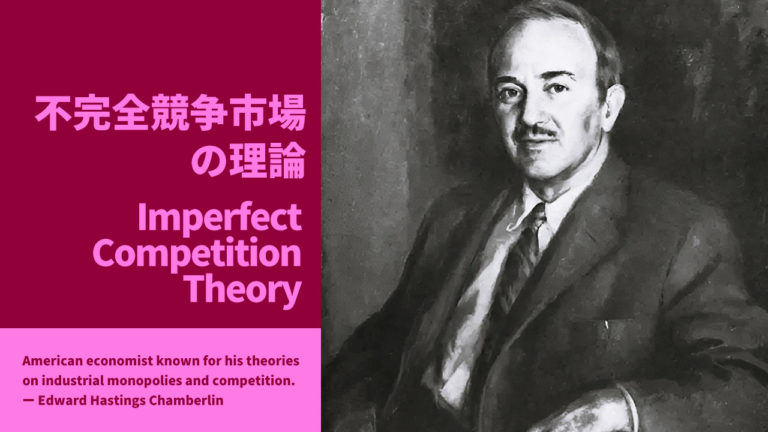
ベルトラン競争(複占市場における価格競争)
同質財が2つの企業によって供給される複占市場において、企業がカルテルを形成せずに価格を決定する状況をベルトラン競争モデルとして定式化するとともに、そこでのナッシュ均衡を特定します。
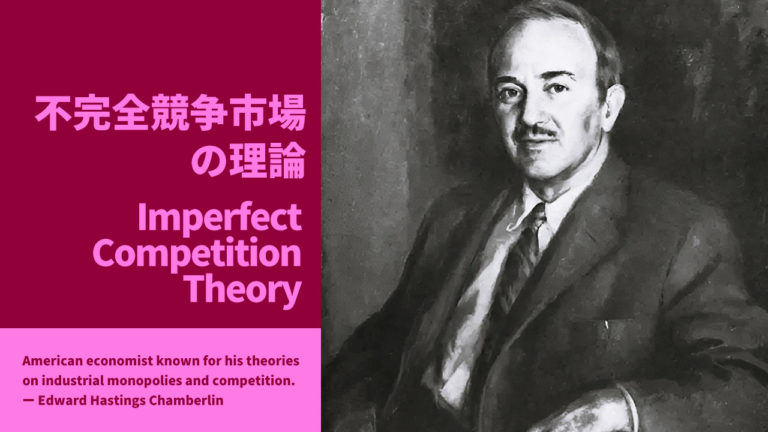
クールノー均衡の社会的効率性
複占市場においてクールノー競争が行われる場合に実現する社会的余剰は、完全競争が行われる場合の社会的余剰よりも小さく、カルテルが形成される場合の社会的余剰よりも大きくなります。
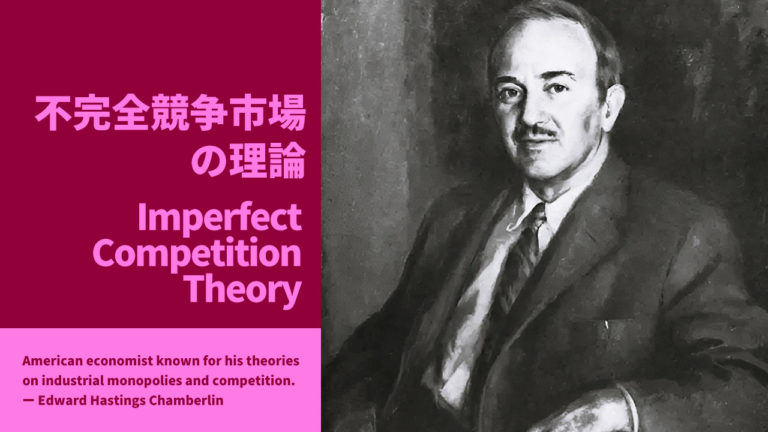
複数業種にまたがる独占(市場と生産がそれぞれ独立している場合)
同一企業が複数の商品市場を独占しており、なおかつ商品間で市場と生産それぞれ独立している場合の利潤最大化問題について解説します。
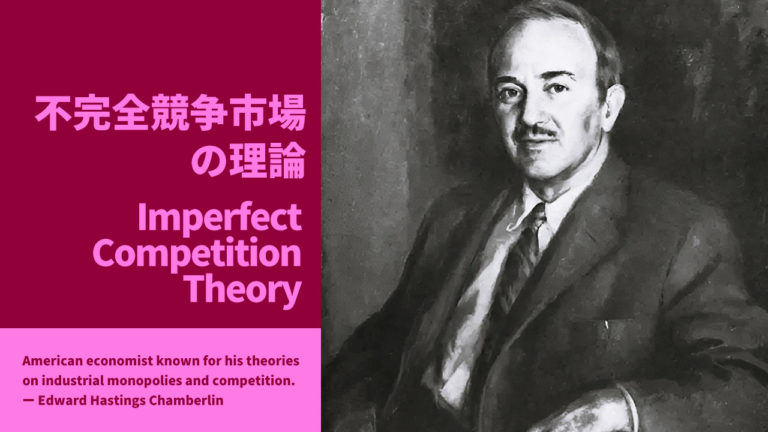
独占市場への政府介入:限界費用価格規制
独占均衡では死荷重が発生するため社会的余剰が最大化されません。社会的余剰を最大化するために、独占企業が供給する商品の価格を競争均衡価格へ抑える政策を限界費用価格規制と呼びます。
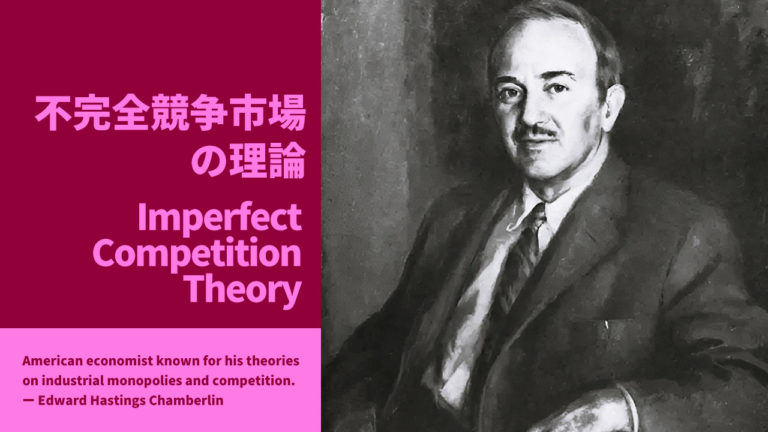
生産量に関するカルテルが形成される場合の複占均衡
複占市場においてカルテルを形成する2つの企業は、カルテルの限界収入と両企業の限界費用が一致するような生産計画を選択することにより結合利潤を最大化することができます。
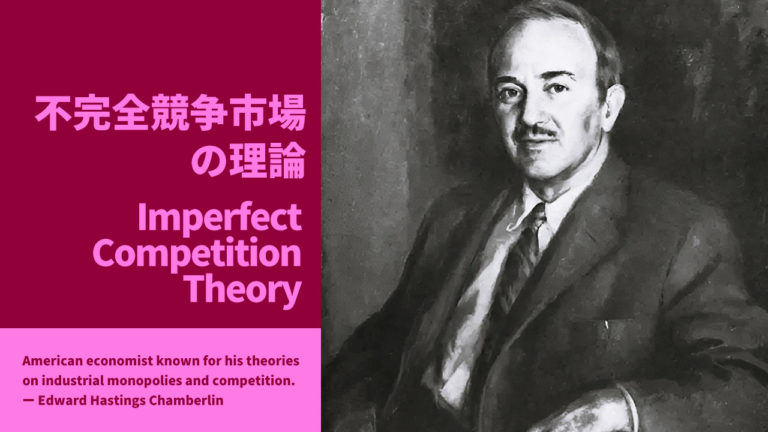
クールノー競争(複占市場における数量競争)
同質財が2つの企業によって供給される複占市場において、企業がカルテルを形成せずに供給量を決定する状況をクールノー競争モデルとして定式化するとともに、そこでのナッシュ均衡を特定します。
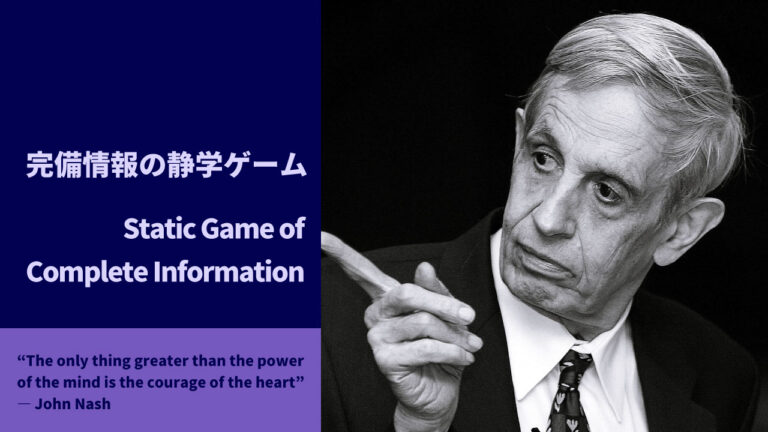
ミニマックス定理
2人ゼロ和ゲームにおいて一方のプレイヤーのマックスミニ値と他方のプレイヤーのミニマックス値が一致することは、ゲームに鞍点(ナッシュ均衡)が存在するための必要十分条件です。特に、有限ゲームの混合拡張においてマックスミニ値とミニマックス値は常に一致します。
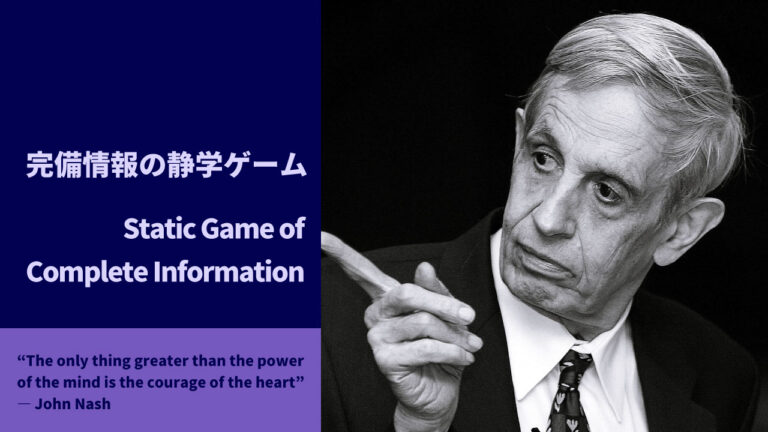
マックスミニ戦略とミニマックス戦略
2人ゼロ和ゲームにおいて、最低でも確保できる利得を最大化する戦略をマックスミニ戦略と呼び、最悪の状況で直面する被害を最小化する戦略をミニマックス戦略と呼びます。
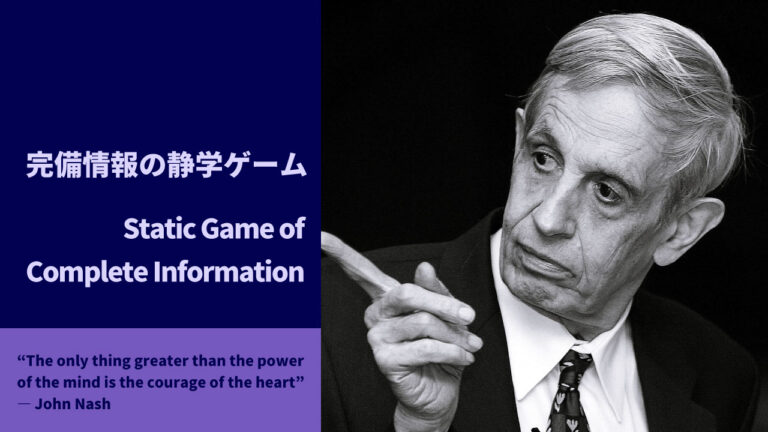
ゼロ和ゲーム(定和ゲーム)
戦略型ゲームのプレイヤーが2人であるとともに、どのような結果が実現した場合にも両者が得る利得の和が必ずゼロであるならば、そのようなゲームをゼロ和ゲーム(ゼロサムゲーム)と呼びます。
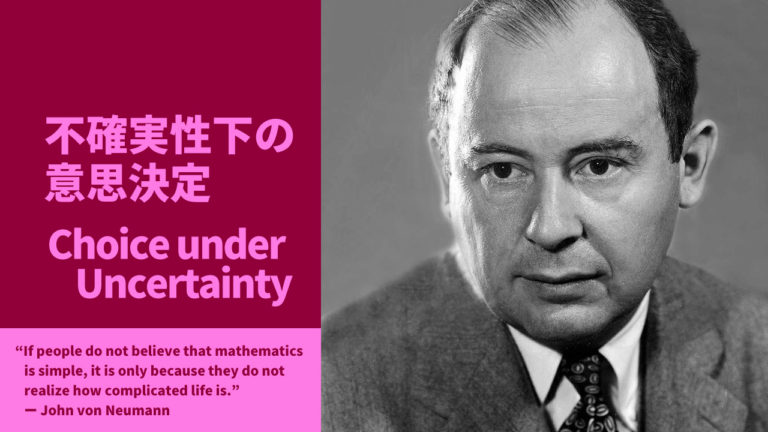
BDMメカニズム(クジの確実同値額の測定実験)
主体にとってのクジの確実性等価を測定するためにはBDMメカニズム(Becker-DeGroot-Marschakメカニズム)と呼ばれる実験手法が有効です。BDMメカニズムは耐戦略性を満たすため、主体にとってクジの確実性等価を正直に表明することが支配戦略になります。
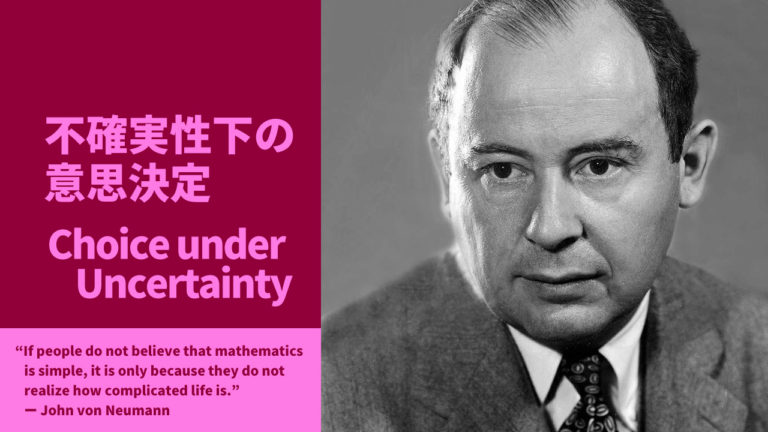
クジの確率プレミアム
ある結果を確実に得ることと、その結果より望ましい結果と望ましくない結果が等確率で起こるクジを無差別にするための確率の調整幅を確率プレミアムと呼びます。確率プレミアムの符号を観察することにより、主体のリスク選好を特定できます。