
絶対収束複素級数(絶対値級数を用いた複素級数の収束判定)
複素級数が与えられたとき、その絶対値級数が収束する場合、もとの複素級数を絶対収束複素級数と呼びます。絶対収束複素級数は収束します。また、収束する一方で絶対収束しない複素級数を条件収束複素級数と呼びます。
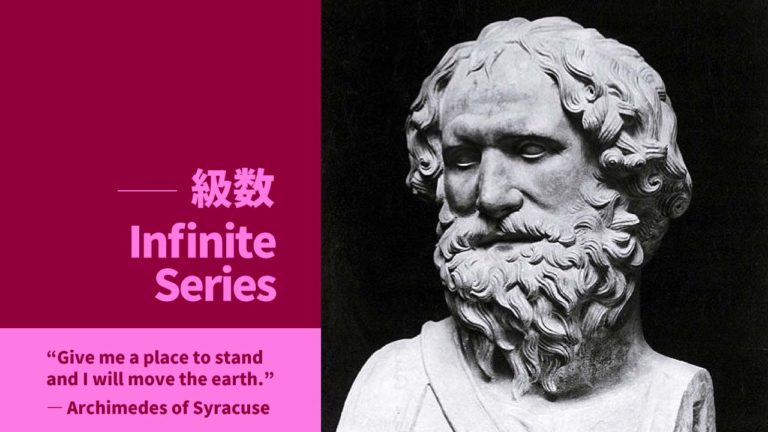
級数どうしの差の収束可能性(差の法則)
収束級数どうしの差として定義される級数は収束します。収束級数と発散級数の差として定義される級数は発散します。発散級数どうしの差として定義される級数は収束する場合と発散する場合の両方のパターンがあります。

等比複素数列とその部分和および極限
隣り合う項が共通の比を持つ複素数列を等比複素数列と呼びます。等比複素数列を定義するとともに、その部分和を明らかにした上で、等比複素数列が収束する・収束しない条件を明らかにします。

等差複素数列とその部分和および極限
隣り合う項が共通の差を持つ複素数列を等差複素数列と呼びます。等差複素数列を定義するとともに、その部分和を明らかにした上で、等差複素数列が収束する・収束しない条件を明らかにします。

複素級数の収束可能性と複素数列の有界性の関係
複素級数が収束する場合には、その級数のもととなる複素数列や部分和の列はいずれも有界になります。対偶より、複素数列または部分和の列の少なくとも一方が非有界ならば複素級数は発散します。

複素級数の収束可能性と複素数列の収束可能性の関係
複素級数が収束する場合には、もととなる複素数列はゼロへ収束します。対偶より、複素数列がゼロへ収束しない場合、その複素数列の項の複素級数は発散します。

実級数を用いた複素級数の収束判定
複素級数が複素数へ収束することと、実部の実級数と虚部の実級数がともに実数へ収束することは必要十分であるため、実級数の知識を駆使して複素級数の収束可能性を検討できます。

複素数の指数表現(複素指数関数とオイラーの公式)
自然指数関数の定義域を数直線から複素平面へ拡張することにより得られる関数を複素指数関数と呼びます。複素指数関数を用いて複素数を表現する方法を解説します。

複素数列に関するボルツァーノ=ワイエルシュトラスの定理
複素数列に関してもボルツァーノ=ワイエルシュトラスの定理が成り立ちます。つまり、複素数列が有界である場合には、それ自身が収束するかどうかを問わず、収束する部分列が必ず存在します。

部分列を用いた複素数列の収束判定
複素数列が収束することと、その任意の部分列がもとの複素数列の極限と同じ極限へ収束することは必要十分です。以上の事実は、収束する複素数列の極限を特定したり、複素数列が収束しないことを示す上で有用です。

有界な複素数列と収束する複素数列の関係
複素数列のすべての項からなる集合が有界である場合、それを有界な複素数列と呼びます。収束する複素数列は有界である一方で、有界な複素数列は収束するとは限りません。

複素数体上の順序
複素数体は全順序体にはなり得ません。つまり、複素数加法と複素数乗法に加えていかなる二項関係を定義した場合でも、複素数集合は全順序体にはなりません。ただし、複素数集合上に全順序や半順序を定義することはできます。

実数列を用いた複素数列の収束判定
複素数列が収束することと、実部の実数列と虚部の実数列がともに収束することは必要十分であるため、実数列の知識を駆使して複素数列の極限を特定できます。

複素数列の極限(収束する複素数列)
複素数列の項が先に進むにつれてある複素数に限りなく近づく場合には、その複素数列は収束すると言い、その複素数を複素数列の極限と呼びます。イプシロン・エヌ論法を用いて収束列の概念を厳密に定義します。

複素数列の定義と具体例
複素数を順番に並べたものを複素数列と呼びます。複素数列はすべての自然数からなる集合を定義域とし、すべての複素数からなる集合を終集合とする写像として定式化することもできます。

複素平面上の距離(1次元複素ユークリッド空間)
複素平面上の2つの点の間のユークリッド距離を定義した上で、距離の性質について解説します。距離が定義された複素平面を1次元複素ユークリッド空間と呼びます。

複素数の根(係数と変数が複素数である2次方程式の解)
複素数のn乗根を求める方法を解説します。その上で、係数と変数がともに複素数であるような2次方程式の解を求める方法を解説します。

共役複素数(複素共役)
複素数の実部を固定したまま虚部の符号を反転させることにより得られる複素数をもとの複素数の共役複素数や複素共役などと呼びます。共役複素数の性質について解説します。

複素数と実数の関係(虚数単位を用いた複素数の表現)
虚部がゼロであるような複素数を実数と同一視する場合、実数空間は虚数空間の部分体になります。その上で、複素数を虚数単位を用いて表記すれば複素数どうしの演算が容易になります。

複素数の極形式(極表示)
複素平面上の複素数と原点の間の距離を複素数の絶対値と呼び、複素平面の実部と動径のなす角を偏角と呼びます。絶対値と偏角を指定することを通じて複素数を表現する手法を極形式と呼びます。

距離空間上のリプシッツ写像による集合の像
距離空間上に定義されたリプシッツ写像はコンパクト集合をコンパクト集合へ移し、全有界集合を全有界集合へ移し、有界集合を有界集合へ移します。

距離空間上の写像の一様連続性とリプシッツ写像の関係
距離空間もしくはその部分集合上に定義された写像がリプシッツ写像である場合には、その写像は一様連続です。その一方で、一様連続写像はリプシッツ写像であるとは限りません。

点列を用いた距離空間上の全有界集合の判定
距離空間の部分集合が全有界集合であることと、その集合上の任意の点列がコーシー列であるような部分列を持つことは必要十分です。また、距離空間が全有界であることと、その距離空間上の任意の点列がコーシー列であるような部分列を持つことは必要十分です。

距離空間上のリプシッツ写像
距離空間上に定義された写像がリプシッツ写像であることの意味を定義するとともに、写像がリプシッツ写像であること、ないしリプシッツ写像ではないことを判定する方法を解説します。

距離空間上の一様連続写像による集合の像
距離空間上に定義された一様連続写像によるコンパクト集合の像もまたコンパクト集合です。また、一様連続写像による全有界集合の像もまた全有界集合です。

距離空間上の写像の連続性と一様連続性の関係
距離空間もしくはその部分集合上に定義された一様連続写像は連続である一方で、連続写像は一様連続であるとは限りません。ただし、コンパクト集合上に定義された連続写像は一様連続になります。

点列を用いた写像の一様連続性の判定
距離空間上に定義された写像が一様連続であることを点列を用いて判定する方法を解説します。また、一様連続写像はコーシー列をコーシー列へ移すことを示します。

距離空間上の写像の一様連続性(一様連続写像)
距離空間上に定義された写像が一様連続であることの意味を定義するとともに、写像が一様連続であること、ないし一様連続ではないことを判定する方法について解説します。

距離空間上の写像に関する最大値・最小値の定理
距離空間の部分集合上に定義され実数を値としてとる写像が連続であるとともに定義域がコンパクト集合である場合、その写像の最大値と最小値が存在します。