純供給関数の0次同次性
生産者の技術が生産集合\(Y\subset \mathbb{R} ^{N}\)ないし変換関数\(F:\mathbb{R} ^{N}\rightarrow \mathbb{R} \)として表現されているとともに、利潤最大化を目指す生産者の意思決定が供給対応\(Y^{\ast }:\mathbb{R} _{++}^{N}\twoheadrightarrow Y\)として表現されているとともに、\(Y^{\ast }\)は非空値をとるものとします。価格ベクトル\(p\in \mathbb{R} _{++}^{N}\)のもとでの利潤最大化問題の解からなる集合は、\begin{eqnarray*}Y^{\ast }\left( p\right) &=&\left\{ y\in Y\ |\ \forall z\in Y:p\cdot y\geq
p\cdot z\right\} \\
&=&\left\{ y\in \mathbb{R} ^{N}\ |\ F\left( y\right) \leq 0\wedge \forall z\in Y:p\cdot y\geq p\cdot
z\right\}
\end{eqnarray*}です。すべての商品の価格を同じ割合\(\lambda >0\)で増加させたとき、変化後の価格ベクトル\(\lambda p\)のもとでの利潤最大化問題の解からなる集合は、\begin{eqnarray*}Y^{\ast }\left( \lambda p\right) &=&\left\{ y\in Y\ |\ \forall z\in
Y:\lambda p\cdot y\geq \lambda p\cdot z\right\} \\
&=&\left\{ y\in \mathbb{R} ^{N}\ |\ F\left( y\right) \leq 0\wedge \forall z\in Y:\lambda p\cdot y\geq
\lambda p\cdot z\right\}
\end{eqnarray*}となりますが、実際には、\begin{equation*}
Y^{\ast }\left( \lambda p\right) =Y^{\ast }\left( p\right)
\end{equation*}という関係が成り立ちます(演習問題)。つまり、すべての商品の価格を同じ割合\(\lambda \)で変化させる場合、その変化の前後において、利潤最大化問題の解からなる集合は変化しません。
以上の議論は任意の\(p\)と\(\lambda \)について成立するため、供給対応\(Y^{\ast }\)について、\begin{equation*}\forall p\in \mathbb{R} _{++}^{N},\ \forall \lambda \in \mathbb{R} _{++}:Y^{\ast }\left( \lambda p\right) =Y^{\ast }\left( p\right)
\end{equation*}が成り立ちます。つまり、供給対応\(Y^{\ast }\)は価格ベクトル\(p\)に関して0次同次であるということです。
\end{equation*}が成り立つ。
純供給関数\(y^{\ast }:\mathbb{R} _{++}^{N}\twoheadrightarrow Y\)が存在する場合には、これと純供給対応\(Y^{\ast }\)との間に、\begin{equation*}\forall p\in \mathbb{R} _{++}^{N}:Y^{\ast }\left( p\right) =\left\{ y^{\ast }\left( p\right)
\right\}
\end{equation*}という関係が成り立ちます。先と同様の議論を繰り返すことにより、純供給関数が価格ベクトルに関して0次同次であることを示すことができます。
\end{equation*}が成り立つ。
\begin{array}{c}
y_{1}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) \\
y_{2}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right)
\end{array}\right) =\left(
\begin{array}{c}
-\frac{p_{2}^{2}}{2p_{1}^{2}} \\
\frac{p_{2}}{p_{1}}\end{array}\right) \quad \cdots (1)
\end{equation}を定めるものとします。\(\lambda >0\)を任意に選んだとき、\begin{eqnarray*}y^{\ast }\left( \lambda p_{1},\lambda p_{2}\right) &=&\left(
\begin{array}{c}
y_{1}^{\ast }\left( \lambda p_{1},\lambda p_{2}\right) \\
y_{2}^{\ast }\left( \lambda p_{1},\lambda p_{2}\right)
\end{array}\right) \\
&=&\left(
\begin{array}{c}
-\frac{\left( \lambda p_{2}\right) ^{2}}{2\left( \lambda p_{1}\right) ^{2}}
\\
\frac{\lambda p_{2}}{\lambda p_{1}}\end{array}\right) \quad \because \left( 1\right) \\
&=&\left(
\begin{array}{c}
-\frac{p_{2}^{2}}{2p_{1}^{2}} \\
\frac{p_{2}}{p_{1}}\end{array}\right) \quad \because \lambda >0 \\
&=&y^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) \quad \because \left( 1\right)
\end{eqnarray*}となるため、純供給関数\(y^{\ast }\)は0次同次性を満たしています。
純供給関数の0次同次性とニュメレール
純供給対応の0次同次性は、貨幣単位の付け替えが経済学的には意味を持たないことを示唆しています。貨幣単位が「円」である場合、価格ベクトル\(p\)のもとでの利潤最大化問題の解からなる集合は\(Y^{\ast }\left( p\right) \)です。ここで、貨幣単位を「銭」に変換すると先の価格ベクトルは\(100p\)と表現され、そこでの利潤最大化問題の解からなる集合は\(Y^{\ast }\left( 100p\right) \)となります。ただし、純供給対応\(Y^{\ast }\)は\(p\)に関して\(0\)次同次であるため、このとき、\begin{equation*}Y^{\ast }\left( 100p\right) =Y^{\ast }\left( p\right)
\end{equation*}が成り立ちます。つまり、貨幣単位を「円」から「銭」に変更しても利潤最大化問題の解は変化しません。通貨を「円」から「ドル」や「ユーロ」などに変更する場合にも同様の議論が成り立ちます。つまり、純供給対応が価格ベクトルに関して0次同次である場合には、貨幣の種類や単位を変更しても利潤最大化問題の解は変化しません。
オイラーの定理
純供給関数\(y^{\ast }:\mathbb{R} _{++}^{N}\rightarrow Y\)が存在する状況を想定します。先に示したように純供給関数\(y^{\ast }\)は価格ベクトル\(p\)に関して0次同次性を満たすため、価格ベクトル\(p\in \mathbb{R} _{++}^{N}\)および正の実数\(\lambda >0\)をそれぞれ任意に選ぶと、\begin{equation*}y^{\ast }\left( \lambda p\right) =y^{\ast }\left( p\right)
\end{equation*}という関係が成り立ちます。言い換えると、それぞれの商品\(n\ \left( =1,\cdots ,N\right) \)の純供給関数\(y_{n}^{\ast }:\mathbb{R} _{++}^{N}\rightarrow \mathbb{R} \)についても、\begin{equation*}y_{n}^{\ast }\left( \lambda p\right) =y_{n}^{\ast }\left( p\right)
\end{equation*}が成り立つということです。点\(p\in \mathbb{R} _{++}^{N}\)を任意に選んだ上で固定し、それぞれの\(\lambda \in \mathbb{R} _{++}\)に対して、\begin{equation*}v\left( \lambda \right) =\lambda p
\end{equation*}を値として定める1変数のベクトル値関数\(v:\mathbb{R} _{++}\rightarrow \mathbb{R} _{++}^{N}\)を定義します。その上で、それぞれの\(\lambda \in \mathbb{R} _{++}\)に対して、\begin{equation}\left( y_{n}^{\ast }\circ v\right) \left( \lambda \right) =y_{n}^{\ast
}\left( \lambda p\right) \quad \cdots (1)
\end{equation}を値として定める1変数の合成関数\(y_{n}^{\ast }\circ v:\mathbb{R} _{++}\rightarrow \mathbb{R}\)を定義します。ベクトル値関数である\(v\)は明らかに微分可能です。したがって多変数関数である純供給関数\(y_{n}^{\ast }\)が点\(\lambda p\)において全微分可能であるならば、1変数のベクトル値関数と多変数関数の合成関数に関する微分公式を利用できます。以上を踏まえた上で\(\left(1\right) \)の両辺を\(\lambda \)を微分し、それを\(\lambda =1\)で評価することにより、\begin{equation*}\sum_{i=1}^{N}\left[ \frac{\partial y_{n}^{\ast }\left( p\right) }{\partial
p_{i}}\cdot p_{i}\right] =0
\end{equation*}を得ます(演習問題)。同様の議論は他の任意の商品についても成立します。これをオイラーの定理(Euler’s Theorem)と呼びます。
商品\(n\ \left( =1,\cdots ,N\right) \)の純供給関数\(y_{n}^{\ast }:\mathbb{R} _{++}^{N}\rightarrow \mathbb{R} \)が全微分可能であるならば、任意の\(p\in \mathbb{R} _{++}^{N}\)において、\begin{equation*}\sum_{i=1}^{N}\left[ \frac{\partial y_{n}^{\ast }\left( p\right) }{\partial
p_{i}}\cdot p_{i}\right] =0
\end{equation*}が成り立つ。
p_{1}+\frac{\partial y_{1}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) }{\partial p_{2}}\cdot p_{2} &=&0 \\
\frac{\partial y_{2}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) }{\partial p_{1}}\cdot
p_{1}+\frac{\partial y_{2}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) }{\partial p_{2}}\cdot p_{2} &=&0
\end{eqnarray*}がともに成り立ちます。
\begin{array}{c}
y_{1}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) \\
y_{2}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right)
\end{array}\right) =\left(
\begin{array}{c}
-\frac{p_{2}^{2}}{2p_{1}^{2}} \\
\frac{p_{2}}{p_{1}}\end{array}\right) \quad \cdots (1)
\end{equation}を定めるものとします。それぞれの商品の純供給関数\(y_{1}^{\ast },y_{2}^{\ast }\)は多変数の有理関数であるため全微分可能です。\(\left( p_{1},p_{2}\right) \in \mathbb{R} _{++}^{2}\)を任意に選びます。すると商品\(1\)について、\begin{eqnarray*}&&\frac{y_{1}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) }{\partial p_{1}}\cdot p_{1}+\frac{y_{1}^{\ast }\left( p_{1},p_{2}\right) }{\partial p_{2}}\cdot p_{2} \\
&=&\left[ \frac{\partial }{\partial p_{1}}\left( -\frac{p_{2}^{2}}{2p_{1}^{2}}\right) \right] \cdot p_{1}+\left[ \frac{\partial }{\partial p_{2}}\left( -\frac{p_{2}^{2}}{2p_{1}^{2}}\right) \right] \cdot p_{2}\quad \because \left(
1\right) \\
&=&\left( \frac{p_{2}^{2}}{p_{1}^{3}}\right) \cdot p_{1}+\left( -\frac{2p_{2}}{2p_{1}^{2}}\right) \cdot p_{2} \\
&=&\frac{p_{2}^{2}}{p_{1}^{2}}-\frac{p_{2}^{2}}{p_{1}^{2}} \\
&=&0
\end{eqnarray*}となるため、たしかにオイラーの定理が成立しています。商品\(2\)についても同様です。
先の命題より、商品\(n\)の純供給関数\(y_{n}^{\ast }\)が全微分可能である場合には、\(p\)を任意に選んだとき、\begin{equation*}\sum_{i=1}^{N}\left[ \frac{\partial y_{n}^{\ast }\left( p\right) }{\partial
p_{i}}\cdot p_{i}\right] =0
\end{equation*}が成り立ちます。以上の事実は何を示唆しているのでしょうか。\(\frac{\partial y_{n}^{\ast }\left( p\right) }{\partial p_{i}}\)は商品\(i\)の価格\(p_{i}\)が限界的に変化したときの商品\(n\)の純供給の変化であるため、これと商品\(i\)の価格\(p_{i}\)の積である\begin{equation*}\frac{\partial y_{n}^{\ast }\left( p\right) }{\partial p_{i}}\cdot p_{i}
\end{equation*}は商品\(i\)の価格が\(p_{i}\)だけ変化したときの商品\(n\)の純供給の変化を表します。したがって、商品\(n\)に関するオイラーの定理\begin{equation*}\sum_{i=1}^{N}\left[ \frac{\partial y_{n}^{\ast }\left( p\right) }{\partial
p_{i}}\cdot p_{i}\right] =0
\end{equation*}は、任意の\(p\)を出発点としたときに、それぞれの商品\(i\)の価格を\(p_{i}\)だけ変化させても、商品\(n\)の純供給は変化しないことを意味します。同様の議論は任意の商品について成立するため、結局、任意の\(p\)を出発点としたときに、それぞれの商品\(i\)の価格を\(p_{i}\)だけ変化させても純供給は変化しません。
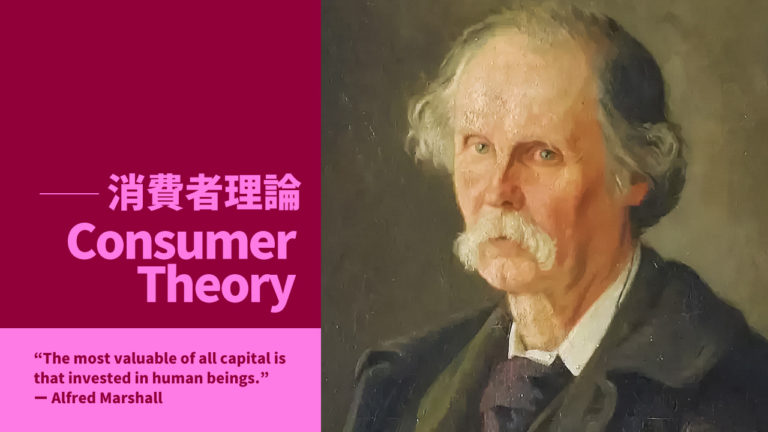
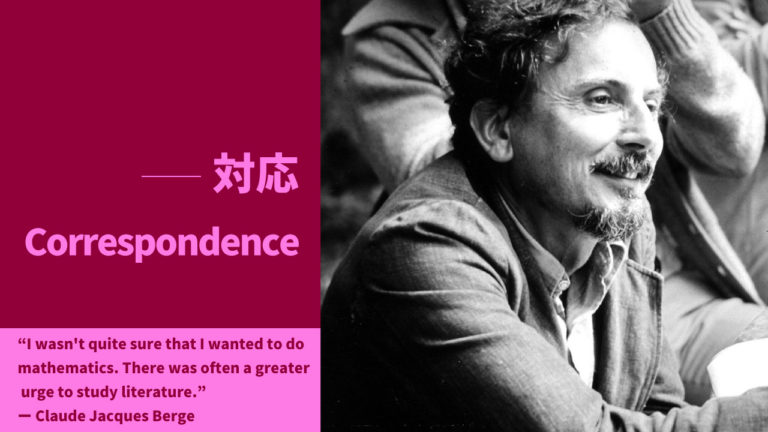
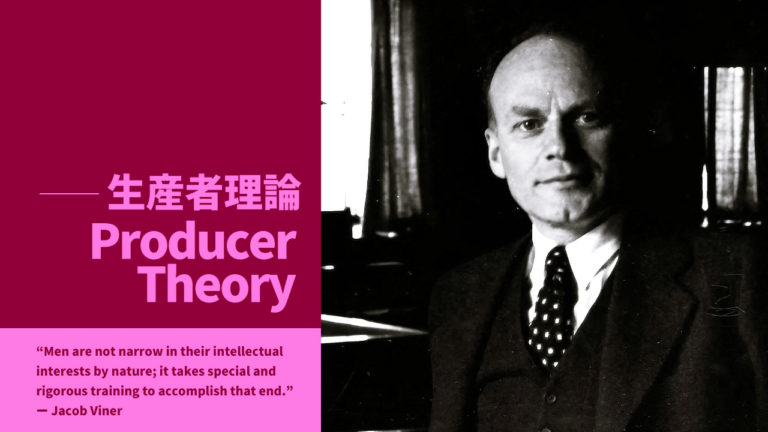
プレミアム会員専用コンテンツです
【ログイン】【会員登録】