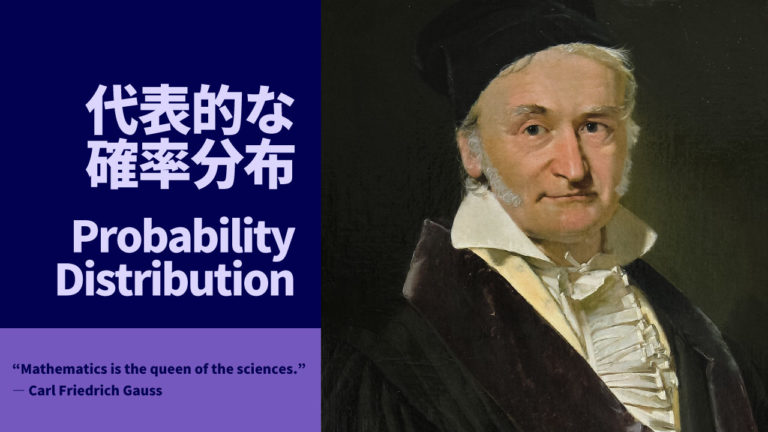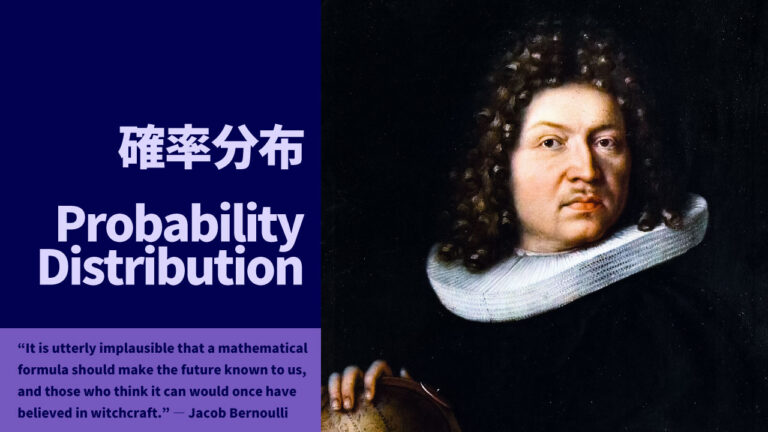
連続型確率変数の条件付き分散・条件付き標準偏差
2つの連続型確率変数の一方が特定の値をとるという条件のもとでの他方の確率変数の分散を評価する際には条件付き分散と呼ばれる概念を利用します。
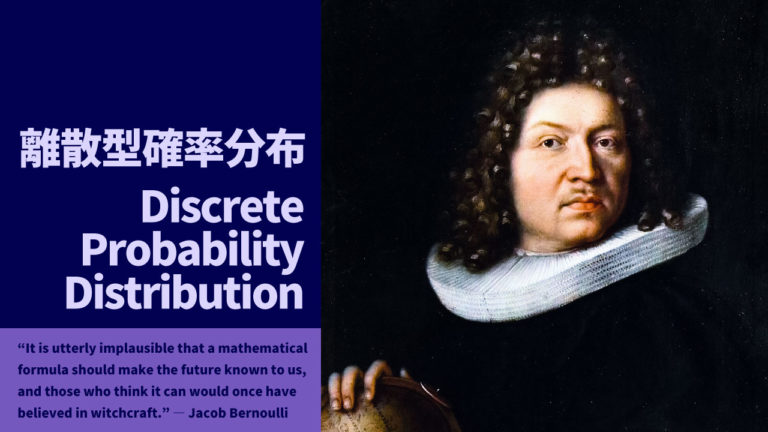
離散型確率変数の条件付き分散・条件付き標準偏差
2つの離散型確率変数の一方が特定の値をとるという条件のもとでの他方の確率変数の分散を評価する際には条件付き分散と呼ばれる概念を利用します。

逆双曲線正接関数(arctanh関数)の定義と具体例
双曲線正接関数の逆関数を逆双曲線正接関数(アークハイパボリックタンジェント関数)と呼びます。逆双曲線正接関数を定義するとともに、その基本的な性質について解説します。

逆双曲線余弦関数(arccosh関数)の定義と具体例
双曲線余弦関数の逆関数を逆双曲線余弦関数(アークハイパボリックコサイン関数)と呼びます。逆双曲線余弦関数を定義するとともに、その基本的な性質について解説します。

逆双曲線正弦関数(arcsinh関数)の定義と具体例
双曲線正弦関数の逆関数を逆双曲線正弦関数(アークハイパボリックサイン関数)と呼びます。逆双曲線正弦関数を定義するとともに、その基本的な性質について解説します。
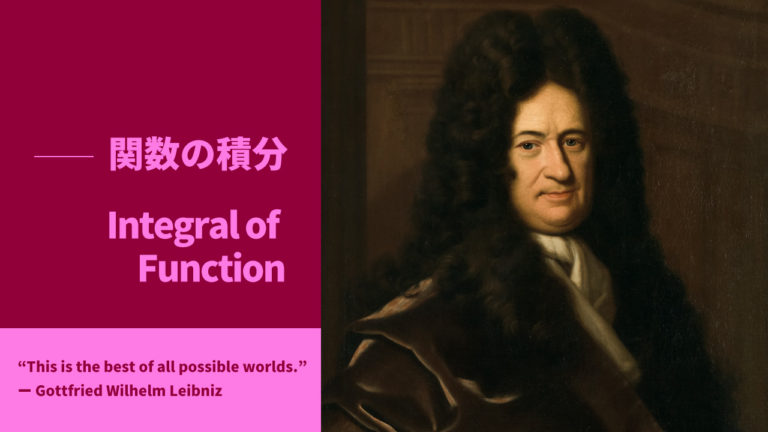
積分を用いたテイラーの定理の表現(積分型の剰余項)
テイラーの定理(マクローリンの定理)において剰余項を積分を用いて表現するとともに、積分を用いてテイラー展開(マクローリン展開)可能であることを判定する方法について解説します。
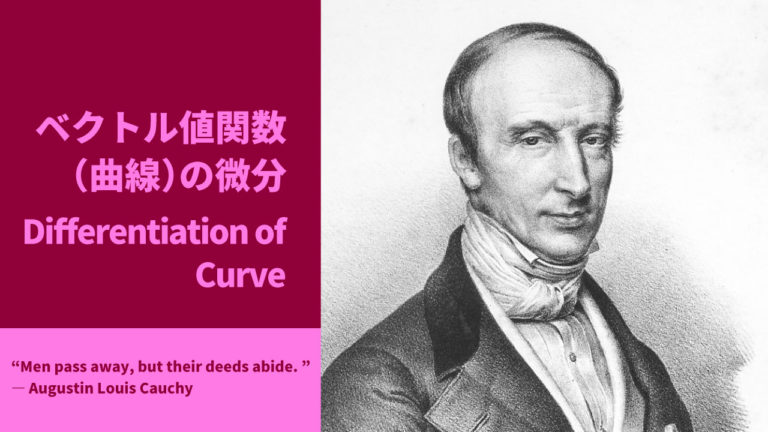
ベクトル値関数の高階微分
ベクトル値関数の導関数が微分可能である場合には導関数の導関数が得られますがこれを2階の導関数と呼びます。同様に、3階の導関数、4階の導関数なども定義可能です。これらを高階の導関数と呼びます。
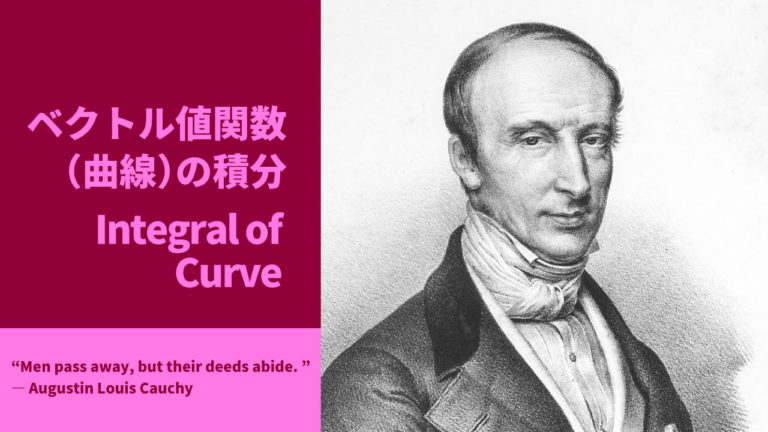
空間上を動く点の位置・変位・速度・加速度・速さ
空間上を動く点の位置・変位・速度・加速度などの概念を定義するとともに、それらの概念の関係をベクトル値関数の微分と積分を用いて表現します。
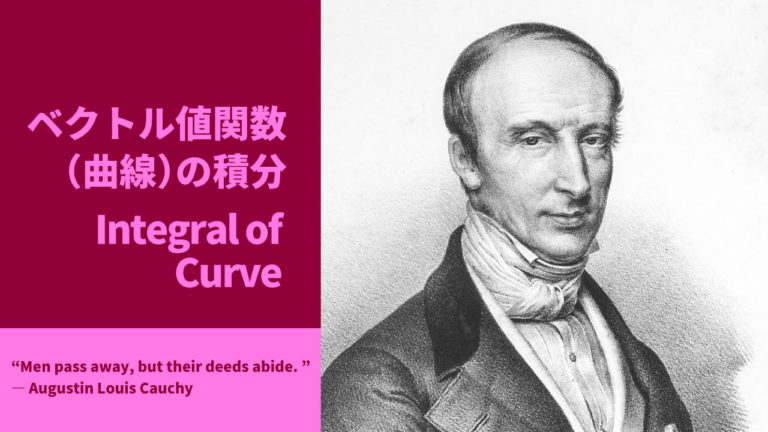
平面上を動く点の位置・変位・速度・加速度・速さ
平面上を動く点の位置・変位・速度・加速度などの概念を定義するとともに、それらの概念の関係をベクトル値関数の微分と積分を用いて表現します。
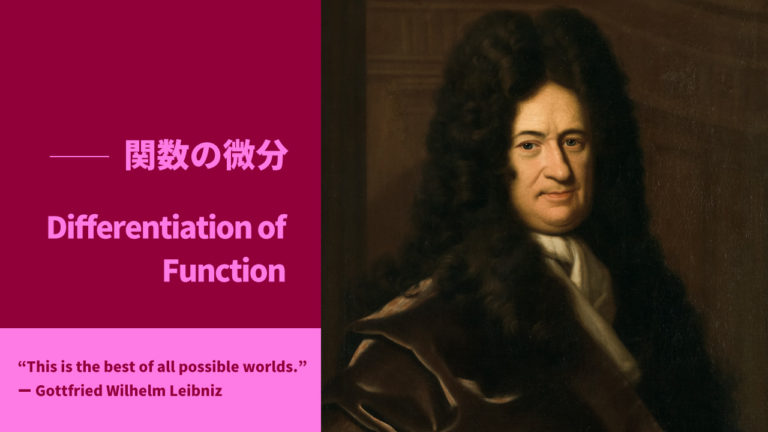
ニュートン法を用いた近似値計算
ニュートン法とは方程式の近似解を求めるためのアルゴリズムです。ニュートン法の手順を解説するとともに、ニュートン法が有効であるための条件およびその根拠について解説します。
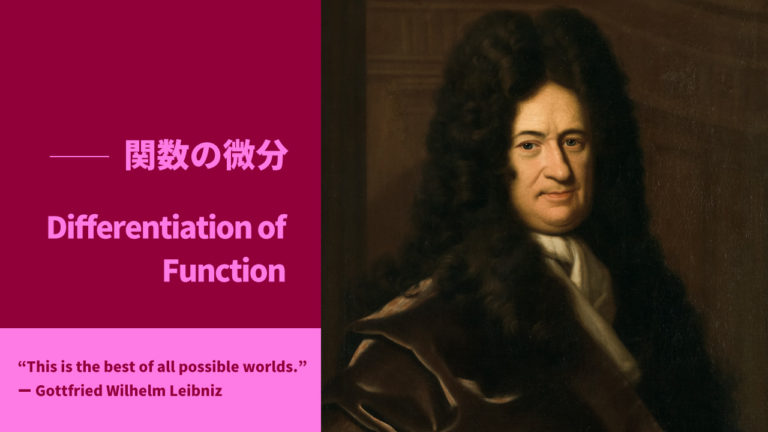
高階微分や漸近展開を用いた1変数関数の極値判定
高階微分や漸近展開を用いることにより、ある点が関数の極大点や極小点であること・ないことを判定する方法について解説します。これは局所最適化のための十分条件の一般化です。
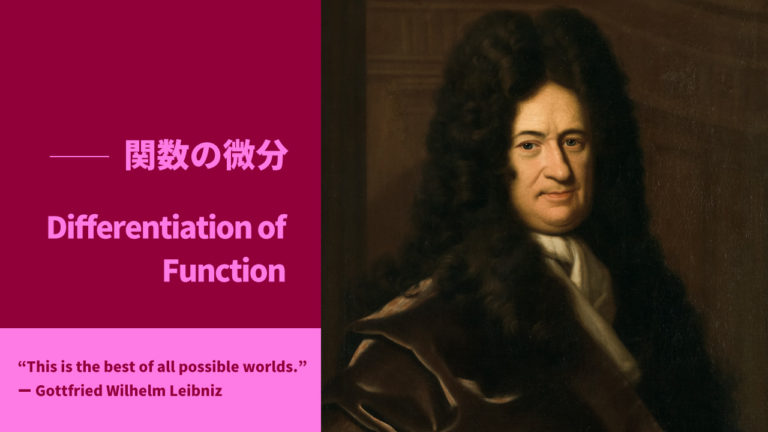
1変数関数の局所最適解(極大値・極小値)
関数の値を最大化するような点が定義域上に存在しない場合でも、変数がとり得る値を限定することにより、その範囲内において関数の値を最大化するような点が存在する状況は起こり得ます。そのような点を極大点や局所的最大点と呼びます。また、関数が極大点に対して定める値を極大値や大域的最大値と呼びます。最小化問題についても同様です。
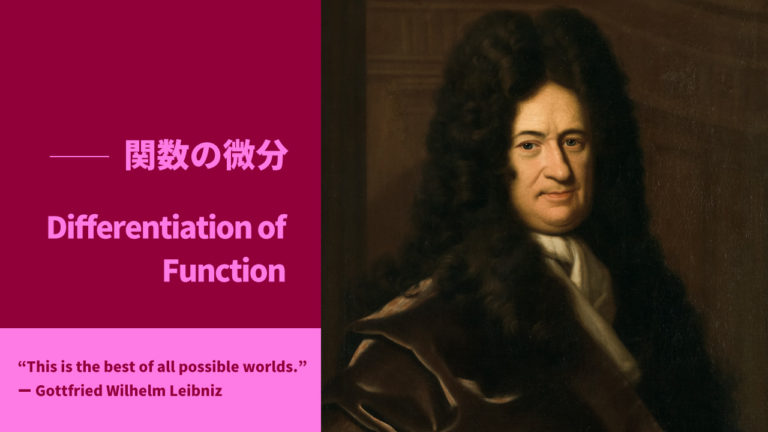
1変数関数の大域的最適解(最大値・最小値)
関数の値を最大化するような点が定義域上に存在する場合、そのような点を最大点や大域的最大点と呼びます。また、関数が最大点に対して定める値を最大値や大域的最大値と呼びます。最小化についても同様です。
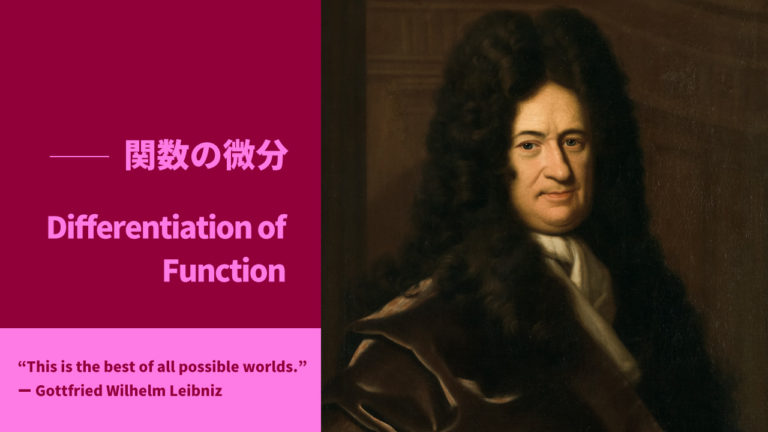
実数ベキ関数の高階微分とテイラー展開(マクローリン展開)
実数ベキ関数にはテイラーの定理を適用できる一方、点0において定義されていないためマクローリンの定理を適用できません。関数 (x+1)^p は点0において定義されており、マクローリン展開可能です。
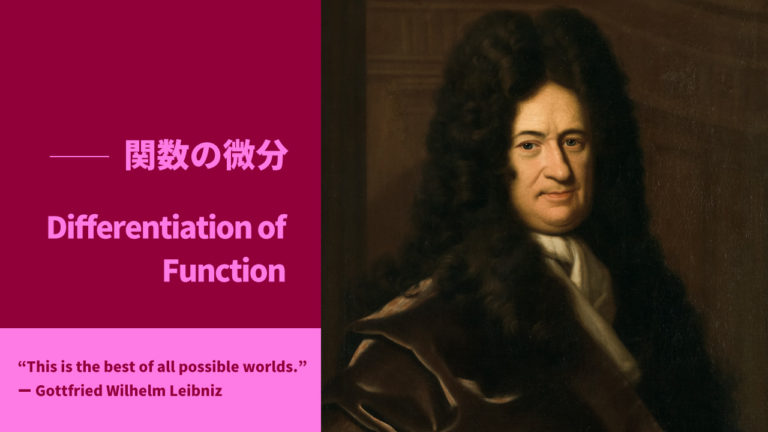
テイラー展開や漸近展開を用いた不定形の極限の解消
与えられた関数の極限が不定形である場合でも、その関数を構成する関数の中にテイラー展開ないし漸近展開可能であるものが存在する場合、テイラー展開ないし漸近展開した上で極限をとれば、不定形を解消できることがあります。
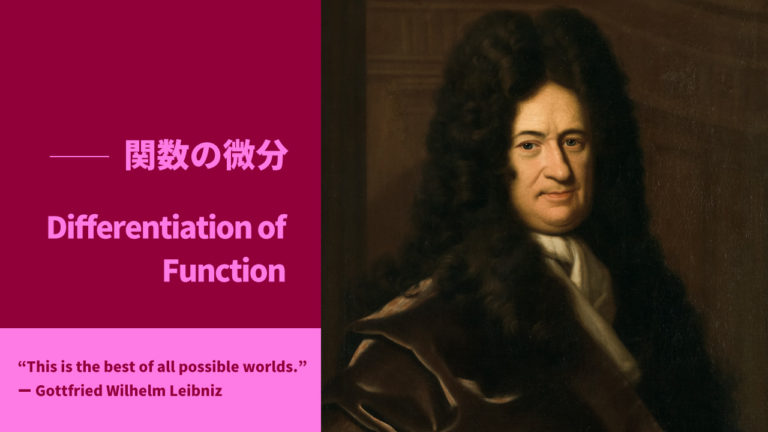
テイラーの定理の一般化(ロッシュ-シュレミルヒの剰余項)
テイラーの定理に関連して、ラグランジュの剰余項を一般化したロッシュ-シュレミルヒの剰余項と、その特殊例であるコーシーの剰余項について解説します。
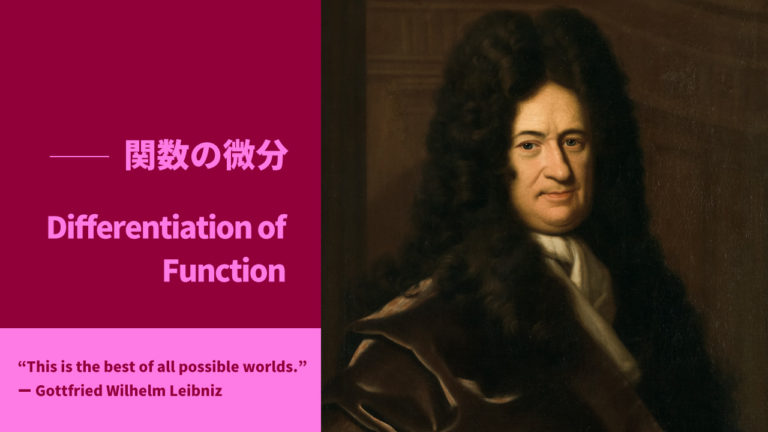
∞/∞型のロピタルの定理(微分を用いた不定形の極限の解消)
2つの関数の商の極限が∞/∞型の不定形である場合でも、一定の条件を満たす場合には、微分を用いてその極限を特定できます。
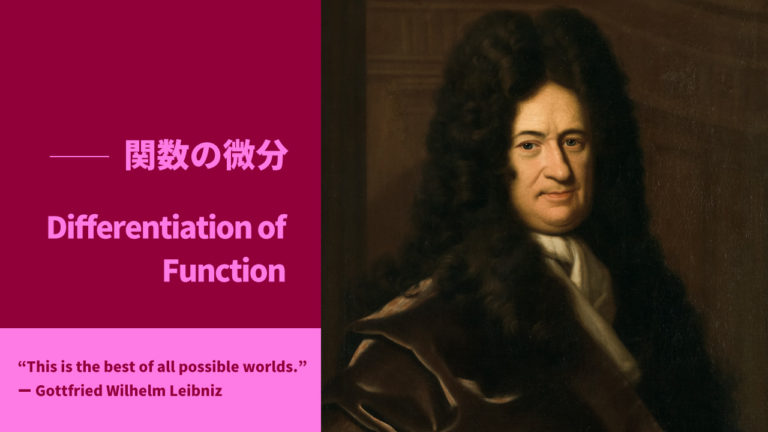
0/0型のロピタルの定理(微分を用いた不定形の極限の解消)
2つの関数の商の極限が0/0型の不定形である場合でも、一定の条件を満たす場合には、微分を用いてその極限を特定できます。
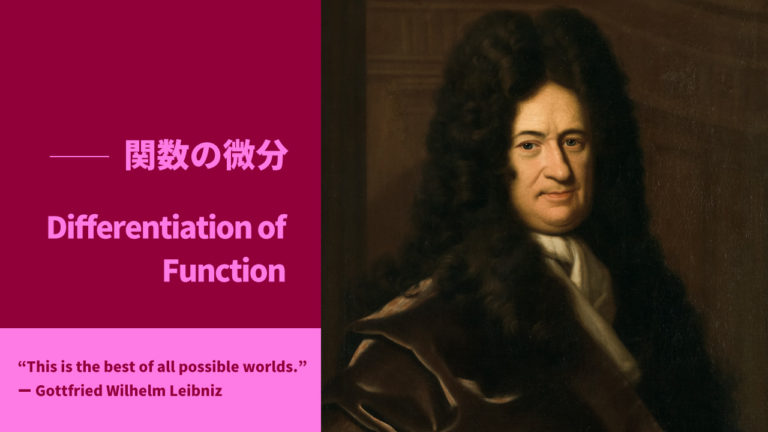
対数微分法
与えられた関数が複数の関数の積の形である場合、商の形である場合、累乗の形である場合などには、その関数の自然対数をとってから微分することにより、導関数を容易に求めることができます。このような手法を対数微分法と呼びます。
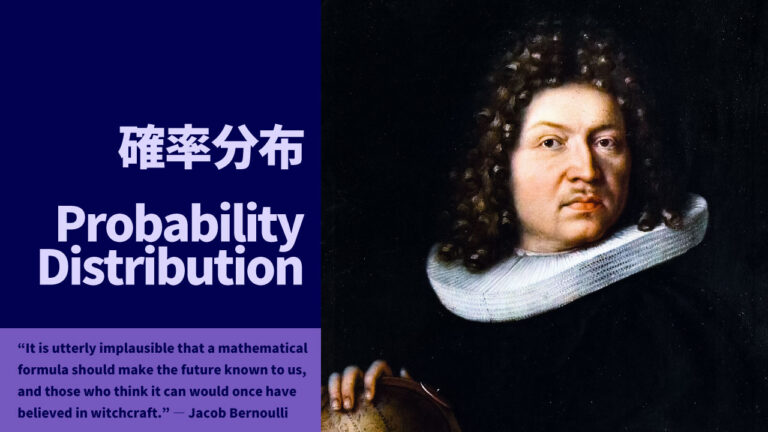
連続型確率変数の条件付き分布関数
2つの連続型確率変数の一方が特定の値をとるという条件のもとでの他方の確率変数の確率分布を条件付き確率分布と呼びます。条件付き確率分布は条件付き分布関数によって表現することもできます。
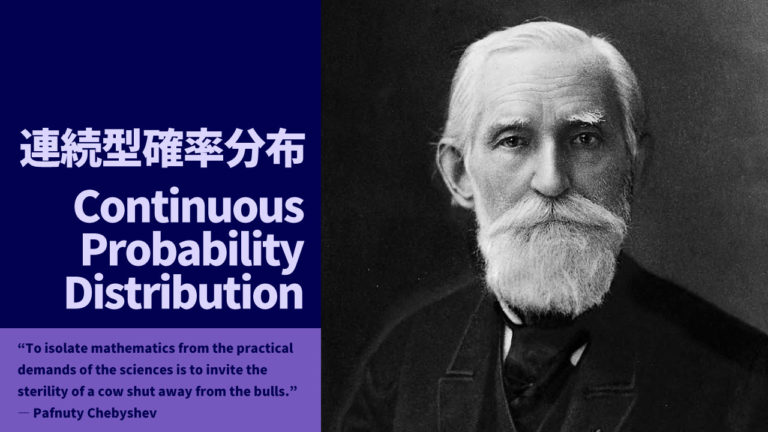
2つの連続型確率変数の相関係数
2つの連続型確率変数の値の分布の関連性を表現する指標として共分散と呼ばれる指標を定義しましたが、共分散の水準は確率変数の値の単位に依存して変化してしまいます。このような欠点を克服する指標が相関係数です。
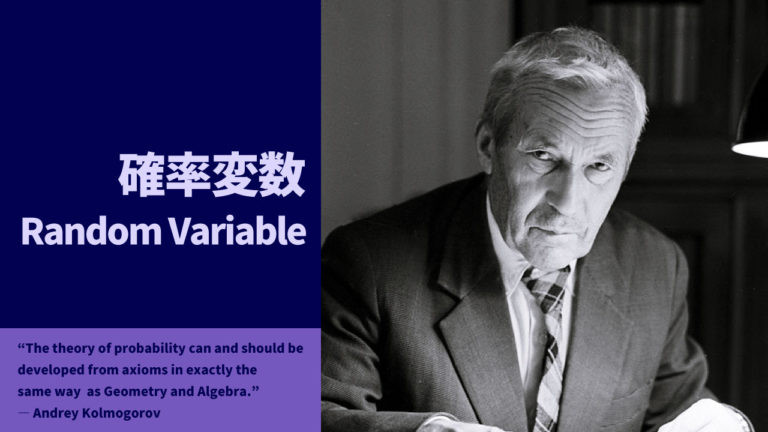
確率ベクトルと連続なベクトル値関数の合成関数は確率ベクトル
確率ベクトルと多変数ボレル可測ベクトル値関数の合成関数は確率ベクトルです。連続関数はボレル可測関数であるため、確率ベクトルと多変数の連続なベクトル値関数の合成関数もまた確率ベクトルです。

2つの事象の条件付き独立性
事象Cが起きているという前提のもと、事象Bが起こるかどうかが事象Aが起こる確率に影響を与えない場合、これらの事象はCのもとで条件付き独立であると言います。

モンティ・ホール問題(事前確率と事後確率)
モンティ・ホール問題とその解法について解説するとともに、この問題の核心が、追加的な情報を活用した事前確率の事後確率への更新にあることを説明します。