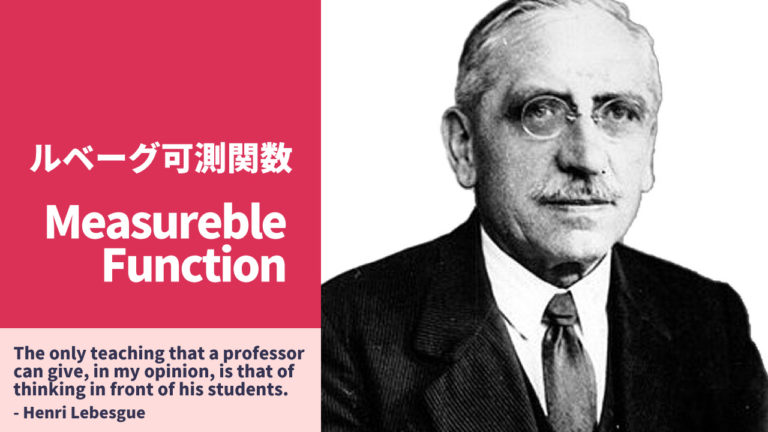
拡大実数値ボレル可測関数の定義
ボレル集合上に定義された拡大実数値関数によるボレル集合の逆像がボレル可測であることが保証される場合、そのような関数はボレル可測であると言います。
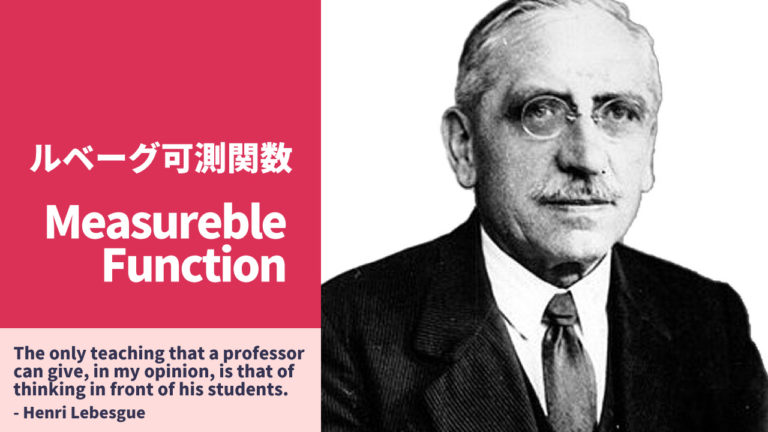
ボレル集合上に定義された拡大実数値関数によるボレル集合の逆像がボレル可測であることが保証される場合、そのような関数はボレル可測であると言います。

拡大実数系上の開集合系から生成される最小のσ-代数をボレル集合族と呼びます。ボレル集合族は拡大実数系上の近傍系や特定の近傍系から生成することもできます。
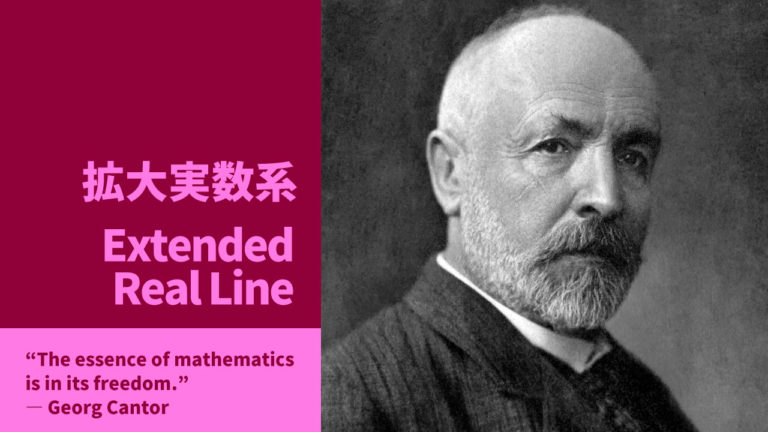
拡大実数系においては正の無限大と負の無限大が体系の中に含まれているため、有限な実数だけでなく、正の無限大や負の無限大もまた拡大実数列の極限の候補になります。
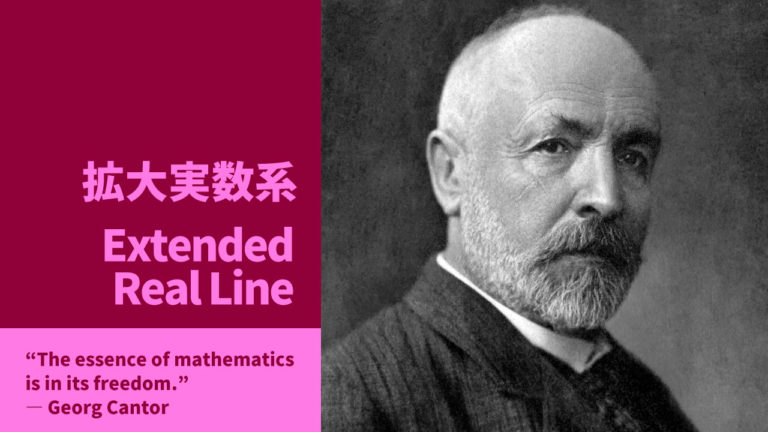
拡大実数系の部分集合Aに属するそれぞれの点に対して、その点を中心とする近傍の中にAの部分集合であるようなものが存在する場合、Aを拡大実数系上の開集合と呼びます。
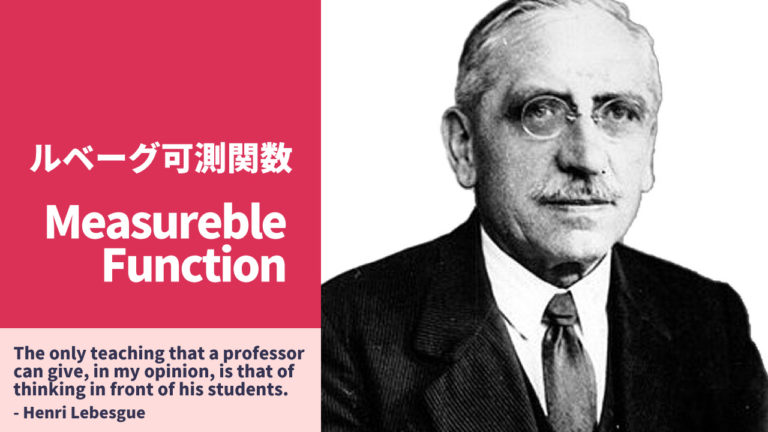
ルベーグ集合上に定義された拡大実数値関数によるボレル集合の逆像がルベーグ可測であることが保証される場合、そのような関数はルベーグ可測であると言います。
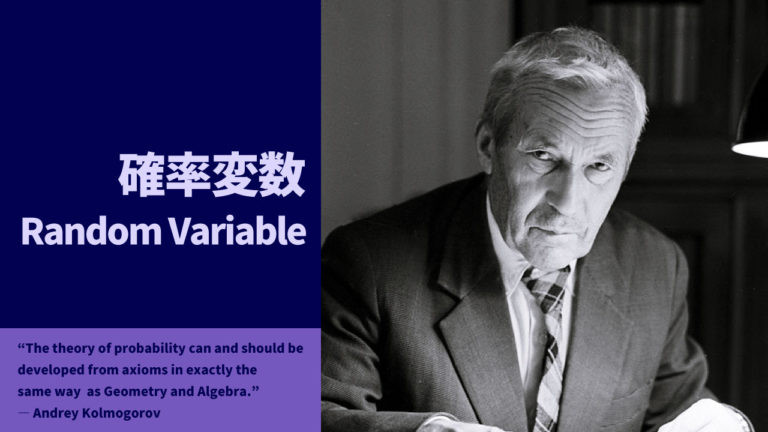
確率変数列の実現値の上極限や下極限や極限を与える写像は確率変数です。また、拡大実数値確率変数の実現値の上極限や下極限や極限を与える写像もまた拡大実数値確率変数です。
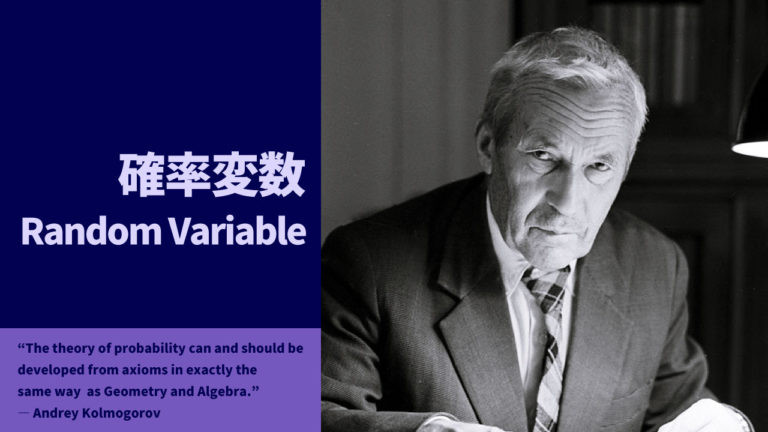
確率変数族の実現値の上限や下限を与える写像は拡大実数値確率変数です。特に、すべての確率変数族の要素であるすべての確率変数が有界である場合、それらの実現値の上限や下限を与える写像は確率変数です。
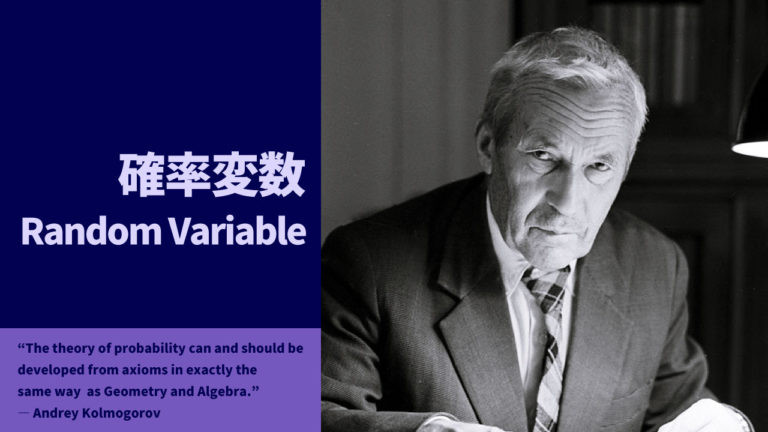
有限個の確率変数の実現値の最大値や最小値を値として定める写像は確率変数です。また、有限個の拡大実数値確率変数の実現値の最大値や最小値を値として定める写像は拡大実数値確率変数です。
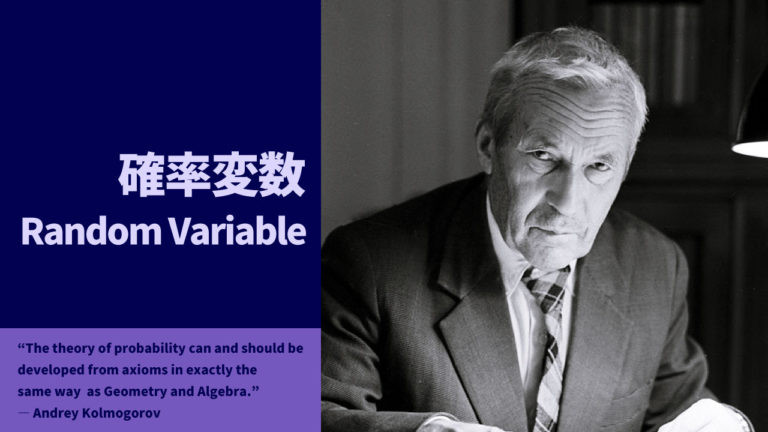
確率変数どうしの商が定義可能であるならば、それもまた確率変数になります。また、拡大実数値確率変数どうしの商が定義可能である場合には、それもまた拡大実数値確率変数になります。
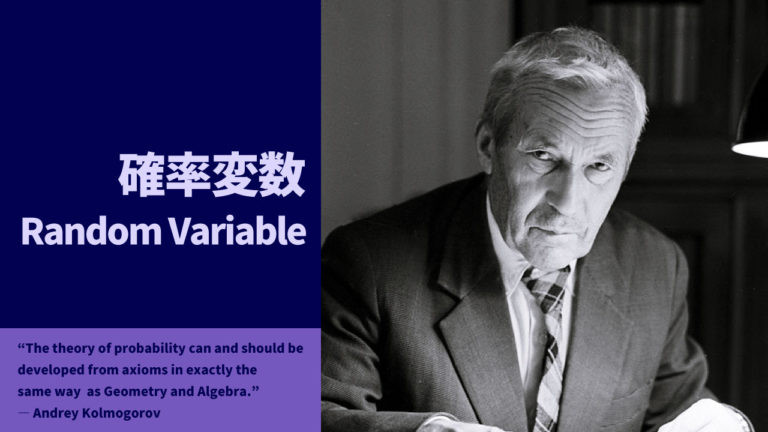
確率変数どうしの積として定義される写像もまた確率変数になることが保証されます。また、拡大実数値確率変数どうしの積が定義可能である場合には、それもまた拡大実数値確率変数になります。

確率変数どうしの差として定義される写像もまた確率変数になることが保証されます。また、拡大実数値確率変数どうしの差が定義可能である場合には、それもまた拡大実数値確率変数になります。
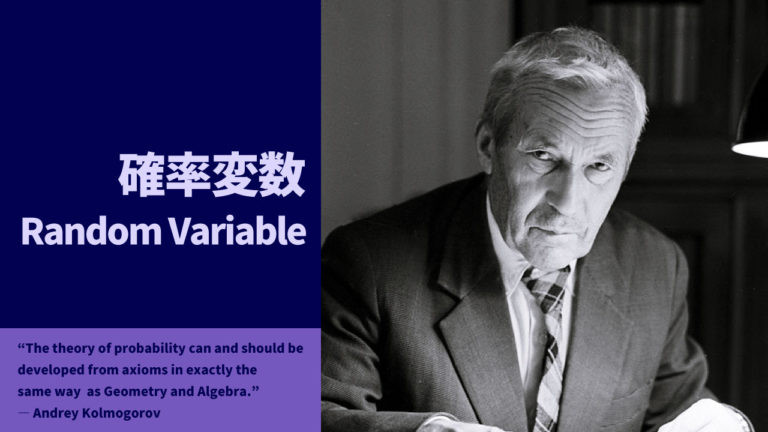
確率変数どうしの和として定義される写像もまた確率変数になることが保証されます。また、拡大実数値確率変数どうしの和が定義可能である場合には、それもまた拡大実数値確率変数になります。
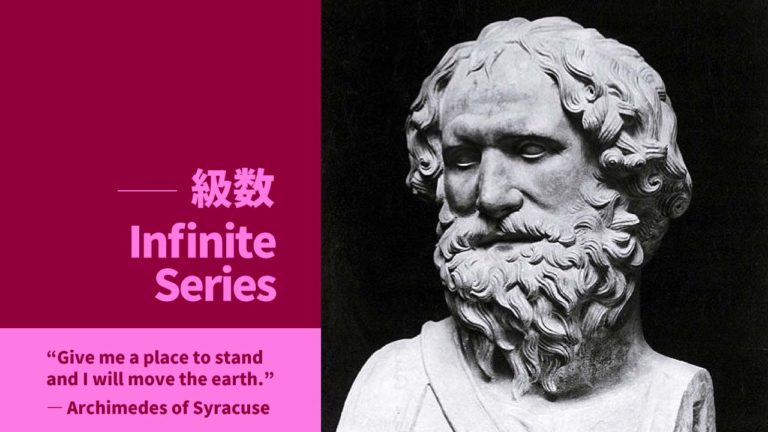
与えられた級数の絶対値級数が収束する場合、もとの級数は絶対収束すると言います。絶対収束する級数は必ず収束する一方で、収束する級数は絶対収束するとは限りません。

可算事象族の要素である無限個の事象の影響を受ける一方で、有限個の事象の影響を受けない事象を末尾事象と呼びます。可算事象族が独立である場合、その任意の末尾事象の確率は0または1のどちらか一方に定まります。これをコルモゴロフの0-1の法則と呼びます。

有限個の事象族から選ばれた事象どうしが独立になることが保証される場合、それらの事象族は独立であると言います。有限個の事象族が独立であり、各々が積事象について閉じているとともに全体事象を要素として持つ場合、それらから生成されるσ-代数もまた独立になることが保証されます。

2つの事象族から選ばれた事象どうしが独立になることが保証される場合、それらの事象族は独立であると言います。2つの事象族が独立であり、なおかつ各々が積事象について閉じている場合、それらから生成されるσ-代数もまた独立になることが保証されます。

確率変数列が独立であるとともに個々の確率変数の期待値がゼロであり、なおかつ分散の総和が有限である場合、その確率変数列のもとでの実現値に関する無限級数はほとんど確実に収束します。これをヒンチン=コルモゴロフの収束定理と呼びます。

有限かつ独立な確率変数列を構成する個々の確率変数の期待値がゼロであるとともに分散が有限である場合、その確率変数列の部分和として定義される確率変数がある値以上の値をとる確率の上限を特定できます。コルモゴロフの不等式はチェビシェフの不等式の一般化です。

確率収束する確率変数列は分布収束する一方で、分布収束する確率変数列は確率収束するとは限りません。ただし、分布収束する確率変数列の確率極限が定数関数である場合、その確率変数列は分布収束します。

関数変数列を構成する確率変数の分布関数の形状が何らかの確率変数の分布関数の形状へ限りなく近づく場合、その確率変数列はその確率変数へ分布収束(法則収束)すると言います。

数列のすべての項が正の実数である場合、隣り合う2つの項の比を項として持つ新たな数列を定義し、その数列の極限を観察することにより、もとの数列の収束・発散を判定できます。

可算個の独立な事象の確率の総和が無限大である場合、それらの事象の上極限の確率は1になるとともに、それらの事象の余事象の下極限の確率は0になります。これをボレル・カンテリの第2補題と呼びます。

可算個の事象が与えられたとき、そこから有限個の事象を任意に選んだ場合にそれらが独立であるならば、もとの可算個の事象は独立であると言います。

可算個の事象の確率の総和が有限な実数である場合、それらの事象の上極限の確率は0になるとともに、それらの事象の余事象の下極限の確率は1になります。これをボレル・カンテリの第1補題と呼びます。
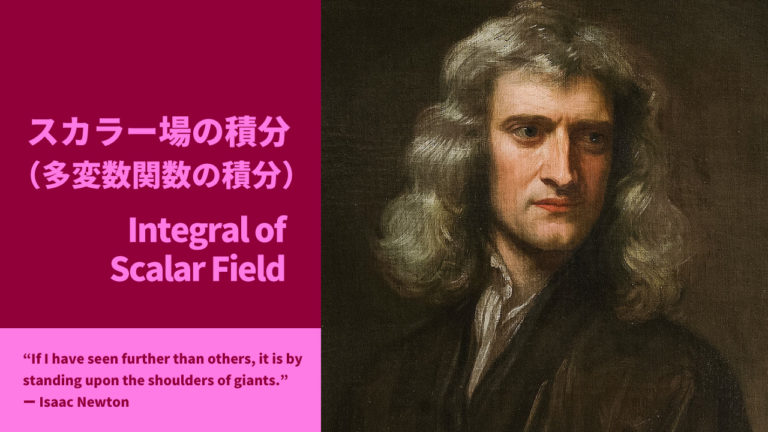
n次元空間上に存在する有界かつ閉な直方体領域上に定義された2つの多変数関数が多重リーマン積分可能である場合、それらの和として定義される多変数関数もまた多重リーマン積分可能です。
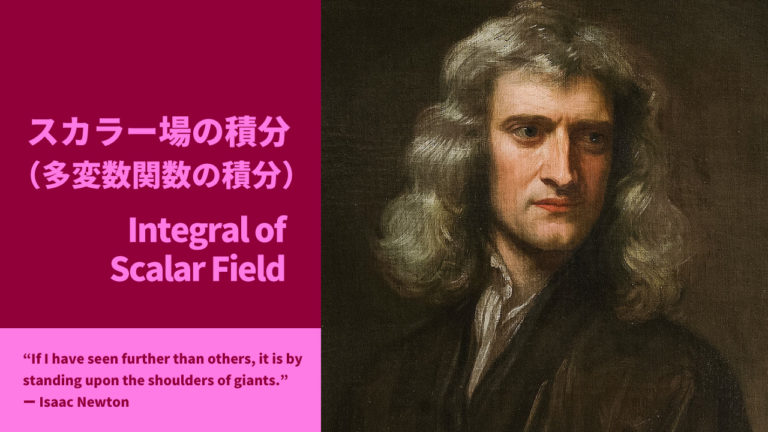
n次元空間上に存在する有界かつ閉な直方体領域上に定義された多変数関数が多重リーマン積分可能であることと、その関数がすべての小直方体領域において多重リーマン積分可能であることは必要十分です。
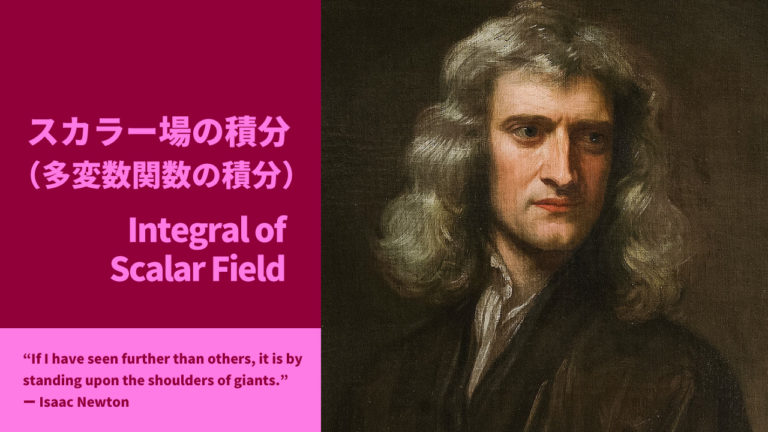
n次元空間上に存在する有界かつ閉な直方体領域上に定義された多変数関数が多重リーマン積分可能である場合、その関数の定数倍として定義される多変数関数もまた多重リーマン積分可能です。
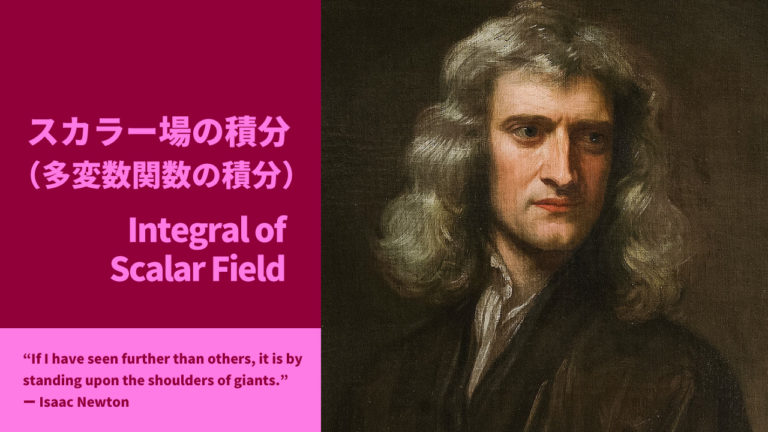
n次元空間上に存在する有界かつ閉な直方体領域上に定義された多変数関数が連続関数である場合、その関数は領域上で多重リーマン積分可能です。

一様連続な多変数関数は連続である一方、連続関数は一様連続であるとは限りません。ただ、連続関数の定義域がコンパクト集合である場合、その関数が一様連続であることが保証されます。

多変数関数がリプシッツ関数であることの意味を定義します。リプシッツ関数は一様連続ですが、一様連続関数はリプシッツ関数であるとは限りません。
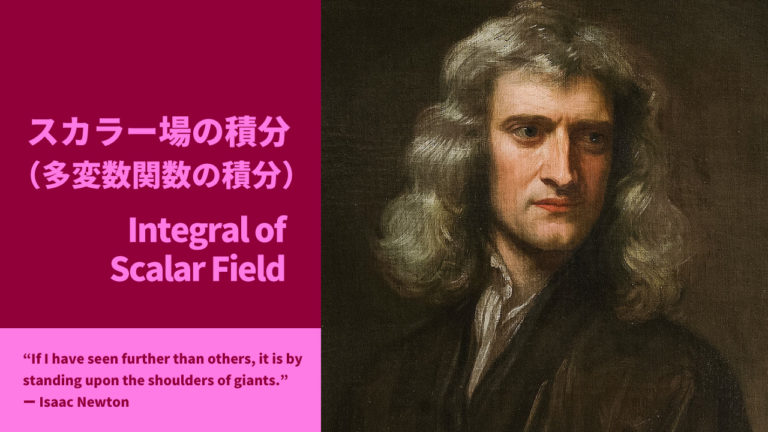
n次元空間上に存在する直方体領域上に定義された多変数関数が単調関数である場合、すなわち単調増加または単調減少である場合、その関数は領域上で多重リーマン積分可能です。
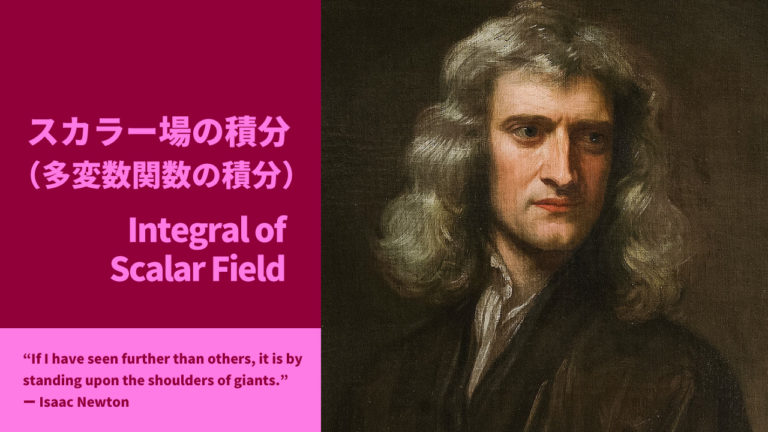
n次元空間上に存在する直方体領域上に定義された有界な多変数関数の上リーマン積分と下リーマン積分が一致することは、その関数が多重リーマン積分可能であるための必要十分条件です。
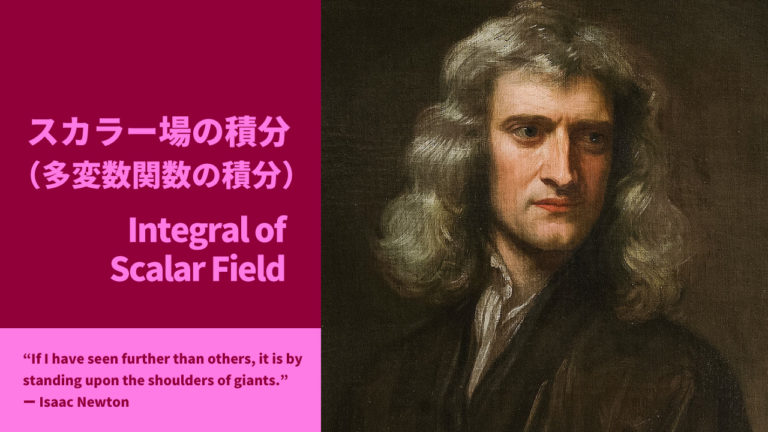
n次元空間上に存在する直方体領域上に定義された有界な多変数関数の上リーマン積分と下リーマン積分を定義するとともに、極限を用いて上リーマン積分や下リーマン積分を特定する方法を解説します。
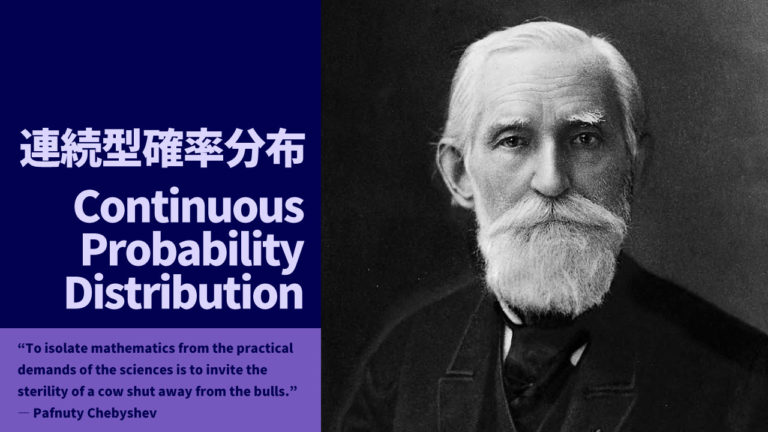
連続型の確率変数を単調増加変換した場合や単調減少変換した場合、または標準化した場合などについて、変換後の確率分布を求める方法を解説します。
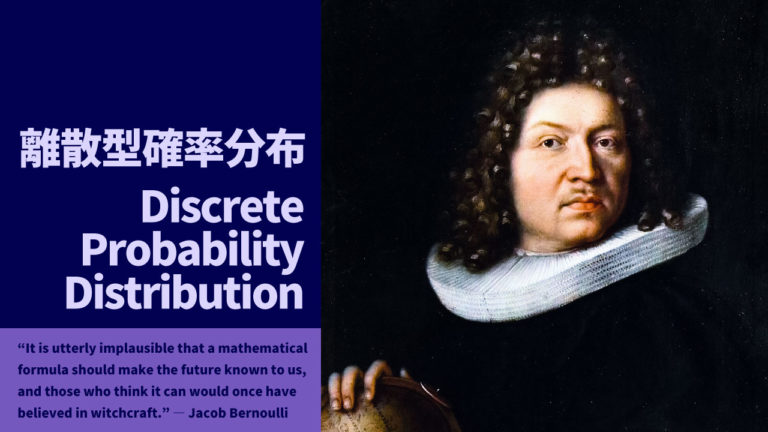
離散型の確率変数を単調増加変換した場合、単調減少変換した場合、単射との合成関数をとった場合、標準化した場合などについて、変換後の確率分布を求める方法を解説します。
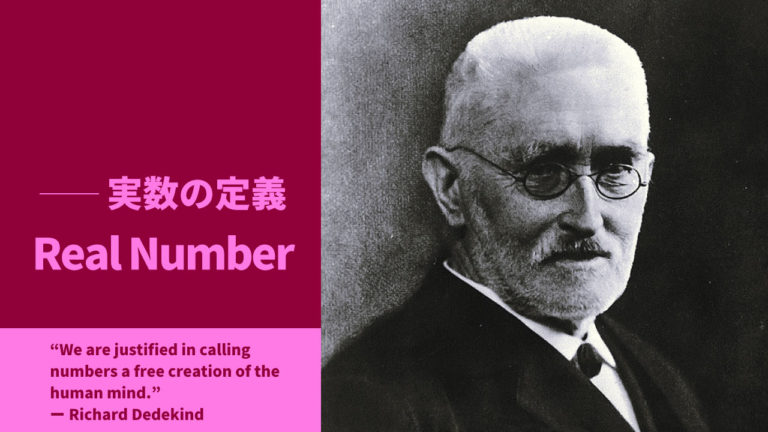
整数と非ゼロの整数の比として表現される実数を有理数と呼びます。有理数集合上に加法と乗法と大小関係を定義すると全順序体になります。その一方で、有理数集合は連続性を満たしません。
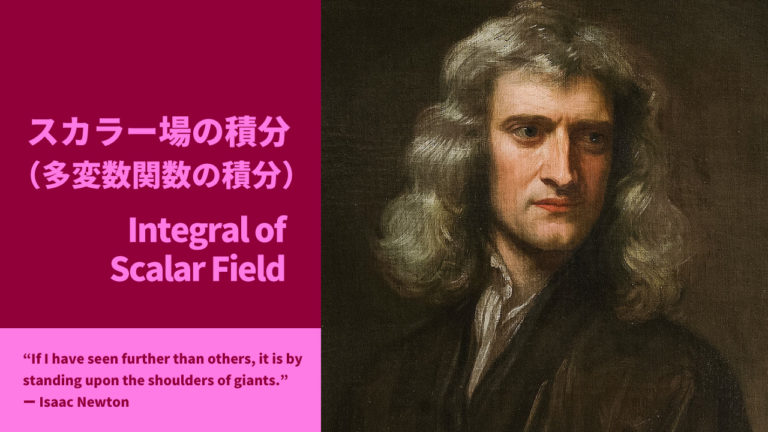
n次元空間上に存在する有界かつ閉な直方体領域上に定義された有界な多変数関数が多重リーマン積分可能であることの意味を定義するとともに、多重リーマン積分可能であること、ないし多重リーマン積分可能ではないことを判定する方法を解説します。
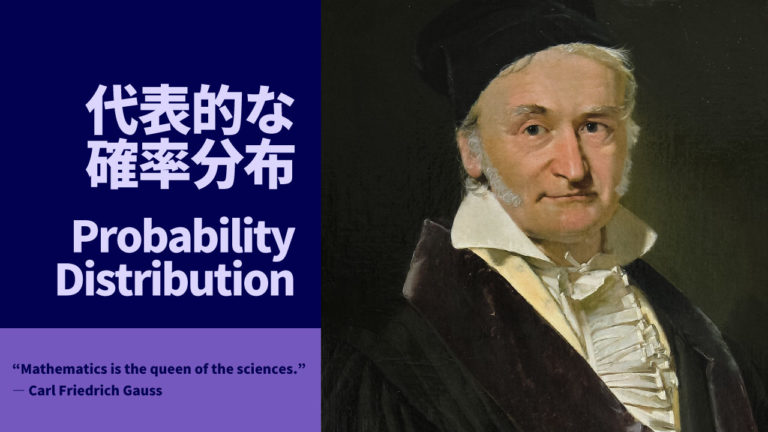
人間の身長の分布や試験の得点の分布など、現実の様々な局面において正規分布は登場します。また、試行を繰り返し行う状況において各回の結果が独立同一分布(i.d.d.)にしたがう場合、試行回数を限りなく増やすと、標本平均の確率分布は正規分布へ限りなく近づきます(中心極限定理)。
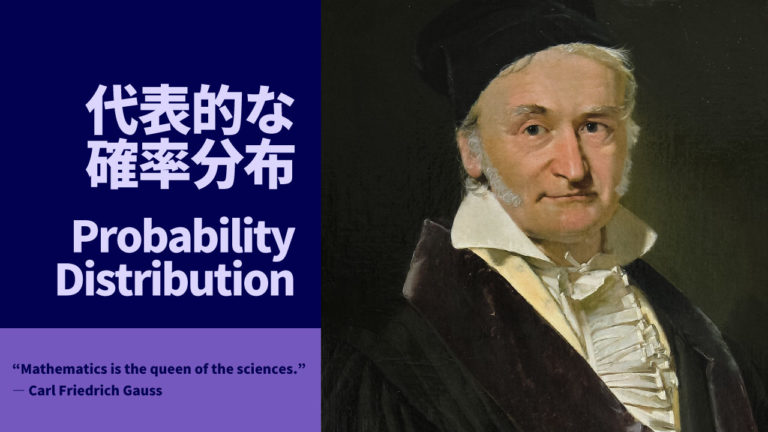
連続型の確率変数の確率分布を記述する確率密度関数が定数関数である場合、その確率変数は連続型の一様分布にしたがうと言います。連続型一様分布にしたがう確率変数を定義するとともに、その期待値と分散を求めます。
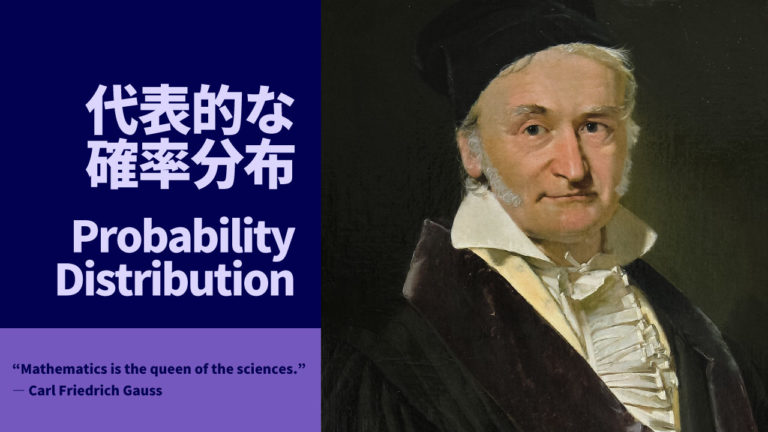
離散型の確率変数がすべての値を等しい確率でとる場合、そのような確率変数は離散型の一様分布にしたがうと言います。離散型一様分布にしたがう確率変数を定義するとともに、その期待値と分散を求めます。
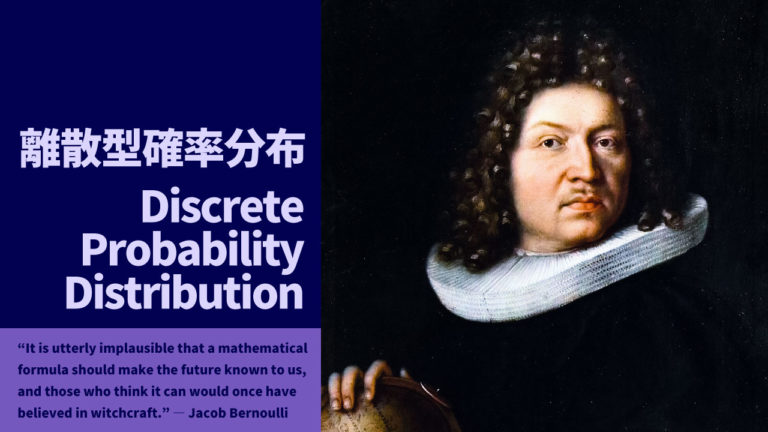
離散型の確率変数列が独立であるとともに同一分布にしたがう場合、その確率変数列は独立同一分布にしたがう(i.d.d.)と言います。