
非負値をとるルベーグ可測関数のルベーグ積分の加法性
ルベーグ可測集合上に定義された非負値をとるルベーグ可測関数が定義されている状況においてその集合を2つのルベーグ可測集合に分割した場合、個々の集合におけるルベーグ積分の和をとればもとの集合におけるルベーグ積分が得られます。

非負値をとるルベーグ可測関数のルベーグ積分の単調性
非負値をとる2つのルベーグ可測関数の間に一方的な大小関係が成立する場合、両者のルベーグ積分の間にも同様の大小関係が成立します。以上の性質を単調性と呼びます。

有界関数のルベーグ積分の加法性
有限測度を持つルベーグ可測集合上にルベーグ積分可能な有界関数が定義されている状況においてその集合を2つのルベーグ可測集合に分割した場合、個々の集合におけるルベーグ積分の和をとればもとの集合におけるルベーグ積分が得られます。

有界収束定理(有界なルベーグ可測関数列の極限のルベーグ積分)
有界なルベーグ可測関数列が一様収束する場合、その関数列のルベーグ積分からなる数列の極限は、一様極限のルベーグ積分と一致します。また、一様有界なルベーグ可測関数列が各点収束する場合、その関数列のルベーグ積分からなる数列の極限は、各点極限のルベーグ積分と一致します。

非負値をとるルベーグ可測関数どうしの和のルベーグ積分
非負値をとるルベーグ可測関数のどうしの和として定義されるルベーグ可測関数のルベーグ積分は、もとの可測関数のルベーグ積分どうしの和と一致します。

非負値をとるルベーグ可測関数の定数倍のルベーグ積分
非負値をとるルベーグ可測関数の定数倍として定義されるルベーグ可測関数のルベーグ積分は、もとの可測関数のルベーグ積分の定数倍と一致します。

非負値をとるルベーグ可測関数のルベーグ積分
有限な台を持つ有界なルベーグ可測関数のルベーグ積分の概念を定義するとともに、それを土台に、非負値をとる一般的なルベーグ可測関数のルベーグ積分の概念を定義します。

有界関数のルベーグ積分の単調性
有限測度を持つルベーグ可測集合上に定義された2つの有界関数の間に一方的な大小関係が成立する場合、両者のルベーグ積分の間にも同様の大小関係が成立します。また、有界関数の絶対値のルベーグ積分は、もとの関数のルベーグ積分の絶対値以上になります。

有界関数どうしの差のルベーグ積分
有限測度を持つルベーグ可測集合上に定義された2つの有界関数がルベーグ積分可能である場合、それらの差として定義される関数もまたルベーグ積分可能です。

有界関数どうしの和のルベーグ積分
有限測度を持つルベーグ可測集合上に定義された2つの有界関数がルベーグ積分可能である場合、それらの和として定義される関数もまたルベーグ積分可能です。

有界関数のルベーグ積分可能性とルベーグ可測性の関係
有限測度を持つルベーグ可測集合上に定義された有界関数に関しては、その関数がルベーグ積分可能であることと、その関数がルベーグ可測関数であることは必要十分です。
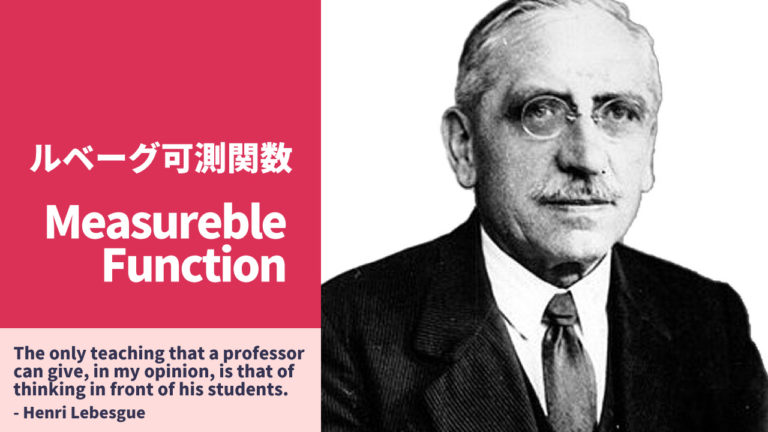
ルベーグ可測関数列の各点極限はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数列の各点極限もまたルベーグ可測関数です。特に、ルベーグ測度空間は完備であるため、ほとんどいたるところで各点収束するルベーグ可測関数列の極限もまたルベーグ可測関数になります。
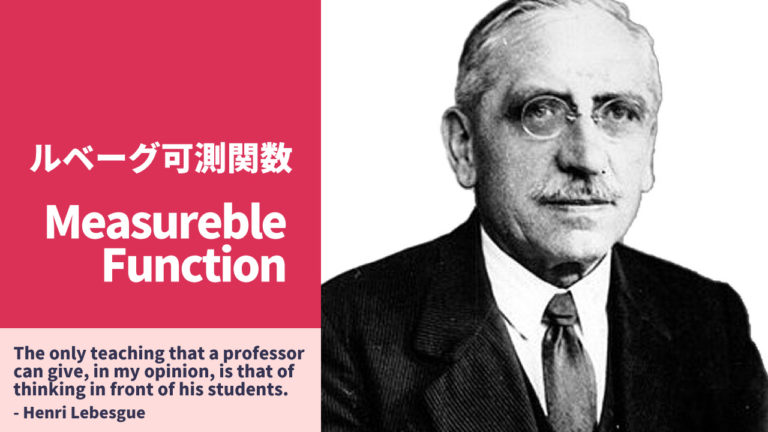
ルベーグ可測関数とほとんど至るところで等しい関数
ルベーグ測度空間は完備です。つまり、零集合であるようなルベーグ可測集合を任意に選んだとき、その任意の部分集合がルベーグ可測になります。したがって、ルベーグ可測関数とほとんどいたるところで等しい関数もまたルベーグ可測になります。
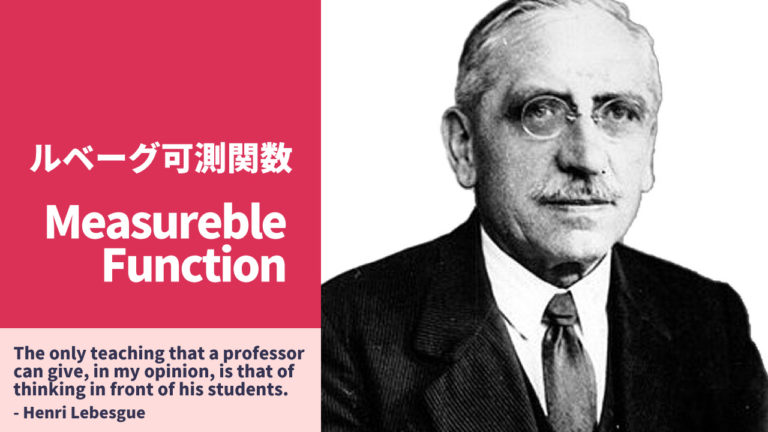
ルベーグ可測関数列の上極限関数と下極限関数はルベーグ可測関数
可測関数列が定める値からなる数列の上極限や下極限や極限を与える写像は可測関数です。また、拡大実数値可測関数列が定める値からなる拡大実数列の上極限や下極限や極限を与える写像は拡大実数値可測関数です。
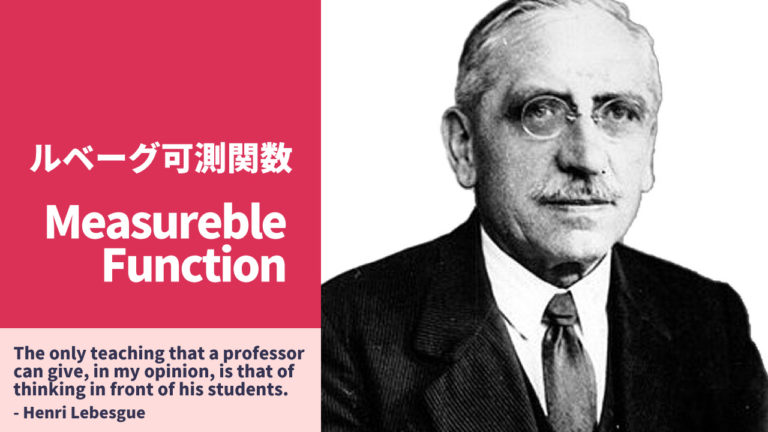
ルベーグ可測関数列の上限関数と下限関数はルベーグ可測関数
可算個の可測関数の値の上限や下限を値として定める写像は可測関数ないし拡大実数値可測関数です。また、可算個の拡大実数値可測関数の値の上限や下限を値として定める写像は拡大実数値可測関数です。
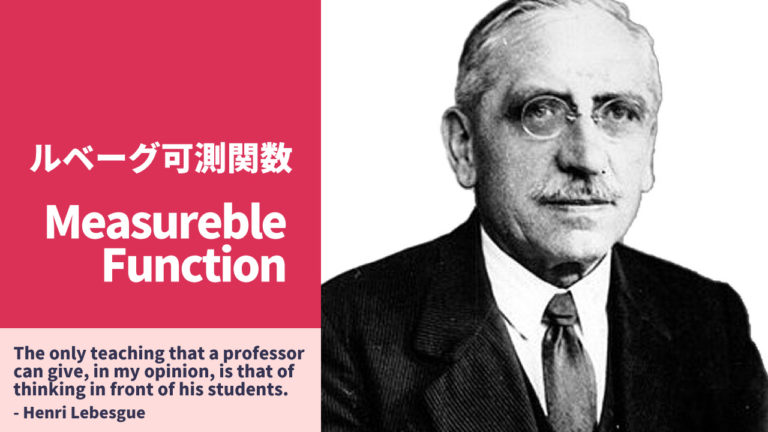
ルベーグ可測関数の最大値関数と最小値関数はルベーグ可測関数
有限個のルベーグ可測関数から定義される最大値関数と最小値関数はルベーグ可測です。また、有限個のボレル可測関数から定義される最大値関数と最小値関数はボレル可測です。
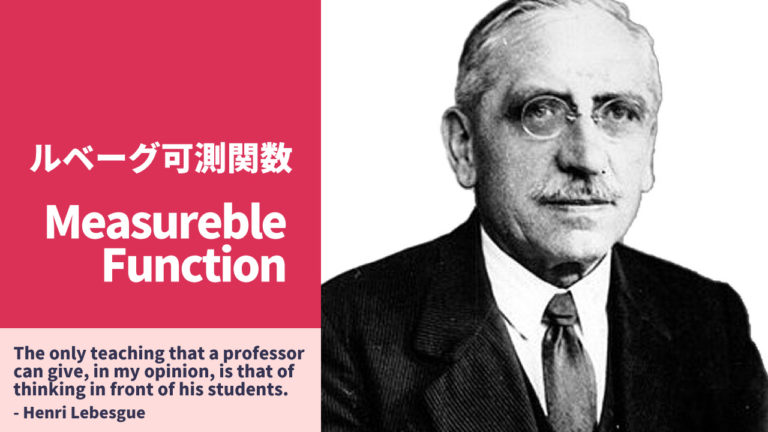
ルベーグ可測関数どうしの商はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数どうしの商として定義される関数はルベーグ可測関数です。また、ボレル可測関数どうしの商として定義される関数はボレル可測関数です。

有界関数のルベーグ積分とリーマン積分の関係
有界閉区間上に定義された有界関数がリーマン積分可能である場合にはルベーグ積分可能である一方で、ルベーグ積分可能な関数はリーマン積分可能であるとは限りません。したがって、ルベーグ積分はリーマン積分の拡張です。

可算個の事象族の独立性(可算個の事象族が生成するσ-代数どうしの独立性)
可算個の事象族の中から有限個の事象族を任意に選んだ場合にそれらが独立であるならば、もとの可算個の事象は独立であると言います。

有界関数のルベーグ積分(上ルベーグ積分・下ルベーグ積分)
有限な測度を持つルベーグ集合上に定義された有界関数の上ルベーグ積分と下ルベーグ積分の値が一致する場合、この関数はルベーグ積分可能であると言います。

単関数のルベーグ積分の単調性
有限な測度を持つルベーグ集合上に定義された2つの単関数がとり得る値の間に一方的な大小関係が成立する場合、両者のルベーグ積分の間にも同様の大小関係が成立します。また、単関数の絶対値のルベーグ積分は、もとの単関数のルベーグ積分の絶対値以上になります。

単関数どうしの差のルベーグ積分
有限な測度を持つルベーグ集合上に定義された2つの単関数の差として定義される単関数のルベーグ積分は、もとの2つの単関数のルベーグ積分の差と一致します。

単関数どうしの和のルベーグ積分
有限な測度を持つルベーグ集合上に定義された2つの単関数の和として定義される単関数のルベーグ積分は、もとの2つの単関数のルベーグ積分の和と一致します。
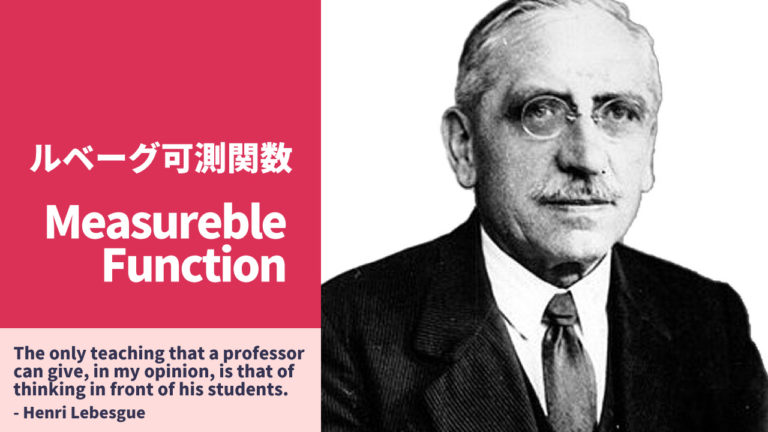
ルベーグ可測関数どうしの積はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数どうしの積として定義される関数はルベーグ可測関数です。また、ボレル可測関数どうしの積として定義される関数はボレル可測関数です。
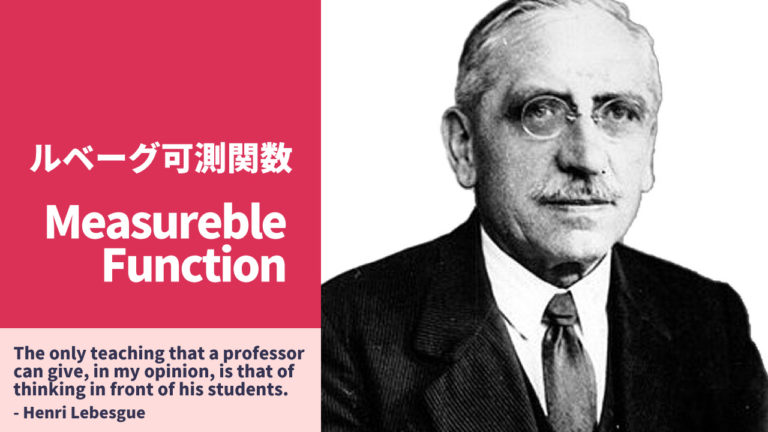
ルベーグ可測関数どうしの差はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数どうしの差として定義される関数はルベーグ可測関数です。また、ボレル可測関数どうしの差として定義される関数はボレル可測関数です。

ベクトルによって張られる四面体の体積
空間上の3つのベクトルの始点をあわせれば、それらのベクトルを3隣辺とする四面体が得られますが、その体積は3つのベクトルのスカラー三重積の絶対値の1/6と一致します。
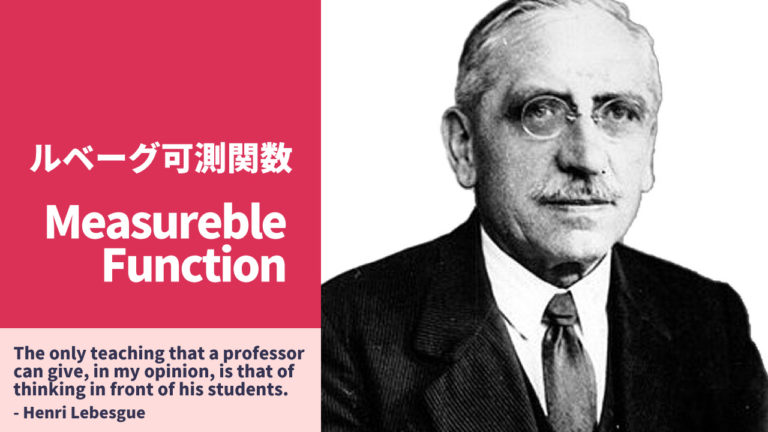
特性関数(指示関数)の定義と具体例
実数空間の部分集合が与えられれば、変数がその集合に属する場合には1を返し、変数がその集合に属さない場合には0を返す関数が定義可能です。これを特性関数と呼びます。特性関数が可測であることと、特性関数を定義する集合が可測であることは必要十分です。

ベクトルによって張られる三角形の面積
2つのベクトルの始点をあわせれば、それらのベクトルを隣辺とする三角形が得られます。2つのベクトルに関する情報から三角形の面積を特定する方法について解説します。
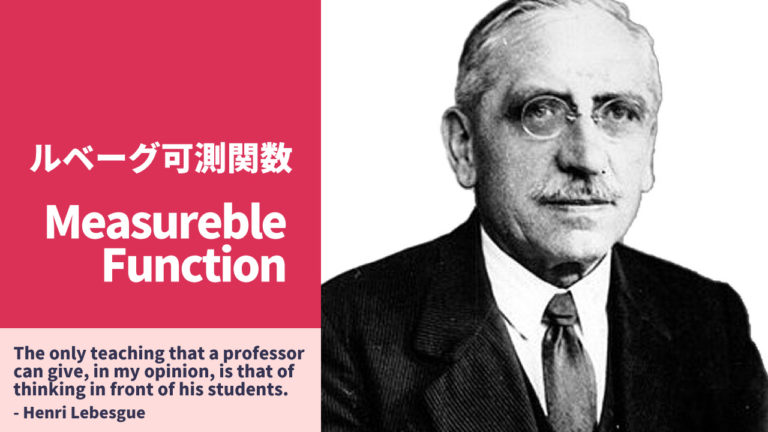
ルベーグ可測関数どうしの和はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数どうしの和として定義される関数はルベーグ可測関数です。また、ボレル可測関数どうしの和として定義される関数はボレル可測関数です。
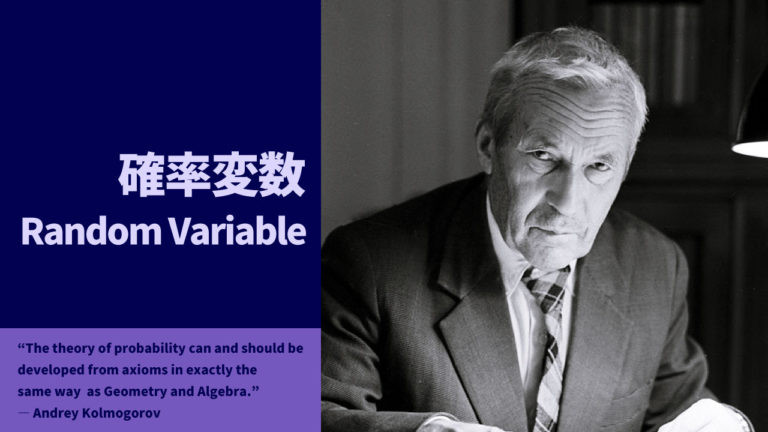
確率変数の分布関数
それぞれの実数に対して、確率変数がその実数以下の値をとる確率を特定する関数を分布関数と呼びます。分布関数の概念を定義するとともに、その基本的な性質について解説します。
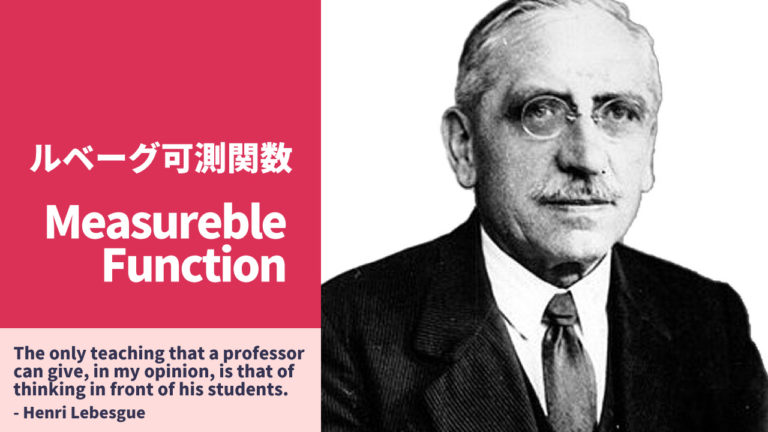
ルベーグ可測関数の定数倍はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数の定数倍として定義される関数はルベーグ可測関数です。また、ボレル可測関数の定数倍として定義される関数はボレル可測関数です。
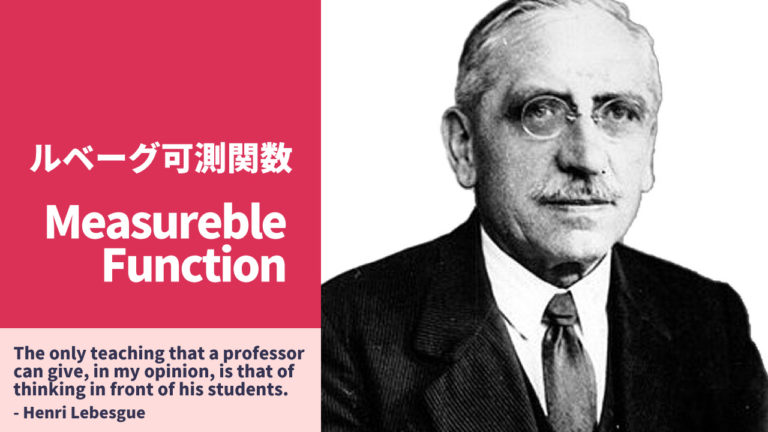
ルベーグ可測関数と連続関数の合成関数はルベーグ可測関数
ルベーグ可測関数とボレル可測関数の合成関数はルベーグ可測です。また、ボレル可測関数どうしの合成関数はボレル可測です。さらに、可測関数と連続関数の合成関数は可測関数です。
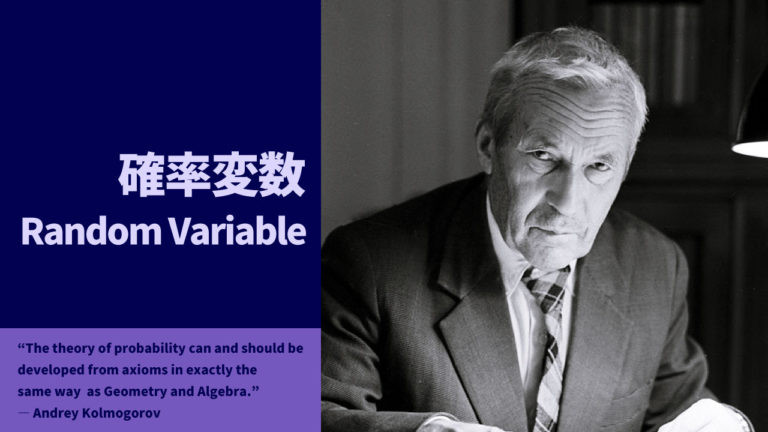
指示関数(指示確率変数)
可測な事象が与えられれば、その事象が起こる場合には1を返し、その事象が起こらない場合には0を返す確率変数が定義可能です。これを指示関数(指示確率変数)と呼びます。指示関数を用いれば集合演算を数値演算に置き換えて考えることができます。

大数の強法則(コルモゴロフの大数の強法則)
確率変数列が独立同一分布にしたがう場合、標本平均の列はもとの確率変数列が共有する期待値に概収束します。これをコルモゴロフの大数の強法則と呼びます。
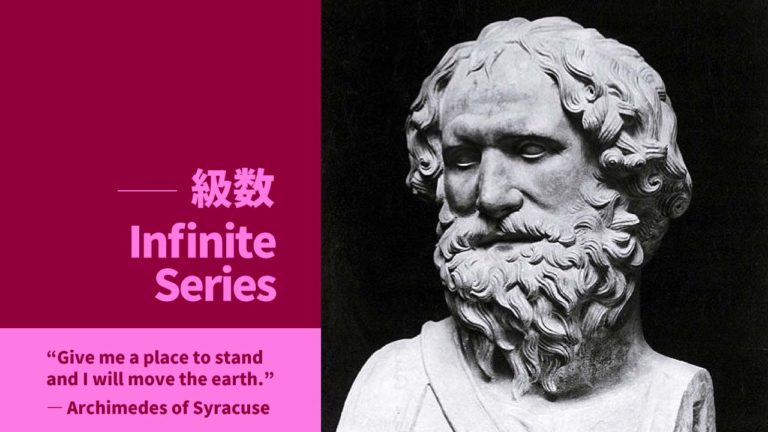
アーベルの補題とクロネッカーの補題
アーベルの補題と呼ばれる式変形テクニックを利用すれば、数列の積として定義される数列の部分和を扱いやすい形に変形できます。アーベルの補題を踏まえた上で、クロネッカーの補題と呼ばれる命題を示します。

コルモゴロフの三級数定理
独立な確率変数列の無限級数が収束するという事象はその確率変数列の末尾事象であるため、コルモゴロフの0-1法則より、その事象の確率は0または1のどちらか一方に定まります。その確率が1であるための必要十分条件を与えるのがコルモゴロフの三級数定理です。
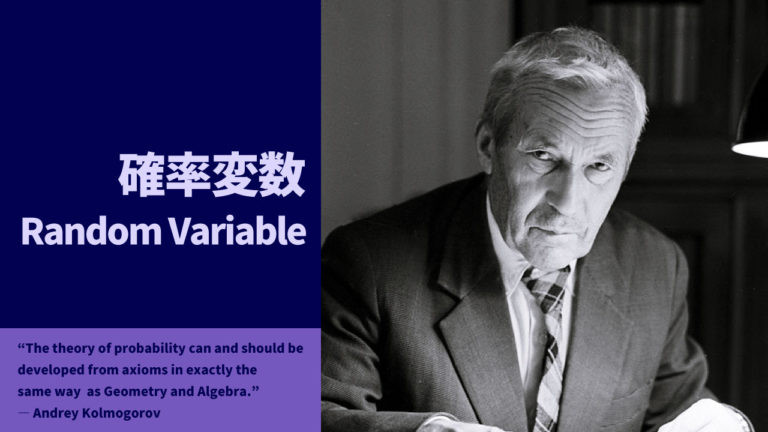
コルモゴロフの0-1の法則(確率変数列の末尾事象の確率)
確率変数列の要素である無限個の確率変数の分布の影響を受ける一方で、有限個の確率変数の分布の影響を受けない事象を末尾事象と呼びます。確率変数列が独立である場合、その任意の末尾事象の確率は0または1のどちらか一方に定まります。これをコルモゴロフの0-1の法則と呼びます。
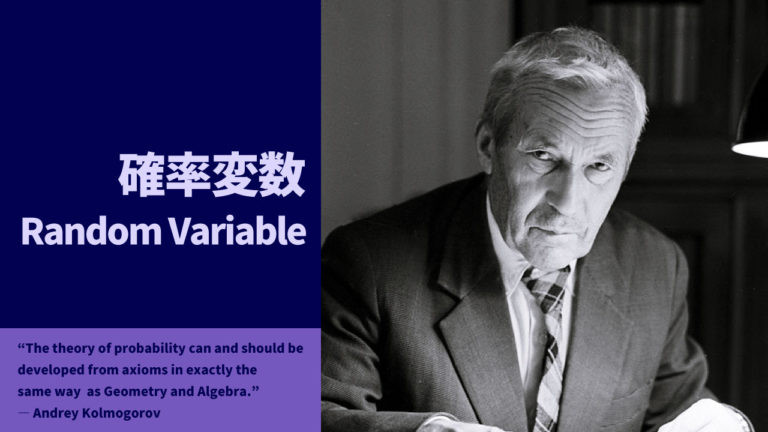
有限個の確率変数の独立性
有限個の確率変数が生成するσ代数どうしが独立である場合、それらの確率変数は独立であると言います。有限個の独立変数が独立であることを様々な形で表現するとともに、独立性を判定する方法について解説します。
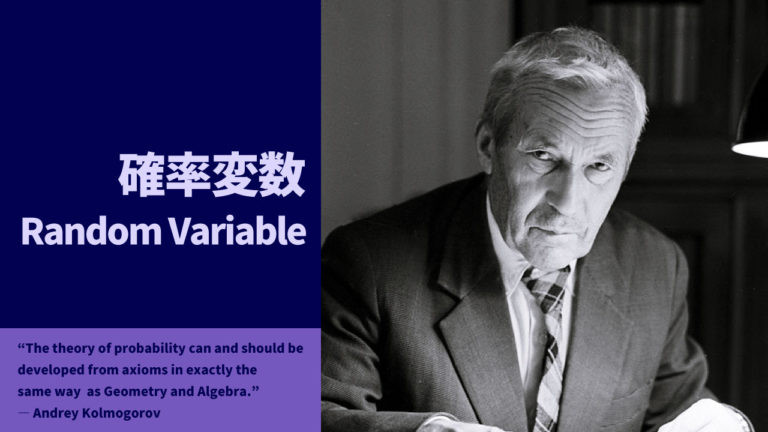
2つの確率変数の独立性
2つの確率変数が生成するσ代数どうしが独立である場合、それらの確率変数は独立であると言います。2つの独立変数が独立であることを様々な形で表現するとともに、独立性を判定する方法について解説します。
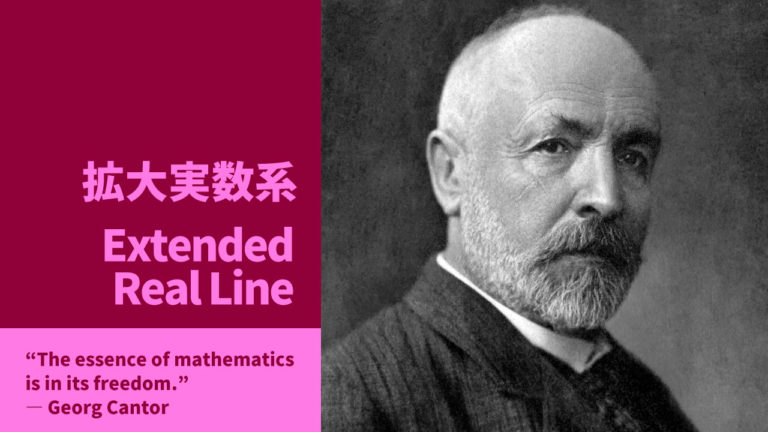
拡大実数値関数の上半連続性・下半連続性
任意の上方位集合が閉集合であるような拡大実数値関数を上半連続関数と呼び、任意の下方位集合が閉集合であるような拡大実数値関数を下半連続関数と呼びます。上半連続かつ下半連続であることと連続であることは必要十分です。

ボレル測度の定義
ルベーグ外測度の定義域をボレル集合族に制限することにより得られる写像をボレル測度と呼びます。ルベーグ測度と同様に、ボレル測度もまたσ-加法測度としての性質を満たします。
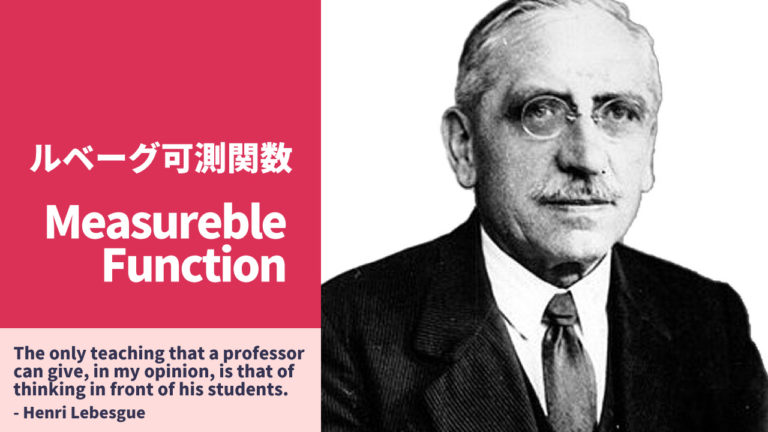
連続関数はルベーグ可測関数
ルベーグ可測集合上に定義された連続な実数値関数や拡大実数値関数はルベーグ可測です。また、ボレル集合上に定義された連続な実数値関数や拡大実数値関数はボレル可測です。
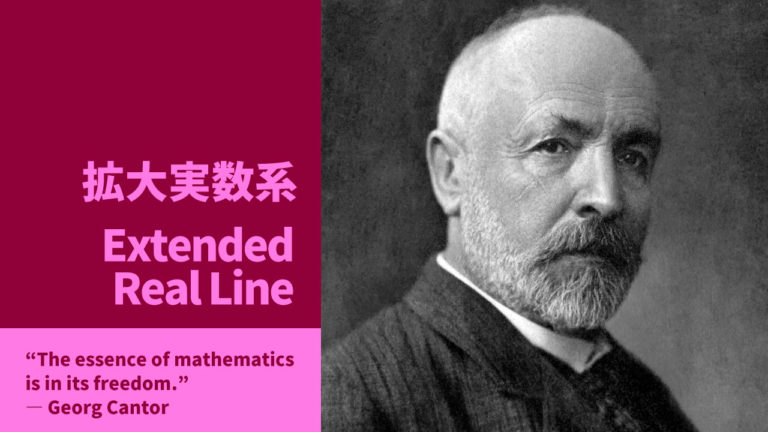
拡大実数値関数の片側連続性(右側連続性・左側連続性)
拡大実数系においては正の無限大と負の無限大が体系の中に含まれているため、拡大実数値関数の値が正の無限大や負の無限大であるような点においても、その関数が片側連続であるか検討できます。
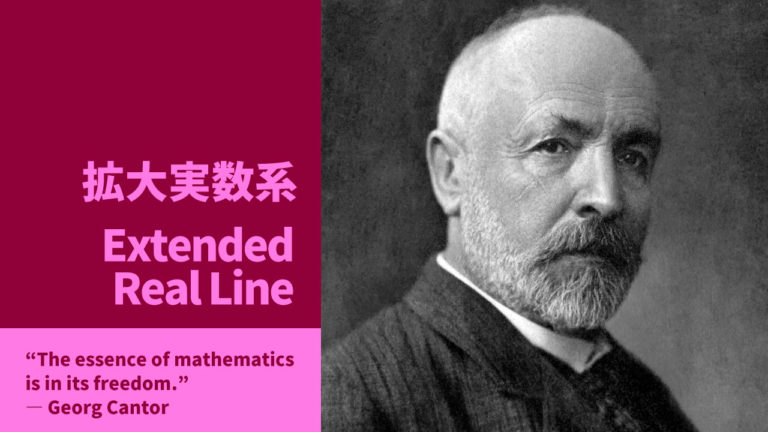
拡大実数値関数の片側極限(右側極限・左側極限)
拡大実数系においては正の無限大と負の無限大が体系の中に含まれているため、有限な実数だけでなく、正の無限大や負の無限大もまた拡大実数値関数の右側極限や左側極限の候補になります。
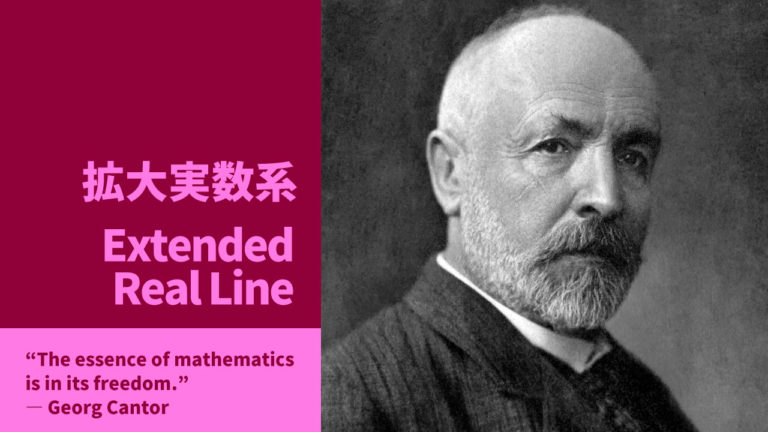
拡大実数値関数の連続性
拡大実数系においては正の無限大と負の無限大が体系の中に含まれているため、拡大実数値関数の値が正の無限大や負の無限大であるような点においても、その関数が連続であるか検討できます。
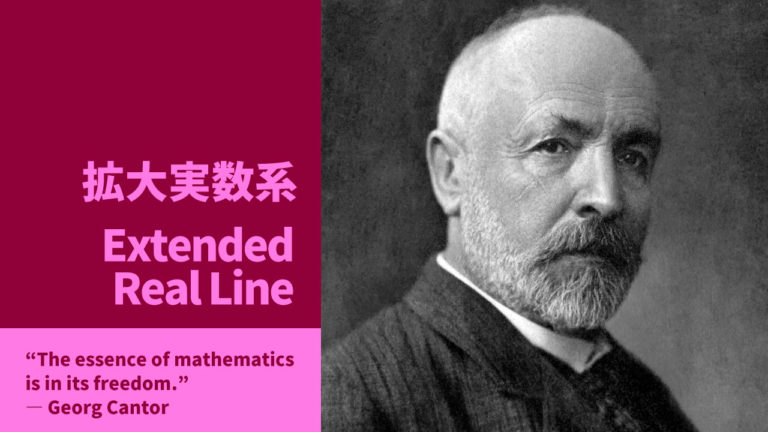
拡大実数値関数の極限(収束する拡大実数値関数)
拡大実数系においては正の無限大と負の無限大が体系の中に含まれているため、有限な実数だけでなく、正の無限大や負の無限大もまた拡大実数値関数の極限の候補になります。